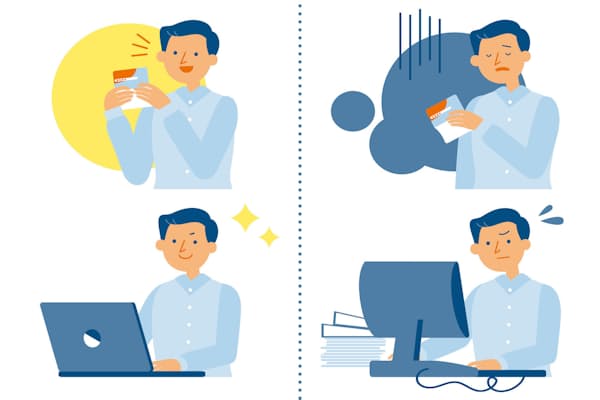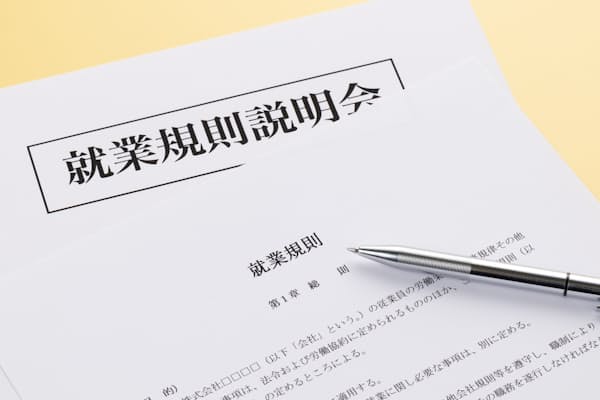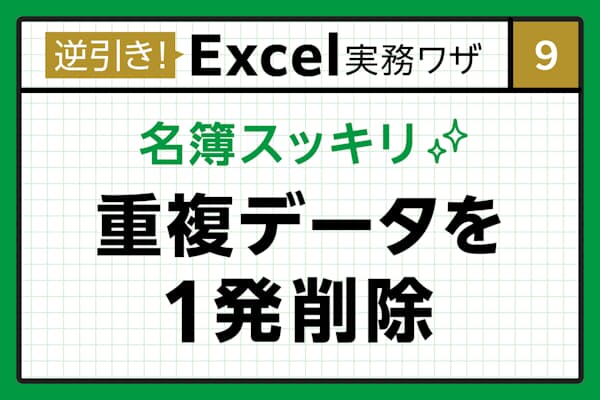テレワーク時代の人事評価 部下はどう行動すべき?
20代から考える出世戦略(104)

写真はイメージ=PIXTA
リモートワーク・テレワークの広がりは、私たちの昇給や賞与に関わる人事の仕組みにも影響を与えつつあります。同じ場所、同じ時間に働いていたからこそできたアピールも、リモートワークでは難しくなります。評価を受ける側として、実際に評価を受けるまでに意識すべきポイントを覚えておきましょう。
人事評価の現場が混乱している
コロナショックの1年でした。結果として、人事評価の現場ではこんなことが言われています。
「やるべきことが期中に変わりすぎて、そもそも評価の基準がわからない」
「上司と部下とのコミュニケーションが不十分で何を評価すればいいのかわからない」
そのため多くの会社で、2020年度だけの特別措置が検討されつつあります。その理由は、上記に示した、人事評価プロセスの機能不全が主なものです。
また、業界によっては個別事情から、特別措置を検討している場合もあります。なぜなら、業界によっては、人事評価をまともに行ったのでは、大半の従業員の評価が低くならざるを得ない場合もあるからです。ちなみにそのような状況にある一部の会社では、会社の業績が悪化した原因は従業員にはない。だとすれば従業員の評価を下げることは妥当ではない、という組合側からの要望に苦労している場合もあると聞きます。
それぞれの会社が実際にどのような結論を出すのか、ということはさておくとしても、激動の中で働いてきた私たちとしては、自分自身がとってきた行動や、生み出した成果を適切に評価してほしいと考えて当然です。
しかし会社からすれば「その行動や成果は何を基準に示しているのか」「努力した証拠はどこで確認すればよいのか」という仕組みと運用の課題を重要視しています。
そのような状況において、評価を受ける側が意識して行動すべきポイントは3つあります。