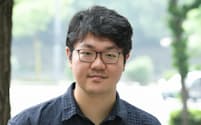「大切にされたい」が強める痛み 切ない悪化サイクル
愛知医科大学 学際的痛みセンター長 牛田享宏(3)

◇ ◇ ◇
牛田さんが愛知医科大学に赴任する前、高知医科大学(現在は高知大学医学部)に在籍した頃から話を説き起こす。
「2000年ごろに軽微な交通事故にて頚椎捻挫を受傷した50代の患者さんを診ていました。その人は、事故の後、1カ月くらいたってから、右手がバーッと腫れてしまって、手がとても冷たくなって、『焼けるように痛い』とか『もう風が当たるだけでも痛い』とか言うようになったんです。こういうのをCRPS(複合性局所疼痛症候群)と言います。最初の組織損傷に由来するものよりもずっと重度で治りにくい神経メカニズムや筋骨格系の異常が大きく絡んだ慢性疼痛、みたいな定義です。痛み刺激に対してより過敏になる『痛覚過敏』や、通常では痛みを引き起こさないような刺激によっても強い痛みが生じる『アロディニア』と呼ばれる症状を出してくることが多い病気です」
CRPS、複合性局所疼痛症候群は、字面はいかめしいけれど、複雑で(Complex)局所的な(Regional)痛みの(Pain)症候群(Syndrome)という意味なので、症状をそのまま記述しているともいえる。銃で撃たれた傷が癒えた後に残る灼熱痛(カウザルギー)などが歴史的には有名だが、今は共通するパターンを持つ様々な病態をまとめた症候群として扱われている。また、CRPSには特徴的な激しい局所的な痛みとして「アロディニア」がみられることが多い。これから後、何度か出てくるのでちょっとややこしい病名・症候名だが紹介しておく。
さて、見せてもらった写真には、アロディニアの右手から右肘までを手袋や包帯で保護した姿が写っていた。一方で手袋をしていない左手もかなり腫れており、こちらも充分すぎるくらい痛々しかった。サーモグラフィ写真もあって、右手は、左手に比べて皮膚の温度が低いことが見て取れた。
「当時の僕は、まだメカニズム論的な発想で、痛みが脳に伝わらなければ対処できるはずと思っていました。それで、いろいろな神経ブロック薬を試してうまくいかなかった後で、最終的に脊髄の痛み伝導路を外科的に切って焼くという手術をして、症状はよくなりました。右手でものをつかめるようになりましたし、手の皮膚の温度もすぐ改善したんですね。ただ脊髄を切ったので感覚がなくなってしまい、怪我を防ぐためにプロテクターをしなければならなくなったのと、その後、手が勝手にグーパー、グーパーするよう動いてしまったり、目の裏がかゆいだとか、ちょっと説明しにくい症状が出るようになりました」
常に怪我を気にしてプロテクターを身に着けたり、手が勝手に動いてしまうのは困る。ただ、それらの症状は、その前の激痛に比べたら、あくまで比較の問題としては「まし」なものだったようで、患者自身による術後の痛み評価や活動評価、そして抑うつの尺度は画期的に改善した。
「治療するまでは、奥さんが『もうお父さんの腕は棺桶に入るまで触れんと思っとったのが、触れるようになったからよかった』とか言ってくれて。それが今のニューロサイエンスの知識からいうと正しかったかは疑問だけど、当時できることということで、考え抜いて悩み抜いて患者さんとも話しながらやったことなんですね。この患者さんは、後に患者会を作ったときに会長を引き受けてくれて、『私のスライド、ビデオも、後の人のためになるなら使ってください』と言ってくれてるんです」
では、術後にあらわれた「手が勝手にグーパーしてしまう」「目の裏がかゆい」というような不思議な症状はどう説明すればいいのだろう。そもそもこういった患者の脳では何が起きているのかという問題に、牛田さんは取り組むようになる。

「刺激の信号が脊髄から脳に入るときに最初に通るのが視床です。だから、まず脳の中でも視床が重要だというのがセオリーで、僕は一時、MRIなんかを使って視床を見ていく研究をしていました。まず、健常者の右手を刺激して痛いというときには、脳では左右反転して、視床の左側が活動するんですね。でも、ずっと長いこと痛みを持っている人は、むしろその部分の活動が下がってるんですよ。つまり、活動が低下しているのに痛いんです。そして、視床の後の、感覚や情動の部位はちゃんと活動しているんです」
これは謎だ。痛みの刺激が脊髄を通って視床に入り、その後、脳内の痛み関連領域で痛いという感覚や痛みの情動につながっていくというセオリーからは想定外の結果といえる。
そこで牛田さんが試みたのが、「視覚刺激による疑似疼痛体験」という実験だ。
「アロディニアでいつも手袋をしているような人たちにMRIの中に入ってもらって、ビデオでとある動画を提示しました。目の前の画面に、手袋をつけていない手が出てきて、それをブラシでゴシゴシする、と。被験者は、自分の手がゴシゴシされているように感じてしまって、すごく不快になって、脳の痛み関連領域の反応もポンと出ます。でも、視床の活動は上がりません。動画を見るだけなら、そこには刺激は行っていないわけですから。これまで、脊髄や視床の問題だと思っていたのが、もっと高次のことが関わっているんだと示せた実験でした」

慢性の痛みをこじらせていくと、感覚器などからの痛みの刺激がなくても、いや、それを最初に感受する脳の部位の活動が低下していてすら、強烈な痛みを感じうる仕組みがもう脳の中に確立してしまっていることになる。なんとも恐ろしい話だ。
そして、こういった不思議な仕組みは、心理的・社会的な諸事情によって修飾され、やはり深みにはまる事例が出てくる。牛田さんが見てきた中には、痛々しくも、切ない事例がたくさんある。例えばこんなふうな症例について話してくれた。
「十代の女性で、僕らのところに来たときには、もう半年以上、車椅子を使っていて、薬も効かず、小児科の先生が困り果てていました。バレーの選手だということで、もとはといえば足を捻ったのがきっかけなんです。それで足に痛みが出て、ひどくなってきた、と。僕らは、まず、下肢を動かさないと拘縮してしまったらいかん、ということで強引にでも動かそうというのと、それから精神科の先生と一緒にカウンセリングをしつつ、薬は効いていないんだからやめましょうというふうにしていきました」
レントゲン写真を見せてもらったが、衝撃的と言ってよかった。
右脚の膝から下が写っているのだが、足首から先がまるで溶けかけているかのようにもやーっとしている。ズディック骨萎縮という、特殊な骨萎縮を起こしていたそうだ。単純に足首を捻っただけで、ここまでなるというのは信じられないレベルだった。
「結局、その子の治療でポイントになったのは、カウンセリングでした。まず神経性疼痛によく使われるプレガバリンって薬を飲んでいるときには、ぼーっとしてゆっくりとしか話せなかったのが、薬をやめてから自分からいろいろ話せるようになって、患者さん本人だけでなくて、両親とも別々にカウンセリングをやりました。そうすると、この女の子は、家庭内の事情でお父さんとお母さんが離婚したいというふうなことを、怪我をした時期にお母さんのほうから伝えられていたんですね。それがその後、ふと解決して、お父さんがずっといてくれることになって、病院にもお父さんが来てくれたらリハビリをめちゃめちゃ頑張るようになって、歩けるようになりました。こうやってみると、この足のアロディニアというのは何だったんだということですね。ちなみにこの子の足は、今でも左右差があって骨ももとどおりにはなってないです」
さらに興味深く、やはり痛々しい症例の紹介。
「20代の女性で、手をついて受傷、手首の靭帯損傷と言われて、手術を3回やっています。手のアロディニアだけじゃなくて、足も動かなくなってきて、右足底のアロディニアと、膝関節の拘縮が起きています。左右の足のレントゲン写真を比べると、右足側はもやっとして、骨がもう映らなくなってきています。これは、骨がもう薄くなってるんですね」
画像がぱっと目に入ってくるだけで、こっちまで痛くなってくるような、同時に胸が痛くなる事例だった。

「実は、この女性は、両親が小学生のときに離婚して、親類に育てられたんだそうです。外来には現在一緒に暮らしている父だという男性と来院するんですけど、その男性が一緒に診察室に入ってこないんですよね。娘がこんな足になってたら心配するはずですから、診察室に一緒に入ってこない親がおるわけがないと思って、おかしいなと思って聞いたところ、一緒に暮らしているけどお父さんではないと言ってました。背景には、さっきの女の子もそうですけど、痛みがあることによって、気遣ってもらえる、大切にしてもらえることが、痛みを固定するのに関係していたんです。『疾病利得(しっぺいりとく)』という言葉もあります」
疾病利得と書くと、何か身も蓋もない印象を受ける。文字通りに解釈すると、病気であることによって利益を得る、という意味になるが、そういう理解でよいのだろうか。
「まず、『侵害刺激』があると『痛み行動』が出ますよね。そして、『痛み行動』に報酬が出ると、『痛み行動』が強化されるということですね。痛いと訴える、痛そうな顔をする、じっとしている。そうすると、優しくしてもらえたり、お金が出たりすると。そうやって『痛み行動』が強化されて、抜け出せなくなるサイクルがあるんです」
こういった強化のメカニズム自体は、いわゆる「オペラント条件づけ」によるトレーニングそのものだ。人は、痛みを訴えたり、痛そうにするような、「痛み行動」をどんどん強化すべく自らをトレーニングしてしまう場合がある。そして、それは単に「痛いふり」というわけでもなく、今の事例のようなアロディニアと診断されるような激しく痛いものになって、レントゲンで骨がまるで溶けたように見えるような状態にまで至る。
そのプロセスを頭の中で想像してみると、本当にやるせなく、切なく、やはり痛々しい。
=文 川端裕人、写真 内海裕之
(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2020年1月に公開された記事を転載)
1966年、香川県生まれ。愛知医科大学医学部教授、同大学学際的痛みセンター長および運動療育センター長を兼任。医学博士。1991年、高知医科大学(現高知大学医学部)を卒業後、神経障害性疼痛モデルを学ぶため1995年に渡米。テキサス大学医学部 客員研究員、ノースウエスタン大学 客員研究員、同年高知大学整形外科講師を経て、2007年、愛知医科大学教授に就任。慢性の痛みに対する集学的な治療・研究に取り組み、厚生労働省の研究班が2018年に作成した『慢性疼痛治療ガイドライン』では研究代表者を務めた。
1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、肺炎を起こす謎の感染症に立ち向かうフィールド疫学者の活躍を描いた『エピデミック』(BOOK☆WALKER)、夏休みに少年たちが川を舞台に冒険を繰り広げる『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』『風に乗って、跳べ 太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。
本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、「マイクロプラスチック汚染」「雲の科学」「サメの生態」などの研究室訪問を加筆修正した『科学の最前線を切りひらく!』(ちくまプリマー新書)
ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。