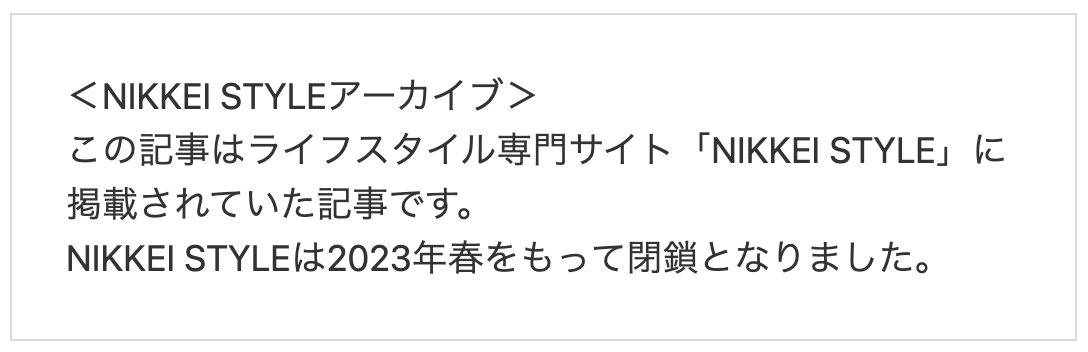夏も今はおいしいカキ 生食と加熱の差は鮮度ではない

冬が旬といわれているカキ。西洋では「カキはRのつく月に食べよ」とされており、1月(January)は英語のスペルで「R」がつく、今はまさに食べごろである。しかし、今はバイオ技術や流通の発展でカキの世界もちょっと変化しているようである。また、カキは「あたりやすい」ともされている。果たしてカキはほかの貝に比べて食あたりしやすいのか。カキに関する素朴な疑問について調べてみた。
カキは貝類の中でも特別な存在かもしれない。カキの専門店「オイスターバー」はもはやレストランの一つのジャンルとして確立している。昨今では、産地でよく見られる、BBQスタイルでカキを焼いて食べる「カキ小屋」が首都圏にも登場。「アサリ小屋」とか「アワビバー」とか「ホタテバー」は存在しないのに、カキは専門店がある。それだけカキは人々をひきつける魅力があるということだろう。
ここでふと疑問に思ったのは、オイスターバーや首都圏のカキ小屋が通年で営業していること。Rのつかない春の終わりから夏にかけての月はカキを食べてはいけないのではなかったか!? 全国で26軒を展開する日本最大級のオイスターバーチェーンで、オイスターバー文化を日本に広めたゼネラル・オイスター(東京・中央)に話を聞いた。
「『Oyster should not be eaten in any month whose name lacks an "r"(Rのつかない月のカキは食べるな)』は昔から伝わる欧米のことわざです。真ガキの放卵から産卵までの時期がちょうど5月(May)から8月(August)まであり、その時期の真ガキは食べられないため生まれた言葉といわれています」(同社広報担当の高瀬繭さん)
カキのおいしさといえば、あのプリプリの食感と、「海のミルク」とも呼ばれるクリーミーで芳醇(ほうじゅん)な味わい。産卵後のカキは身も細くなり、身に含まれる豊富なビタミンやミネラルなどの栄養も失ってしまうのだとか。つまり、あのプリプリの食感や、豊富な栄養素から来るうまみもなくなってしまう。「R」のことわざは暑い時期に差しかかるので食中毒にならないための「戒め」だと思っていたが、それよりも「おいしくないから」というのが大きな理由のようだ。
しかし、これは真ガキに限った話。高瀬さんは「日本ではその時期でもおいしく食べられる『岩ガキ』もありますし、海水温が低く産卵時期がずれ込むことで出荷できる北海道産や岩手県産の真ガキもあります。また、『三倍体』といって、特殊な技術を用いて産卵をしない真ガキも開発されています」と続ける。

日本で食べられる主なカキは「真ガキ」と「岩ガキ」。真ガキは水温が一定の高さになると一気に大量産卵するのに対し、岩ガキは時間をかけてゆっくり産卵する。そのため、身がやせ細ってしまったり、栄養がごっそり失われてしまったりすることがない。岩ガキは時間をかけてゆっくり成長するので、殻と身が大きく育ち、ジューシーな味わいが特徴だ。
「三倍体カキ」は広島県立水産海洋技術センターがバイオ技術を用いて真ガキを品種改良した広島県が誇るブランドガキ。産卵しないので、夏でも身が細ってまずくなることはない。
さらに「南半球では季節が真逆となるので、『R』のつかないその時期は冬。ニュージーランドなどから輸入すれば、ちょうどおいしいカキを食べることもできます」と、高瀬さんは日本のオイスターバーで生ガキを1年じゅう楽しめる理由を説明してくれた。
まとめてみると、北半球では真ガキはRのつかない5月から8月はおいしくないが、その時期は日本ではおいしい岩ガキもある。産卵しない真ガキもあるし、国内外から旬を迎えるカキを取り寄せられる。そのため1年を通してカキを食べられる、ということになろうか。つまり、「品種改良」や「流通網の発達」によって「Rがつかない月に食べるな」は、今は昔の話となっているようだ。
このようにあの手この手で「1年じゅう食べたい!」という熱狂的なファンがいる一方、一度「あたった」経験をしてからは「絶対に口にしない」というアンチもいる。これもカキが「特別な存在」と思うゆえんである。この「あたる」とはいったい何なのか。また、カキはほかの貝に比べてあたりやすいのだろうか。
高瀬さんによれば、「そもそもカキ自体が菌やウイルスを持っているわけではありません。カキは1時間に20リットルもの海水を吸って吐くといわれています。その過程でエサと一緒に海水にいる菌やウイルスも取り込んでしまうのです。カキは内臓も含めてそのまま食べます。そのため、体内に菌やウイルスがいる状態で食べるとあたるということになります」とのこと。
なるほど、ツブ貝やホッキ貝などは内臓を取り除いて刺し身にする。内臓を取り除いて食べる貝類に比べて、内臓も一緒に食べるカキは海水にいる菌やウイルスにあたりやすいといえるかもしれない。
「ですので、生食用のカキは、そもそも育つ海域が菌やウイルスが極めて少ない清浄海域であることや、出荷前に浄化するなどをして安全に仕上げることが必要です」と高瀬さん。

スーパーで売られているむき身のカキには「生食用」と「加熱用」がある。その違いは実はここにある。
「各県が定めた指定海域で獲れたもので、さらに厚生労働省が定める『生食用カキの規格基準』をクリアしたもののみが『生食用』として出荷できます。『加熱用』はそれ以外の海域で獲れたものとなります」(高瀬さん)
雑排水が流れ込む川の河口近くの海域はカキの栄養素となるプランクトンが多い半面、雑菌も多く、生食には向かない。そのため県は生食用カキを獲る、あるいは養殖する海域を指定している。生食用と加熱用の違いを「鮮度」の差だと思っている人も多いかもしれないが、実は獲れる海域の違いなのである。
さらに国の基準としてグラム当たりの細菌の数や洗浄などの加工方法、保存温度も細かく決められている。
つまり、生食用と加熱用を間違えない(加熱用を生で食べない)こと、加熱用は最後までしっかり火を通すことが重要である。
さて、先に「カキは貝の中でも特別な存在」と書いたが、私がそう感じる理由がもう1つあった。それはいろいろなお酒に合うこと! 日本酒にも合うし、ワインの世界では「カキといえばシャブリ」といわれ、フランス・ブルゴーニュ地方最北部シャブリ地区で作られたシャルドネ種の白ワインが合うとされる。
また、スコットランドでは生ガキにウイスキーをたらして食べるそうで、ウイスキーとの相性もいい。焼きガキとビールの組み合わせも最高だ。和洋さまざまなお酒に合う貝はカキを置いてほかにないのではないだろうか。
1年じゅう楽しめるようになったカキだが、真ガキは今が旬であることは間違いない。いろいろなカキ料理とお酒のマリアージュを楽しもう。
(ライター 柏木珠希)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。