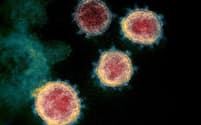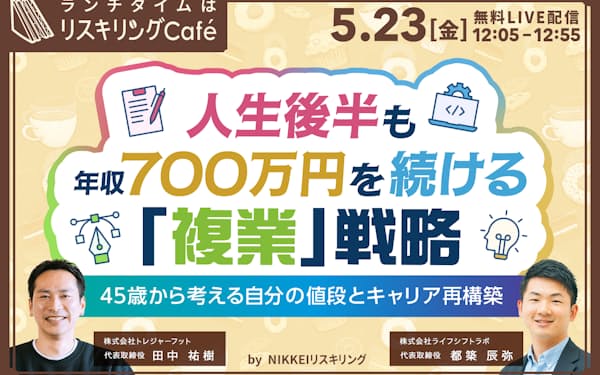2度目の感染あるコロナ 重症化?ワクチンは有効?
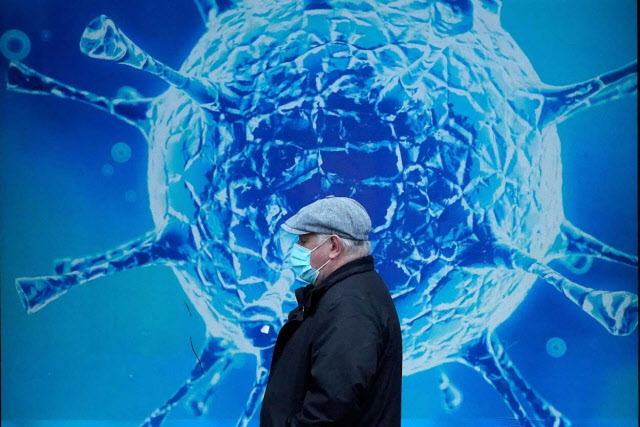
新型コロナウイルスには2度感染する。最近では、それが専門家の共通認識だ。今のところ、再感染の報告は世界で数百例とそれほど多くはないが、パンデミック(世界的大流行)が続けばその数字は増えるだろう。
既に感染して「免疫パスポート」を手にしたと思っていた人々にとっては、ありがたくない話に違いない。パンデミックが続く限り、自分には免疫があるのでマスクもソーシャルディスタンス(社会的距離)も必要ないというわけにはいかなさそうだ。2020年10月には、再感染による初の死者が報告された。オランダに住む89歳の女性だった。
他のコロナウイルスと同様に、新型コロナでも時間とともに免疫が失われる可能性がある。また、2度目に感染すると、1度目よりも症状が重くなるケースすらある。
20年10月12日付で医学誌「The Lancet」に掲載された論文の症例によると、4月上旬、米ネバダ州に住む25歳の男性が、のどの痛み、せき、頭痛、吐き気を訴え、検査で新型コロナ陽性と判定された。その後数週間の自宅隔離を経て2度再検査を行い、完全に回復したとされていた。
ところが5月末に再び発症。前回よりも症状が重く、呼吸困難に陥り、緊急治療室で酸素吸入を受けなければならなかった。4月と5月のウイルスの遺伝子をそれぞれ詳しく比べた結果、2度目は再感染だったことが明らかになった。
他の国でも、再感染の報告が相次いでいる。10月に、スウェーデンでは150人に関して再感染かどうかの調査を開始し、ブラジルでも科学者が95例を追跡している。メキシコでは、10月中旬の時点で258人が再感染したとしている。そのうち15%近くが重症化し、4%が死亡した。このデータセットからは、最初の感染で重い症状を示した患者は2回目の感染で入院する可能性が高いことが示されている。
「結論を言えば、再感染は極めて珍しいですが、確実に起こりうるということです」と、米ネバダ州ラスベガスにあるネバダ大学オーダーメード医療研究所の生物統計学者で、論文の筆頭著者であるリチャード・ティレット氏は言う。
感染の長期化ではなく再感染
2度目の発症が再感染なのか、それとも最初に感染したときのウイルスがまだ体内に残っていて、再び増殖したものなのかどうかを見極めるのは難しい。新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、症状が回復した後に何週間も体内に残ることがある。
したがって、再感染したかどうかは、患者の訴えや通常のPCR検査だけでは判断できない。再感染であることを明確に示す遺伝子解析が必要だ。
新型コロナウイルスは平均して15日ごとに変異を繰り返す。今のところ、こうした自然の変異はウイルスの性質や悪性度を変化させるほどの大きな変異ではない。しかし、2度目の発症が最初の時と同じウイルスによるかどうかを判別する根拠にはできる。
2カ月後に再び発症したネバダ州の男性の場合も、そうやって1度目のウイルスの残りが再び増殖を始めたものではないと結論付けられた。「2度目のウイルスは、6カ所に変異が見つかりました。ですから、別のところから感染したと考えて間違いないでしょう」と、ティレット氏は言う。
通常のPCR検査で再感染者を洗い出すことはできない。それには、患者の病歴と遺伝子解析の両方が必要だ。査読前論文を投稿するサイト「MedRxiv」に20年9月28日付で発表されたカタールの調査では、患者の病歴を基に243例が再感染の疑いありと特定されたが、それを証明するのに十分な遺伝物質が残されていたのはわずか4例だけだった。
再感染かどうかを知るには、検査手順を統一し、検体を長期間保存するように体制を整えなければならない。そこで、米疾病対策センター(CDC)は10月下旬になって、再感染の「判断基準」に関する新たなガイドラインを作成した。
ガイドラインでは、再感染が疑われるケースが発覚した場合、その地域の保健当局は遺伝子解析ができる研究室へ検体を送るよう勧められている。また、詳しい症状の記録と、最初の感染から再感染の疑いが判明するまでどれくらいの期間が空いていたかの報告も求められる。
この期間が、新型コロナウイルスに対する免疫がどれくらい持続するのかを知る重要な手がかりとなる。
季節性コロナは6~9カ月後にも再感染
人々が元の生活へ戻れるかどうかは、新型コロナへの免疫力の強さやその持続期間にかかっている。感染者がいかにして回復するのか、パンデミックを抑え込むためにどれほどの頻度でワクチンを接種すべきなのか、そしてソーシャルディスタンスは今後も続けるべきかなどが、それによって決まる。
しかし、どんな病気でもいえることだが、免疫が持続するかどうかを証明するには時間がかかる。新型コロナウイルスに関しては、専門家は他のヒトコロナウイルスの研究から再感染リスクを推測しようとしてきた。
たとえば20年9月14日付の学術誌「Nature Medicine」に発表された研究によると、4種の季節性コロナウイルスでは、12カ月後に再感染するケースが最も多かったが、早ければ6~9カ月後には再感染することもあるという。新型コロナウイルスにもこれがそのまま当てはまるかはわからない。季節性コロナウイルスは以前から存在し、人間もウイルスも時間をかけて互いに適応してきたためだ。
一般に免疫が低下するのは、特定のウイルスに対する抗体がなくなるせいであると、グルーバー氏はみている。病原体が侵入すると、免疫系によって抗体が作られ、細胞への感染を防いだり、毒素を中和したり、あるいは将来の感染も防ぐことができると広く考えられている。
ただし、抗体はすぐにできるわけではない。20年4月29日付で「Nature Medicine」に発表された調査では、新型コロナウイルスに感染すると、発症から2週間後までに抗体ができる人はおよそ95%に上ることが示されている。
グルーバー氏は、この抗体が時とともに減少し、再び感染することはあるかもしれないが、それは数年か数十年先の話だろうという。むしろ、一部の人は感染しても十分に抗体を作れなかった可能性の方が高い。
33歳の香港に住む男性の場合も恐らくそうだろう。この男性は3月に発症した後、8月に再び感染が発覚したが、この時は無症状だった。
だが、症状がなくても他の人に感染を広げることはある。グルーバー氏は、現時点で再感染した人の多くは、免疫系が弱いのではないかとみている。
さらに謎なのは、新型コロナに対する免疫自体は実は強固だという研究が最近になって出てきている点だ。20年10月27日付で「MedRxiv」に発表された、英国で36万5000人を対象に行われた予備的な研究など、新型コロナの抗体レベルが感染から2カ月以内に下がったことを示す研究結果がある一方、だからといって免疫が失われたわけではないと主張する別の研究もある。
免疫交響曲
実のところ、抗体が減少するのは通常の健全な免疫反応のしるしである可能性がある。20年11月19日付で同じく「MedRxiv」に公開された英国の研究では、感染後一斉に作られる抗体が時とともに減少しても、6カ月間は感染を防ぐ効果があると報告された。それによると、検出可能な抗体を保有していた1246人の医療従事者のうち、再感染したのは3人で、いずれも無症状だった。
米ミネソタ州ロチェスターにあるメイヨークリニックのがん専門医で医学教授のS・ビンセント・ラジクマール氏は、そもそも抗体のレベルだけで将来の感染の有無を測ることは難しいと話す。
人間の免疫系をオーケストラに例えてみよう。このオーケストラには、多才な演奏者である免疫細胞の「B細胞」と「T細胞」がいる。
新型コロナウイルスが侵入すると、体の中で盛大な第1楽章が始まる。一部のB細胞が直ちに反応して、最初の1~2週間で抗体を大量に生産する。それと同時に、キラーと呼ばれるT細胞の集団がコロナウイルスに侵された細胞を探し出し、自死させる。別のタイプのヘルパーと呼ばれるT細胞が、これらの危機対応を誘導する。
もし、どの部分であってもハーモニーが崩れれば、曲全体が乱れ、被害を抑えるどころか逆に拡大させてしてしまう。そして、これらすべてが起こっている間、メモリータイプのB細胞とT細胞が学習し、記憶する。これらのメモリー細胞は、感染症から回復した後も、将来の再感染を防ぐべく舞台裏でひそかに待ち構え続ける。
2002~2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)コロナウイルス感染者が、回復して何年もたった後も検出可能なメモリーT細胞を保有していたことが、7月に研究者らの間で話題になったのはそのためだ。
そして最新の研究で、新型コロナウイルスの感染に反応したB細胞とT細胞も、長期間残存するらしいこともわかってきた。20年11月16日付で「BioRxiv」に掲載された論文は、185人のコロナ患者の免疫の記憶がどれくらいの期間保持されるのかを調査した。
それによると、6カ月後にはまだ大量のメモリーB細胞が残っており、メモリーT細胞は減ったものの半分ほど残っていた。同じく「BioRxiv」に20年11月2日付で発表された別の論文によると、春にウイルスに感染して軽症だった100人の医療従事者が、抗体をわずかしか生産しなかったのに、やはり6カ月後には強いT細胞を保持していたことがわかった。
2度目は軽症で済むとしても
だが、体がコロナウイルスに再びさらされた場合、これらの免疫の記憶が実際にどのように働くかはわかっていない。炎症反応を起こして、前回よりも重症化してしまうのか。それとも、一部で報告されているように、前回よりも軽症で済むのだろうか。
普通の風邪を引き起こすコロナウイルスと同様であるとすれば、新型コロナウイルスの再感染も、ほとんどの人にとっては軽症で済む可能性が高いと、ラジクマール氏は言う。ということは、香港の男性が一般的なケースで、重症化したネバダ州の男性は珍しいケースと言えるだろう。
ワクチンについて言えば、現時点では、最先端のmRNAワクチンで活性化されるB細胞とT細胞がいつまで感染を防いでくれるのかを十分なほど長期的に調べた研究はない。マウスを使った最近の2カ月間の研究では、期待が持てそうだが。
とはいえ、2回目は軽症で済むとしても、もうマスクは不要と考えるべきではない。再感染すれば、1回目と同じく人に感染させることはある。そして、感染させた相手が重症化してしまうことだってある。
ラジクマール氏は、世界が集団免疫を獲得するまでは、マスクの使用を継続すべきだと忠告する。「ほとんど症状が出なかったら、再感染に気付かないかもしれません。ですから、一度感染した人でも他の人のためにマスクを着用すべきです」
(文 SARAH ELIZABETH RICHARDS、NSIKAN AKPAN、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック 2020年12月4日付の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。