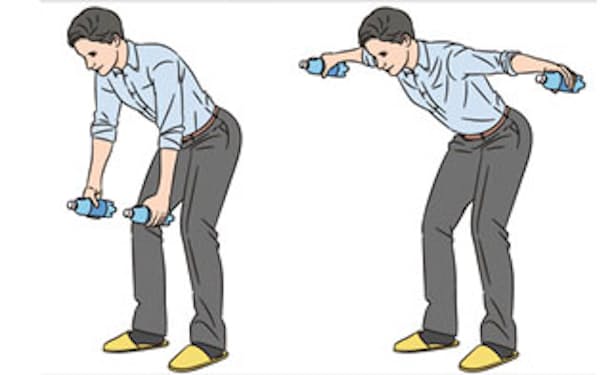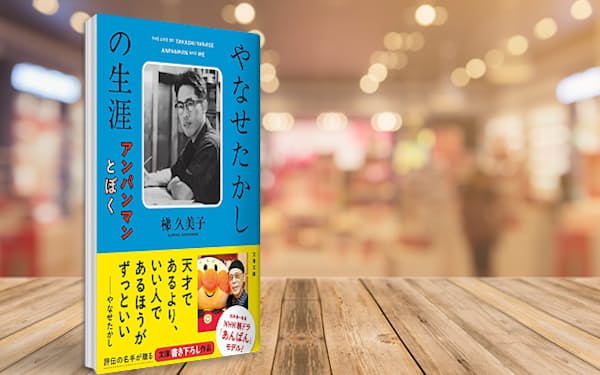就活も仕事も「答えは現場に」 弁護士・菊間千乃さん
通年採用時代の就活のトリセツ(10)

こんにちは、法政大学キャリアデザイン学部教授の田中研之輔です。ニューノーマルな大学生活、いかがお過ごしですか? オンラインで実施される講義と対面で実施されるゼミ、ハイブリッドな形で展開される大学生活に戸惑いを抱えている方も少なくないようです。2年生や3年生は、オフィスでのインターンを経験できなくなり、これから迎える就活に不安を抱いていると耳にします。
コロナ禍では、企業もオンラインで説明会や選考を実施したり、学生もツイッターなどで情報収集したりと、どんどんオンライン化が進んでいます。私が一つ危惧しているのは、オンラインでの就活が常態化することで、企業に訪問したり、社会人から直接アドバイスを聞いたりというリアルな機会を通じて得られる、「プレ社会人」化への変容機会が絶対的に不足していくことです。
就活は「点」ではなく、「線」です。就活をはじめた翌日から激変する、能力が急に向上するスーパーマンは、この世に存在しません。就活の一つ一つの経験を通じて、社会人としての必要なコミュニケーションを身体化していくのです。
今回、皆さんと共有しておきたいのは、これまでの日常が継続できなくなった時にこそ、ビジネスシーンで求められる心構えが露呈するということなのです。
これまでの当たり前が通用しなくなった時に、何を考え、どう行動するのか? 人は二つのタイプにわかれます。一つは、目の前の変化に翻弄され、不満や文句ばかりを述べ続ける現状不満型タイプ。もう一つは、目の前の変化に適合し、問題の解決策を導き出す未来創出型タイプ。もし前者だと感じるなら、大学生活の間に後者になれるように日々を過ごすようにしてください。基礎的な知識を覚え、単位を習得するだけが大学の学びではありません。大学生活を通じて、社会を生き抜いていくのに必要な心構えを「身体化」させることが大切なのです。未来創出型タイプの人は変化の中でどうすべきかを考え、自ら主体的にキャリア形成を続けていきます。
今回は弁護士の菊間千乃さんにインタビューを実施しました。菊間さんは早稲田大学を卒業後、フジテレビのアナウンサーとして長年活躍。その後、弁護士へと転身し、今も数多くのテレビ番組でコメンテーターをされています。弁護士として、それから主体的にキャリアを築いてきた先輩として、菊間さんに社会人になっていく上での心構えを聞きました。
同じ事実でも、評価は人によって異なる
――SNS(交流サイト)で就活の情報収集をする学生が増えていますが、その延長で、内定者や新入社員が会社のことについて投稿し、トラブルになるケースもあるようです。法律の専門家としてどう見ていますか。
SNSに投稿した内容は、一瞬にして世界に拡散されることがあるというリスクをあらためて理解しておいてください。何のために書くのか? 誰に向けて書くのか? しっかり考えて投稿するようにしてください。内定先の企業のことだって、書いてはいけないということではなく、これを内定先の会社の人が見るかもしれないという意識を持つことが大事だと思います。対面でのコミュニケーションで言えないこと、言わないことをSNSだから書けるというのは、危険な使い方。SNSは、パブリック(公)の場なんですから。
――就職先が「ブラック企業」かどうかを気にする学生も多いですが、見分け方はありますか。
ブラック企業とは何か? その言葉が意味することを自分なりに考えてみてください。そもそもA社はブラック企業、B社はホワイト企業だと、一枚岩的に捉えることは間違っています。また、誰かが言っていることをうのみするのも間違いです。同じ事実でも、それに対する評価は、人によって違うからです。オンラインでも対面でも構いませんが、OB・OG訪問をしましょう。自分の目で企業を見分けることが大切です。ネットでの情報をうのみにして、入社して、その後、思い描いていた働き方と違ったとしても、誰かのせいにはできません。
30以上のアルバイトで多様な世界知る

――弁護士として様々な相談を受けるなかで、改めて仕事や働き方について感じたことは何ですか。
人は誰しもスマートに生きられないということです。信じた人に裏切られたり、人間関係がこじれたり、トラブルに発展してしまうこともある。日々の法律相談や裁判を通して、「自分の目で物を見る」ことの大切さを改めて感じています。弁護士はいろいろな方にお会いしますが、外から入ってくる情報は参考程度。自分がその人と会って感じた気持ちのほうが圧倒的に大切だと思っています。
基準をネットの情報や世間の評判にすることは、とても楽ですけど、それって自分で考えることを放棄しているのではないかなと思います。法律違反はもちろんアウトですが、では法律で規定されていなければなんでもセーフかというと、そんなことでもないと思うんですよね。専門家じゃないからわからないということでもない。ルールがあったとしてもその背景には何があり、何を信用するのか、それぞれが考え、自律的な共存関係を創っていくのが大事だと思います。
――「自分の目で見る」ということは学生時代から意識していたのでしょうか。
私は大学時代に工事現場、イベントコンパニオン、警備員など30を超えるアルバイトを経験しました。私は自分の知らない社会を経験するという目的でアルバイトをしていたので、大学生が多く集まるようなアルバイトは、あえて選択しませんでした。工事現場で「早稲田大学の菊間です」と言っても通用しないわけです。日ごろ出会ったことのない人たちと、見たことのない世界で働くことを重視しましたね。
――アナウンサー新人時代に学び、今の仕事に生かされていると感じることは何ですか?
印象深いのは、沖縄での基地問題の取材です。東京で新聞や書籍で事前の下調べをして、自分の中でこんなインタビューが取れれば、とイメージしながら、いざ現地に赴くと、どうも違う。カメラを回さないという条件でお話しをしてくださる方もいました。何かを思っていても、人前で言わない人もいる。基地がないと生きていけない立場の人もいる。
基地問題は立場によって様々な意見がありますから、聞けば聞くほど、何をリポートしていいかわからなくなって、ディレクターと1時間くらい議論しましたかね。間接的な情報をたくさん仕入れて、知ったかぶりをしてはいけない、答えは現場にしかない。自分で見て聞いたことをリポートする、そんな基本的なことを沖縄取材を通して学びました。

「ネタ帳」持ち歩いた就活時代
――就活ではどんなことを意識しましたか?
明確に言えるのは、準備の大切さです。私は小学校6年生からアナウンサーになりたい!と思っていたので、準備は早かったですね。先のアルバイトもアナウンサーになるためですし。人と違う準備で言えば、フリートークの練習です。アナウンサー試験には、当時は必ず1分程度のフリートークがありましたので、どんなお題を出されても、打ち返せるように(笑)、常にネタ帳を持ち歩き、何かあればメモしていました。
――大学生へのアドバイスをお願いします。
自らの目を養ってください。スマホから入手できる情報のみを頼りにするのではなく、自ら行動して、自ら判断することを習慣化させてください。知ったかぶりは、あなたの成長のブレーキです。知らないことは恥ずかしいことじゃない。大学生だから飛び込める現場があります。
そして、社会のルールは誰からか教わるものだけではなく、実践的に学んでいくものでもあるということを知っておいてください。挫折、失敗も貴重な経験です。社会に出たときに経験する厳しさに、少しばかりの免疫をつけておきましょう。
実践していく中で大事なことは、何事も自分軸で動くということです。自分を起点にして、物事を捉える。会社に過度の期待を抱き、依存してはいけません。私は「安定」という言葉が嫌いなんです。先が見えている人生は、つまらないじゃないですか。私はどんな環境でも、楽しみながら生きていますよ。
◇ ◇ ◇
実際に、行動されているからこその具体的なアドバイスをいただきました。できることを自らまず、一つでいいのでやってみましょう。大学生がいない世界へと一歩踏み出してみる。社会人が集まるオンラインイベントでもいいでしょう。やらないで悩むことは、一番もったいない。一つ一つ経験しながらキャパシティーを広げていきましょう。
東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。1995年、フジテレビ入社。バラエティーや情報・スポーツなど数多くの番組を担当。2005年、大宮法科大学院大学に入学。07年、司法試験の勉強に専念するため、フジテレビを退社。09年。大宮法科大学院大学修了。10年司法試験合格、司法修習を経て弁護士となる。11年、弁護士法人松尾綜合法律事務所に入所。19年、早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻知的財産法LL.M.コース修了。紛争解決、一般企業法務、コーポレートガバナンスなどの分野を中心に幅広く手がけている。
1976年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員をつとめる。日本学術振興会特別研究員(SPD:東京大学) 2008年に帰国し、法政大学キャリアデザイン学部教授。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。企業の取締役、社外顧問を19社歴任。著書25冊。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術』(日経BP社)など。最新作『ビジトレ―ミドルシニアのキャリア開発』(金子書房)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。