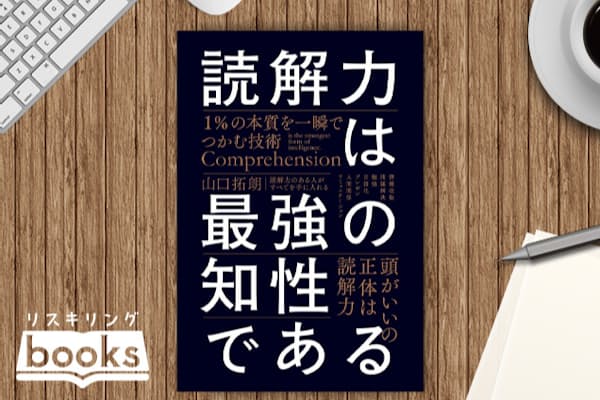日本企業の働き方にほころび 行動が次の成功への道
人事のプロ、八木洋介氏に聞く(4)

年長者が牛耳る「上へならえ」体質は企業の競争力をそぎかねない(写真はイメージ) =PIXTA
ニューノーマル(新常態)時代の幕開けとともに、企業や私たち個人はどう行動しなければならないのか。米ゼネラル・エレクトリック(GE)の日本法人及びアジアの人事責任者やLIXILグループ副社長(人事・総務担当)を歴任した八木洋介people first(ピープルファースト、東京・世田谷)代表の視点から、困難な現代を生き抜くヒントを提供する。4回目は、「年功序列」「終身雇用」と同じ文脈で語られることが多いメンバーシップ型の限界について考える。
「あの上司、いなくてもいいよね」。若手社員から、冷ややかに見られる管理職が増えています。新型コロナウイルス禍で在宅勤務が浸透した結果、こうした不都合な現実があぶり出されました。「企業や組織に貢献できない人材」がはっきりみえてきたのです。年功序列のレールに乗って昇進し、業務プロセスをチェックするだけの管理職ポストが不要となってしまいました。
年功序列はもはや機能しません。過去に有効な時代があったことは認めましょう。戦後、1ドル=360円という固定相場制の時代がありました。当時の日本企業は欧米企業を手本に優秀な製品を安く作ればよかったのです。目の前に手本が明示されているわけです。機能や役割を分担して、決まったことを秩序のもとに実行する「すり合わせの妙」によって、手本を超える成功体験を重ねてきました。経験と序列の維持という手法が有効に機能していたのです。
しかし、1971年の金・ドルの交換停止(ニクソン・ショック)以降、環境が大きく変わりました。変動相場制へ移行。円が強くなったことで、日本の労働力が相対的に割高になりました。家電やクルマといったモノの需要が飽和し、消費者の嗜好も成熟化、多様化。さらにバブル崩壊後は低成長が基調となり、「前例踏襲でもうまくいく」というアプローチが機能しなくなったのは自明です。
いまや自らが問いを立て、仮説を検証し、社会に存在価値を認めてもらう。こうしたプロセスを、当事者意識のもとに反復することで、イノベーションをもたらす戦い方が必要となりました。手本や正解がない以上、試行回数を増やすなかで精度を上げ、成功確率を向上させる営みが必然となります。年功序列を含めて、経験値に優位性を認め、既存秩序を維持することは非合理的な存在にならざるを得ません。今回のコロナ禍ではっきりした事実といえるでしょう。