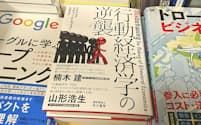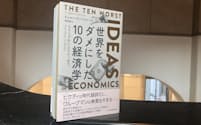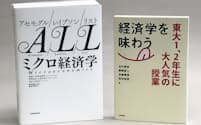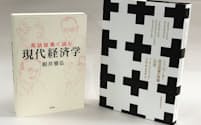経済理論をビジネスに活用 広がるメカニズムデザイン

経済学者が理論を応用して新しい制度を設計し、ビジネスの世界などで活用する「メカニズムデザイン(制度設計)」が日本でも広がり始めています。
三省堂書店有楽町店(東京都千代田区)は9~10月、経済学をテーマとするブックフェアを開催しました。その中の10冊を対象に、マジョリティー・ジャッジメント(MJ)と呼ばれる方法を使って読者の人気投票を実施しました。投票対象の本ごとに読者に6段階の評価をしてもらい、評価を集計して順位を決める方式です。この方式では、似通った対象が票を食い合う「票の割れ」を防ぎ、人気に応じた順位がつく可能性が高いとされています。同時に、1人1票の多数決での人気投票も実施しました。
仕掛け人はメカニズムデザインの専門家である慶応義塾大学の坂井豊貴教授です。結果をみると上位1、2位は両方式とも同じでしたが、3位はMJと多数決で結果が分かれました。「MJで3位の本は広い層から高い評価を受けたので、様々な売り場や棚に置くとよい。一方、多数決で3位の本は特定の層から支持されているので、その層に絞り込んでアピールすればよい」と分析します。
坂井氏は、今年のノーベル経済学賞の授賞対象となったオークション理論の応用にも積極的です。今夏には、ブロックチェーン技術をエンタメに応用しているGaudiy(東京・渋谷)と共同で、新たなオークション方式を開発しました。同社はデジタルゲームのカード販売を新方式で実施したほか、他の事業でも活用する計画を示しています。
不動産オークションを手掛けるデューデリ&ディール(東京・千代田)とも協力しています。同社の今井誠取締役は「事前に収集した買い手のデータを分析し、オークション方式のほうが売り手にとってよいのかなど、経済理論を応用すると様々なポイントが明確になる」と言います。年間の契約件数は60~70件と1年前に比べて2倍近くに増えました。
オークション理論の応用は世界各地で進んでいます。政府による周波数免許の売却、IT(情報技術)企業によるネットの広告枠の売却が代表例です。求める側と求められる側の最適な組み合わせを考える「マッチング理論」も、臓器移植、研修医と病院の組み合わせ、学校の選択といった幅広い分野で役立っています。
経済理論はもちろん、万能ではありませんが、日本でも応用できる余地は大きそうです。理論を生かせる分野を発掘し、実用性を高めていくのは、経済学者の役割の一つといえるでしょう。
■坂井豊貴・慶応義塾大学教授「理論だけでは世の中は変わらない」
経済理論を活用して制度を設計する「メカニズムデザイン」が日本でも徐々に広がってきました。第一人者である、慶応義塾大学の坂井豊貴教授に、現状と今後の見通しを聞きました。
――不動産オークションの会社には、どんな形で協力しているのですか。

「2018年4月からデューデリ&ディール社のチーフエコノミストを兼務しています。個々の案件というよりも、全体について助言しています。例えば、ある物件を売るときにオークションをするほうがよいのか、その物件を買いたいという特定の人に売るほうがよいのかを判断するのはなかなか難しいのですが、その判断基準を理論的に作ります。過去の取引データも活用し、売り主にとってどちらが得かを類推します。購入を希望する人が事前に希望額を伝えるとき、どの程度、さばを読むかも理論やデータを使えば推測できます」
「18年11月、同社の今井誠取締役とともに『オークション・ラボ』を立ち上げ、月に1回のペースでメカニズムデザインに関するワークショップを開いています。米国などに比べると日本ではなおメカニズムデザインは十分に活用されていません。自分たちの取り組みやアイデアを話し、関心がある人たちと交流したいと思ったのです。これまでに21回開催し、ビジネスパーソン、官僚、学者、僧侶など多様な人が参加しています。その模様を近著『メカニズムデザインで勝つ』で紹介しています」
――三省堂書店有楽町店は、マジョリティー・ジャッジメント(MJ)という投票方式で10冊の経済学書を対象に人気投票を実施しました。デューデリ&ディール社とともに運営に協力したそうですが、MJと経済理論とはどんな関係があるのですか。
「投票用紙をインプット、投票結果をアウトプットと考えると、投票の方式は関数の一種といえます。良い関数を考えれば、良い結果が出るのです」
――今回の投票結果は。
「MJと同時に多数決による投票も実施しましたが、両方式ともに1位は伊藤公一朗著『データ分析の力』、2位は山口慎太郎著『「家族の幸せ」の経済学』でした。3位はMJでは、大竹文雄著『行動経済学の使い方』で、多数決では瀧澤弘和著『現代経済学』と結果が分かれました」
――経済理論を応用するときに注意すべき点はありますか。
「学者はしばしば現実と理論モデルの世界を混同します。現実が理論モデルの世界に当てはまるのなら、うまくいく場合が多いのですが、そうでない場合もあります。例えば、オークション理論では落札した人が購入するのが当たり前の設定になっていますが、現実には落札したのにお金を払わない人がいます。そんな事態はオークション理論の教科書や論文にはどこにも書いてありません。入札者に条件をつけて絞るといった対応が必要になります。実際にビジネスに携わる人と、きちんとコミュニケーションをとって、使える理論と使えない理論を選別していく作業がとても大切です」
――日本ではメカニズムデザインはさらに広がるのでしょうか。
「オークション理論とマッチング理論ではかなり状況が異なります。マッチング理論が適用されるのは、臓器移植、医者と病院の組み合わせなど社会的に難しい問題が多いため、活用事例はそれほど増えないでしょう。一方、オークションは金銭の世界、あっさりした市場経済の話であり、売り上げや利益にプラスになればよいと考えるなら、利用すればよいのです。ブロックチェーンの世界も、発行コインの売買などでオークション理論を応用しやすい分野の一つです」
――学者のビジネスへの関与に対して、学界内には慎重にすべきだとの声もあります。
「自分が向き合っている相手にどれだけ価値をもたらしているのか、と考える学者は少ないと思います。学者のキャリアパスの中では、そういうマインドが育ちにくいため、ビジネスの世界に足を踏み入れるのに慎重な人が多いのです。しかし、制度設計の問題でも、理論だけでは世の中は変わりません。実際に使っている例を見ると、人は行動を変えます。理論を応用した成功例を増やすことが大切なのです。私はこれからも草の根運動を続けるつもりです」
(編集委員 前田裕之)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。