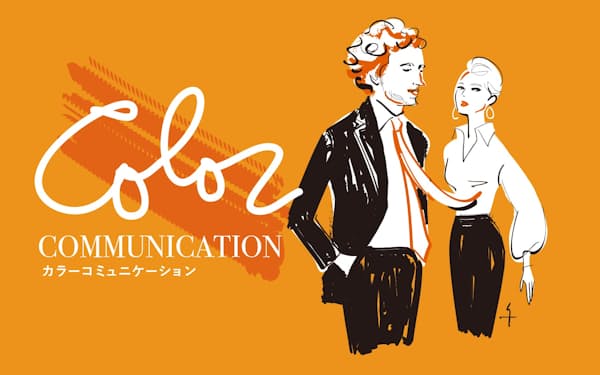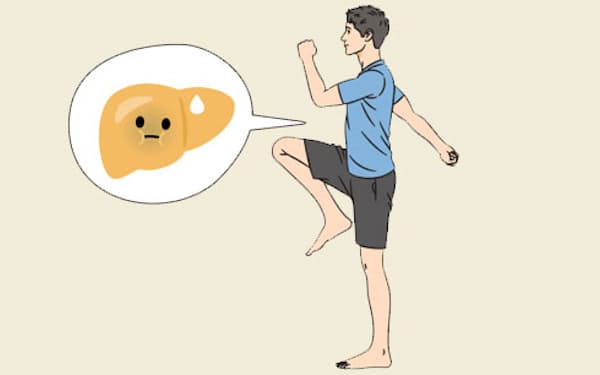進化するレトロ喫茶 元格闘家3代目が放つ新メニュー

昭和の風情を色濃く残す、東京・新宿のレトロ喫茶店「但馬屋珈琲店」。いずれその経営を引き継ぐ3代目が、思案に思案を重ねている。
コロナ禍をどうしのぎきるか。歴史を重ねた店の何を変え、何を変えないか。そして新たな成長の糧を何に求めるのか……。静かに悩んでいるだけではない。元格闘家らしく軽いフットワークで、攻めのパンチも繰り出し続ける。
新宿駅西口、JRの線路に沿って伸びる飲み屋街「思い出横丁」の入り口に、但馬屋珈琲店の本店がたたずむ。喫茶店の開業は1964年。明治・大正時代の商家をほうふつとさせる、武骨な木組みに漆喰(しっくい)風の白壁を合わせた外観で、木造の店内にも時代の香りが満ちる。1、2階にカウンターが据えられ、一隅には自在鉤(かぎ)が下がる。ちょっと薄暗くて、壁にはタバコのヤニが染みついて。ここには「今風」の片りんもうかがえない。
運営するイナバ商事(東京・新宿)の常務で、創業家3代目の倉田光敏さんは「この空間こそが大事な売り物」と話す。
「少し男性的ですが、店のイメージは今のままでいいと思います。この雰囲気でホッと一息つくお客は多い。時代が変わってもこれは変えちゃいけない。のんびり本を読んだり、アイデアをひねり出したり。そんなことができる空間の提供が、喫茶店本来のあり方かな、と思う」

コンセプトは「大人のひととき 通の味」。中心ターゲットのイメージは「時間とお金にゆとりのある40~50代の紳士」だという。自家焙煎(ばいせん)のネルドリップで淹(い)れるコーヒーは深煎りでしっかりコクのある一杯。種類は豊富で、各国の代表的銘柄のほかマラウィ産ゲイシャ(750円)や、ジャコウネコのフンから採った豆「コピルアック」(3500円)もそろえる。大半は750円とやや高めだが「この空間の入場料と思っていただけたら」。
現在、但馬屋系列の店は本店を含めて新宿に4店(うち1店は別会社が運営)、吉祥寺に1店ある。店構えやメニューは店ごとに一部異なるが、おおむね本店を踏襲している。複数店を抱え、自家焙煎で、フルサービスのレトロな純喫茶、という業態はそれほど多くない。「その"かけ算"がウチの勝負のしどころ」と言う。
コロナショック前のコーヒーブームの主役は、サードウエーブ系カフェだけではない。昔ながらの純喫茶に対する消費者の関心も呼びさました。多種多様な店が百家争鳴する日本独特の喫茶文化はこの時期、一段と厚みを増した。但馬屋もその恩恵に浴した業者の一つ。本店は一見、常連客以外は入りにくそうな雰囲気も漂うが、若いカップルや一人客も頻繁に訪れる。
もっとも、個性の現状維持だけでは生き残れない。同じレトロ喫茶でも、経営の事情は単独店とは異なる。光敏さんは家業に参加した2015年以来、矢継ぎ早に改革の手を打ってきた。

高校3年生でキックボクシングを始め、大学生時代にプロ転向。「手堅く勝ちに行くタイプでした」。7年ほどで引退し、小岩井乳業に入社した。そこで7年間、営業に携わった後に、父の雄一さんが社長を務める家業に身を投じた。
入社した時の印象は「正直、数字は厳しいと思った」。ピーク時に7店あった店舗数は5店に減っていたが、15年には入居していたビルの建て替えで、さらに2店を閉鎖。「何かを変えなきゃ、と思って、まず卸売りを始めました」
キックボクシングと営業で鍛えた根性と行動力で、コーヒーのドリップバッグを高級スーパーに売り込んだ。今では350店以上の店頭に但馬屋の商品が並ぶ。
「とにかく店の知名度と、ブランドロイヤルティーを高めるのが狙いでした。おかげさまで、スーパーで商品を買って気になった人が店に来たり、逆に店のお客がドリップバッグを買ったりと相乗効果が生まれました」

その後、新宿駅南口と吉祥寺に相次ぎ出店して5店体制に戻り、一時落ち込んだ売上高も回復。「ここ2、3年は黒字で、特に昨年はいい感じの黒字でした」。その矢先にコロナショックが襲来したものの、卸売りと豆の通販で致命傷は避けられた。今や卸売りは一つの店舗の売り上げを上回る規模に成長している。
コーヒーそのものでは差別化を念頭に、本店のメニューに「世界遺産コーヒーシリーズ」と銘打つ2商品を昨年導入した。
一つはネパール産の豆を使った「ヒマラヤン アラビカ」(850円)。現地の業者の売り込みに応じて直接調達に踏み切った。香りも苦みも繊細で、スッキリとした風味が味わえる。もう一つはエクアドル産の「ガラパゴス ブルボン」(同)。ガラパゴス諸島のサンタクルス島で有機栽培された豆を、つてをたどって調達した。苦みは優しく、柔らかで甘い後味が楽しめる。
さらに変わり種を一つ。その名も「西伊豆海底熟成コーヒー」(950円)。海底熟成ワインにヒントを得て、密閉した生豆を約半年間、西伊豆の海底に沈めてみた。以前、コーヒー蒸留酒を沈めると、確かに味が変わった。それならコーヒーも、というわけでエイジング(熟成)を試してみると、まろやかな風味に仕上がったことから10月末に数量限定で販売した。「来年以降の継続販売も検討できれば」という。

客単価を上げるためコーヒーとペアリングする商品としてメニューに加えた濃厚なテリーヌショコラの評判はいい。他社との連携にも積極的で、雑貨メーカーと期間限定コラボカフェを開いたり、江崎グリコ「ポッキー贅沢(ぜいたく)仕立て」のプロモーションでコラボしたり。「結婚式の引き出物などの体験型ギフトに掲載した、ネルドリップ教室や飲み比べ体験には若い世代から引き合いがあります」
一方、全店にPOSレジを導入し、店ごとに異なる客層に合わせてメニューの見直しを進め、店員のシフトも合理化した。この物静かなファイター、とにかく手数が多い。
「まずはコロナ後の残存者利益を得るために、無理にターゲット層は広げず、ディフェンシブにやってきました。それでもがむしゃらに、しつこく、いろんなことは試していきます。ダメだったらやめればいい」
現状の改革、刷新をためらわない性格は、親子3代に共通のものらしい。創業者で祖父の数雄さんは戦後、新宿西口で洋品店「イナバ」を開業。5店まで増やしたが、競合が増えるとスッパリ喫茶店にくら替えした。64年、現本店の場所に開業したのが純喫茶の「エデン」。その後、喫茶店とイタリア料理店を計8店展開した。

2代目の雄一さんは社長に就任した翌年の87年に高級路線への転換を決断。父親の出身地にちなんで店名を但馬屋珈琲店に変え、店構えも現在の形にリニューアルした。新宿に同業者が増え、差別化が必要と考えたからだ。150客以上のコーヒーカップをそろえ、全ての客に異なるカップを出すなど、自らの感性を生かしたアイデアを次々と店舗運営に取り入れた。「改革は経営がいい時にやらないとダメなんです」と雄一さんはきっぱり言う。
雄一さんも光敏さんも、いずれ新店を開いて成長を図りたいとの思いは一致する。では、どこが有望か。雄一さんは新宿駅東口を想定しているが、光敏さんには迷いがある。「地域集中の戦略がいいと思っていたけれど、コロナでそのリスクが露呈してしまった」からだ。

巨大な「夜の街」を抱える新宿は営業自粛の大波をくらい、ここに展開する全店が打撃を受けた。現在、客の戻りが最もいいのは吉祥寺の店だ。住宅街を含め、都心以外の立地でリスクヘッジする必要性をひしひしと感じている。
2人が口をそろえて課題に挙げるのはサービスのレベルアップ。アルバイトを含め60人以上の従業員の接客は「もっともっと水準を上げたい」(雄一さん)。光敏さんも従業員教育への投資を惜しまず「空間と味と接客」の三位一体での成長を追求する。「まだまだ、普通の企業にはなりきれていないので」
光敏さんの姉で経理などを担当する伊東直美さんによれば「父は直観的で、弟は論理的」。ちょうど補完しあう関係にある。この2人の進取の精神が衰えぬ限り、新宿を代表するレトロ喫茶が古びることはなさそうだ。
(名出晃)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。