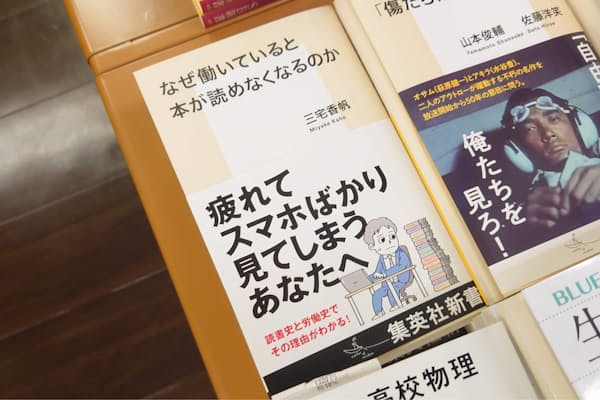総裁選で圧勝 菅首相のどんなイメージが後押し?

菅義偉首相は自民党の総裁選を圧勝で制した
菅政権の誕生は、イメージ戦略を考えるうえで、貴重な手がかりを提供してくれた。「人は見た目が大事」といわれる通り、言葉以外のイメージは印象を左右する。菅義偉首相が自民党の総裁に選ばれる過程でも、イメージ戦略は結果を大きく左右したとみえる。出馬表明の前はダークホース的な存在だった菅氏を総理・総裁の座に押し上げたのは、どんなイメージ効果だったのだろう。テレビから見えた「菅義偉」像を、残りの2候補と比べながら、考えてみたい。
人のイメージは長い時間をかけて浸透していくケースと、パッと見のいわゆる「第一印象」に分かれる。総裁選の3候補に関しては、長く政治の表舞台で活躍してきた人たちなので、長期的に形成されたイメージが強いと思われる。その点、安倍晋三政権で官房長官を務め続けた菅氏は圧倒的に有利だった。日々の記者会見は、国民への接触・露出頻度の面で頭抜けていた。
心理学の研究によって、人は単純に会った回数が多いほど、親しみを覚えやすくなることがわかっている。研究した心理学者の名前から「ザイアンスの法則」と呼ばれる。しょっちゅう顔を出す営業担当者が取引先とうちとけていくような事例でも知られる。3候補の顔は、安倍氏の退陣報道と直後から、これまで以上にメディアで見る機会が増えたが、過去の積み重ねは菅氏に有利だったはずだ。
見た目の印象は、「令和おじさん」というニックネームが示すように、ややソフトなタイプだろう。首相・内閣を支える官房長官という役割もあって、波風を立てない女房役に徹してきたことが菅氏のイメージをかたちづくっていった。実際には時にけんかを辞さない骨太の政治家でもあるが、一般的にはひょうひょうとしたイメージのほうが強いだろう。
それに対して、石破茂元幹事長にはこわもてのムードが漂う。眼光が鋭く、にらむような表情を見せることがあるのは、菅氏の穏やかな雰囲気とは対照的だ。総裁選の途中からは眼鏡をかけた姿を見る機会が増えた。いかつい印象をやわらげるうえで、眼鏡は効果的だ。前回の総裁選当時から石破氏が眼鏡を使いこなしていたら、いかついイメージはかなり変わったはずだ。イメージコンサルタントを抱えているのかどうかは知らないが、このあたりの戦略に工夫がみられなかったのは、今回の敗北につながった可能性がある。
一方、岸田文雄元外相は開成高校、早稲田大学を経て、日本長期信用銀行(現・新生銀行)に入ったという経歴がうかがえる、理知的で端正な見え具合。立ち居振る舞いに品があって、エリート感が漂う。とっつきにくい感じまではしないものの、いくらかクールな雰囲気を帯びている。石破氏のような押し出しの強さには見劣りするところがあり、「線が細い」とみる向きもありそうだ。実際、菅氏が担ぎ上げられる前の段階で、有力派閥をとりまとめそこなった立ち回りのまずさは「首相の器」を疑わせる結果になった。
安倍政権を受け継ぐ人物を選ぶにあたって、関係者の多くは、印象面での「安倍っぽさ」に近い人物像を求めたのではないだろうか。憲政史上最長の首相在任記録を打ち立てた安倍氏だが、豪快なキャラクターではなく、むしろ「おぼっちゃま感」のほうが強かった気がする。居酒屋の酔客には「アベちゃんはさぁ」と、「ちゃん」付けで呼ばれるような存在だったように思える。
あだ名が付くような気安さは、人気投票では重要な要因になりやすい。本来、一国の指導者を、人気投票気分で選ぶべきではないのかもしれないが、やたらと警戒心をあおるような人柄では、支持率も期待しにくい。何度かの危機を迎えながらも、安倍政権が選挙の強さと支持率の維持で乗り切ってきたことを思えば、「アベちゃん」テイストに近い人物像を、自民党関係者が望んだのは筋が通っていると思える。