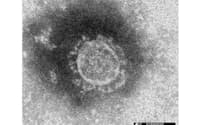育休復帰後の社会保険料どうなる? 時短勤務の影響は
人生100年時代のキャリアとワークスタイル

今年は新型コロナウイルスの影響により、特に緊急事態宣言期間中においては、在宅で仕事をしていた人は多かったのではないでしょうか。本来であれば、育児休業をしていた人も、新年度に合わせて4月中に復帰するのが通常ですが、自粛要請などで休業を延長し、6月から7月にかけて復帰する人は多数います。
フルタイムで復帰する人もいれば、時短勤務で復帰する人もいますが、働き方が変われば、それに応じて給与も変わります。では、社会保険料はどうなるのでしょうか? 実は時短勤務で給与が下がったからといって、社会保険料が休業前と比べてすぐ低くなるわけではありません。いったいなぜでしょうか。人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子氏が解説します。
社会保険料はどうやって決まる?
私たちの給与から毎月天引きされる社会保険料。社会保険とは狭義の意味で、健康保険と厚生年金保険を指し、40歳以上であれば介護保険も含まれます。社会保険料は、一定の報酬の幅にある給与を「標準報酬月額」に当てはめ、これに各保険料率を乗じて算出します。2020年7月1日現在、健康保険は1等級から50等級、厚生年金保険は1等級から31等級の区分に分かれています。
たとえば、給与の月額が25万円以上27万円未満であれば、標準報酬月額は26万円(健保20等級、厚生年金17等級)となります。健康保険料率は、協会けんぽ東京支部の場合9.87%なので、本人負担は事業主と折半されて1万2831円。厚生年金保険は、18.3%を事業主と折半で2万3790円になります。
この保険料を決めるタイミングは入社するときですが、その後は年に1回「定時決定」といって、4月から6月に支払われた給与の平均をもとに、9月分から毎年見直されます。さらに、昇給など固定的な賃金の変動で、標準報酬月額が大幅に変動する場合、変動した月の4カ月目から改定します。これを「随時改定」といいます。
では、育児休業期間中はどうなるのでしょうか?
育児休業期間中は、給与が支給されないケースがほとんどですが、その場合でも標準報酬月額は0円になるのではなく、休業前のものが維持されます。社会保険料が発生しないのは、申請によって免除されているからです。
そのため、育児休業から復帰したときの標準報酬月額は、休業前のものとなります。復帰後、給与が同額であれば気になりませんが、問題は時短勤務によって給与が低くなる場合です。給与に比べると、高い割合の社会保険料が天引きされてしまうので、手取りが少なくなってしまうのです。
育児休業終了時改定は本人の申し出が必要
社会保険料を引き下げるには、本来は随時改定が必要になります。ただし、次の3つの条件をすべて満たすことが必要になります。そのうえで、4カ月目から改定することができます。
【原則的な随時改定の条件】
(1)昇給または降給などにより固定的賃金に変動があった
(2)変動月から3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある
実は、ちょっと給与が下がったからといって、そう簡単に社会保険料を引き下げることはできないような仕組みになっています。
そこで、育児休業から復帰した人で3歳未満の子を養育している場合、上記の随時改定に該当していなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた平均給与に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができる特例的な制度(育児休業終了時改定)があります。
この場合、給与の支払基礎日数が17日未満の月は除きますが、通常の随時改定と違って、1カ月でも17日以上の月があればよく、対象となるケースが各段に増えます。さらに、標準報酬月額が1等級以上の差でも該当となるので、フルタイムの人でも残業手当がなくなってわずかに給与が下がった場合なども対象となります。
もう1つ、重要なポイントがあります。それは、この手続きに必要となる「育児休業等終了時報酬月額変更届」を事業主経由で健康保険組合などに提出するのは、被保険者本人からの申し出を受けた場合に限られることです。
通常の随時改定に該当する場合であれば、会社が自動的に手続きを行ってくれます。ところが、育休終了時の改定については、本人の申し出が原則。親切な会社であれば、「該当しますが、どうしますか?」など、確認をしてくれるかもしれません。ただ担当者が忙しかったり、多数の復職者がいたりすれば、そう丁寧に対応することも難しいので、自身で理解しておくことが大事になってきます。
制度の活用にはメリット・デメリットがあります。育休終了時改定をして標準報酬月額(等級)を引き下げる場合のメリットは、社会保険料も低くおさえられるので、手取りが増える、という点です。ただし、将来の年金額の算定額が下がることや、次のお子さんの妊娠を控えているような場合は、出産手当金の額も下がってしまう可能性があるため、慎重に検討したいところです。
養育期間の特例措置を活用する方法
年金額の低下の影響については、解決できる方法があります。それは、養育期間の特例措置で、子どもが3歳までの間に標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる制度です。対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで。
これも、ポイントは本人の申し出による点です。本人の申し出を受けて、添付書類として戸籍謄(抄)本や住民票などを添えて、事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。
また、この特例は、育児休業をしていた従業員には限られません。3歳未満のお子さんがいる夫婦において、それぞれ申し出ることも可能です。昨今は新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務をしている企業が多いですが、在宅になることで通勤手当の支給がなかったり、残業代の減少や休業などにより標準報酬月額が下がるケースは十分に考えられます。
添付書類を準備する手間などはあっても、それに見合うメリットはあると言えるでしょう。これこそ、知らないと損する仕組み、と言えるかもしれません。
コロナによる特例改定も新設
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった人に、一定の条件に該当する場合は社会保険の標準報酬月額を通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定が可能となる仕組みが新設されました。
上述した育児休業終了時の改定についても優遇はされていますが、あくまでも改定ができるのは4カ月目からとなります。新型コロナによる標準報酬月額の特例改定では、翌月に改定できる点が大きな特色といえます。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことで4月から7月までの間に、報酬が著しく低下(2等級以上)した月が生じた場合で、この特例措置による改定内容に本人が書面により同意していることが必要です。
本人の同意が必要な理由は、傷病手当金や出産手当金、および年金の額においても影響を受けることによります。その他にも、この特例改定には通常と異なる注意点がいろいろとあります。本人からの申し出が手続きの要件ではありませんが、新型コロナの影響による休業で給与が下がった場合は、会社に自分の場合は該当するかどうか、確認してみてもいいかもしれません。
社会保険は私たちの生活に密接にかかわるうえ、現在の給与や将来の年金額にも影響します。少し難しく感じられるかもしれませんが、知らないまま放っておいてしまうと、もったいないこともあります。特に、育児休業をする当事者は、制度のポイントを理解して、最大限に活用しましょう。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。