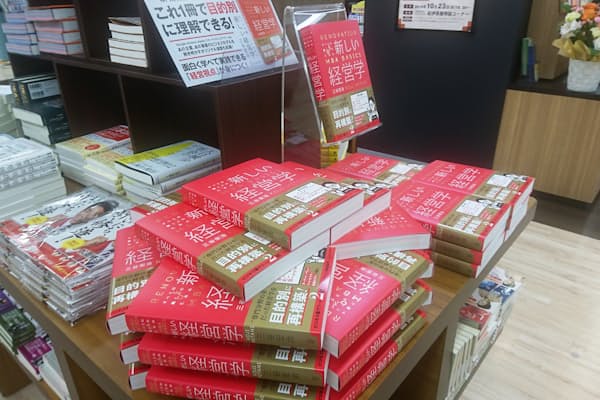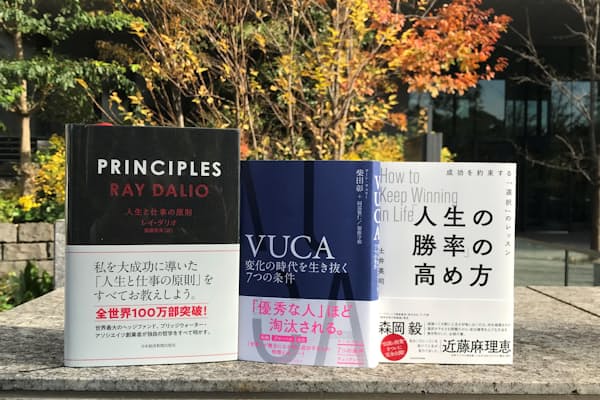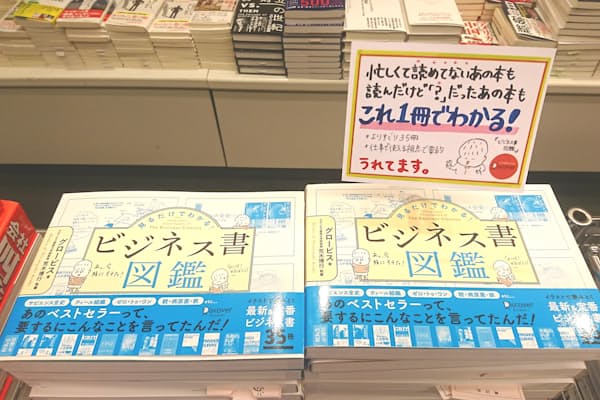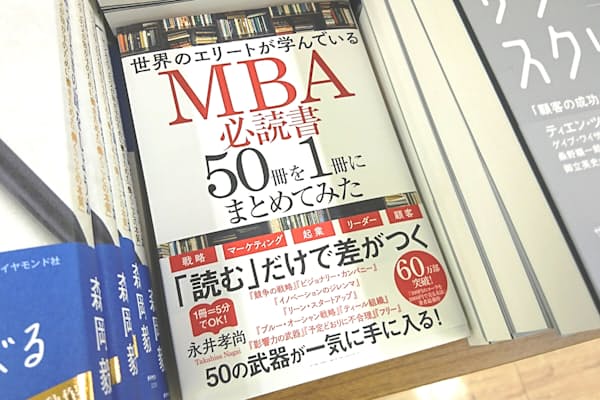「いつ何を読むか」が成長を決める 戦略読書のススメ
『戦略読書〔増補版〕』
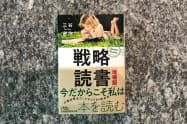
経営戦略の考え方を読書術に応用した
あなたは、自分が読む本をどのように選んでいるだろうか。成功するビジネスに優れた戦略があるのと同じように、読書をキャリア形成の糧にするなら読み方に「戦略」が必要だ。「なにを、いつ、どう読むか」を意識することで、読書体験は2倍も3倍も豊かになる。今回は一流の経営戦略コンサルタントがビジネスに効く読書術を解説した『戦略読書〔増補版〕』を紹介する。
◇ ◇ ◇

三谷宏治氏
著者の三谷宏治氏は1964年の大阪生まれで福井育ちです。子供の頃から無類の本好きでした。東京大学理学部物理学科を卒業した後、世界の一流コンサルティングファームで20年近く経営戦略コンサルタントとして働きます。その間1992年には欧州トップクラスの経営大学院、フランスのINSEADでMBA(経営学修士)を修了しました。2006年からは教育分野に活動の場を移し、KIT(金沢工業大学)虎ノ門大学院教授、早稲田大学ビジネススクールと女子栄養大学の客員教授を務めています。また、放課後NPOアフタースクール、認定NPO3keysの理事でもあります。
独自のキャリアを作る読書術
大学の専攻は理系でしたが、物理・科学系の本に加えて歴史、法哲学、SF、ノンフィクションなど幅広く読んできたという著者。「読書に戦略が必要だ」と気付いたのは、コンサルティングファームで働いていた社会人2年目のある体験がきっかけといいます。
そうなってしまった理由は簡単でした。その前の1年半、人と同じものを読み続けていたためでした。
社会人経験もなくMBAも持たない学卒若手コンサルタントが、その弱点を埋めるため、必死に本を読みました。
(序章 戦略読書のススメ――読書には戦略が必要なのだ 18~19ページ)
「人の体が食べるものからできているように、人(の精神)は読むものからできているのだと理解しました」と著者は振り返ります。独自のキャリアを作りたければ、人と同じものを読んでいてはだめなのです。