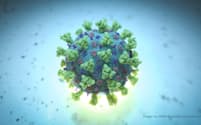パニックになる人ならない人 買い占めにみる生存本能

新型コロナウイルスが世界に広がり始めると、トイレットペーパー、消毒液、マスクを求め、各地で客が店に殺到した。感染者の数が増え、各国の政府や自治体は大規模な集会を自粛させ、店を閉めさせて、他人と一定の「社会的距離」を保つよう促している。それが人々の不安をあおっていわゆる「パニック買い」を助長し、店の棚はあっという間に空になってしまった。
昔から人間は、予測できない感染症が流行するたびに、日用品のパニック買いに走ってきた。1918年にスペインかぜが流行したとき、米メリーランド州ボルティモアの薬局に人々が押し寄せ、インフルエンザに効きそうなものを手当たり次第に奪っていった。同じような現象は、2003年のSARSまで、ことあるごとに繰り返されてきた。
「人が極端な行動に走るのは、自分の生存が脅かされていると感じるためです。何かをして、自分は大丈夫だと思えるようになりたいのです」と説明するのは、米ハーバードT.H.チャン公衆衛生大学院の精神科疫学教授カレスタン・ケーネン氏だ。
だが、そもそも何が人にパニックを起こさせるのだろうか。パンデミックのように、誰もが激しいストレスを感じているときに、どうすれば平常心を保てるだろうか。それは、脳の異なる領域が互いにどう作用するかによる。
不安が恐怖を駆り立てる
人間の生存は、恐怖と不安の両方に依存している。そのように進化したおかげで、危機(すぐそこの角を曲がった先にライオンがいる)に遭遇したとき直ちに反応するし、将来予測される脅威(ライオンは今夜どこにいるのだろうか)についてもじっくり考えられる。
ところが、頭のなかでそのバランスが決壊すると、人はパニックを起こす。
人が危険を感じたとき、感情の中枢である扁桃(へんとう)体は、すぐに逃げろと要求する。その際、ライオンをどうやって回避するかという細かいことは考えない。一方、行動をつかさどる前頭葉は、まずライオンの状況をよく考えろと訴える。次にいつライオンと出くわすだろうか。そうなったらどうすべきか。
だが、たまに不安がこうしたメカニズムを乱すことがある。すると、どのようにして自分はライオンの餌食になるのか、考え得る限りのシナリオを脳のあらゆる領域が好き勝手に主張し始めて、計画や決定が得意な前頭葉と対話しなくなり、前頭葉が混乱に陥る。
そして、脳の回路がショートするとパニックが起こる。明日の夜ライオンがどこにいるかを前頭葉がじっくり考えようとしているのに、扁桃体がフル回転している状態だ。
「より理性的な前頭葉が感情に圧倒されてしまうと、パニックが起こります」と、ケーネン氏は言う。恐怖の感情が強くなりすぎて、扁桃体が脳の支配権を握り、アドレナリンが多量に分泌される。
もちろん、パニックが命を救うこともある。今すぐライオンに襲われそうになったり、自動車にはねられそうになったとき、最も理性的な反応は、逃げるか、闘うか、または硬直して動けなくなるかのいずれかだろう。頭のなかで議論している暇はない。
しかし、扁桃体のいうことばかりを聞いていては、深刻な結果を招くこともある。
災害社会学者のエンリコ・クアランテリはかつて、災害時に人間がどのように行動するかについて画期的な研究を行った。その1954年の論文「The Nature and Conditions of Panic(パニックの特性と状態)」に、ある女性の例が紹介されている。
爆発音がしたので、女性は自宅が爆撃を受けたのだと思い、慌てて外へ飛び出してみたが、爆発が起きていたのは通りの向こうだった。それを知った後で初めて、女性は自分の赤ちゃんを家の中に残していたことに気付いたという。
「反社会的であることよりも、パニックのほうが非社会的な行動である」と、クアランテリは書いた。「この社会通念の崩壊が、最も強力なはずの絆を粉々に砕いてしまうことがある」
長期的な脅威に対しても、パニックは何の役にも立たない。そういうときこそ前頭葉が主導権を握り、潜在的な脅威を警戒しつつも、時間をかけてリスク評価を行い、行動計画を立てることが望ましい。
不確実性がパニックを助長する
では、パンデミックが起こるとなぜ一部の人々はトイレットペーパーや消毒液を買い占め、他の人々は感染リスクがあるのを承知でバーに押し寄せるのだろうか。
人は、不確実な事態に直面した際のリスク評価があまりに下手なのだ。下手といっても誰もが同じように下手なのではない。リスクを過大評価してしまう人もいれば、反対に過小評価してしまう人もいる。
米カリフォルニア大学バークレー校の心理学准教授ソニア・ビショップ氏は、不安が判断力に与える影響を研究している。そのビショップ氏は、コロナウイルスがパンデミックになった今が、まさにそんな状況だと指摘する。政府やメディア、公衆衛生当局から発せられる一貫しないメッセージが、人々の不安をあおっている。
「今後の見通しが目まぐるしく変化する今のような状況に、私たちは慣れていません」
ビショップ氏は、不確実な事態に直面したときには、モデルフリー学習と呼ばれるアプローチでリスク評価をするのが理想的だという。

パニックと心理的バイアス
これは、どんな行動が利益につながるのかがわからない環境を前提としている。基本的には試行錯誤で、何かが起こる可能性はどれくらいか、もし起こったら事態はどれだけ悪くなるのか、それを防ぐためにどれだけの努力をすべきかといった予測を、自らの経験に即して少しずつ修正していくやり方だ。
だが、脅威に対処するモデルがない場合でも、多くの人はモデルベース学習に頼る。そして、モデルになりそうな過去の事例を適用し、将来の可能性をシミュレーションしようとする。
すると、過去の事例を使う際に「利用可能性バイアス(利用可能性ヒューリスティック)」が忍び込む。利用可能性バイアスとは、何度も聞いたり読んだりすることは思い出しやすく、そのためにそれが起こりやすいと思い込んでしまう錯覚だ。
例えば、ニュースで盛んに飛行機事故が報道されると、自分の乗る飛行機が墜落する状況を想像して、飛行機に乗ることのリスクを過大評価してしまう。「そのシナリオを頭のなかで簡単にシミュレーションできてしまうことが、判断力を鈍らせます」
楽観主義または悲観主義へ偏ってしまう人にも、同じことが言える。悲観主義者は、起こりうるあらゆる破滅的シナリオを思い描くのを止められず、パニック買いをする。逆に楽観主義者は何も悪いことなど起こるはずがないと考えがちだ。そういう人は、コロナウイルスで重症化しやすい要因があるにも関わらず、自分は健康だから平気と思い込んでバーに足を運ぶ。「そうすることで、自分は大丈夫だと感じられるのです」と、ビショップ氏は説明する。
パニックにもメリットはあるのか?
両極端な例は別にしても、この時期に急激な不安を抱いている人は多いだろう。
災難に直面したとき、ある程度の不安を感じるのは良いことだ。不安が動機付けとなって、警戒心とエネルギーのレベルが高まる。手をよく洗い、ニュースに注意を払うようになる。もちろん、食料品を備蓄することも良い。
米デラウェア大学疫学科の創設者で、公衆衛生対策の専門家でもあるジェニファー・ホー二ー氏は、少しばかりのパニックが役に立つこともあると指摘する。特に、米国人は他の国と違って、人との接触制限や隔離措置といった公衆衛生上の指示に従うのが昔から苦手だ。
「そういう意味では、少しはパニックを起こしたほうが、自分の行動が実際に他の人に大きな影響を与えることを理解できて、生産的だと思います」
一方、長期にわたって続く不安は耐えがたい。ひとつには、不安になればなるほど、脳がパニックモードになっていくのを抑えられなくなる。恒常的なストレスは、理性的に物事を考える脳の部分を萎縮させ、さらにパニックを悪化させるとの研究結果がある。
私たちの身体は、急性のストレスや不安に、何週間も何カ月も耐えられるようにはできていないとビショップ氏は指摘する。短期的にはエネルギーがぐんと増えたとしても、次第に疲弊して気分が落ち込むようになる。これが、最終的に何を意味するのだろうか。自宅に引きこもってストレスの限界に達した人々が、パンデミックがピークを迎える前に外に出るようになれば、どんな事態を招くだろうか。
2009年に起こったH1N1型インフルエンザのパンデミックで緊急対応チームの訓練に当たったホー二ー氏は、不確実性を減らすことがパンデミック対策の効果を上げるために重要だと話す。
新型コロナウイルスは、全く未知のウイルスというわけではない。SARSとMERSの経験から、コロナウイルスについてはかなり多くのことがわかっている。
「現在行っていることの多くは、感染拡大を抑えるために取られる典型的な公衆衛生対策です。ただ、今回は、これまでよりもはるかに大きな規模で起こっているだけのことです。クルーズ船の隔離は、ノロウイルスや季節性インフルエンザなど感染症が流行したときにはいつも取られている措置です」
(文 AMY MCKEEVER、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック 2020年3月20日付の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。