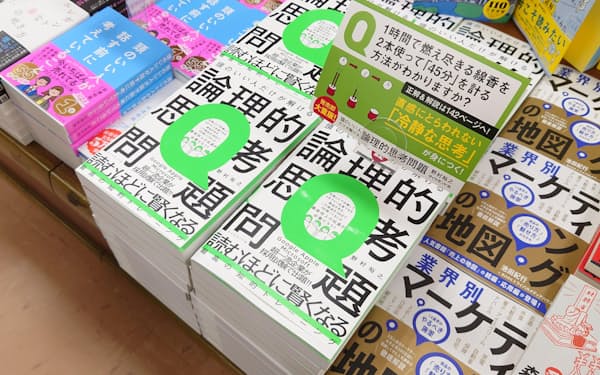男性限定の生け花の世界 教室や花展、華道家も脚光

生け花を楽しむ男性が増えている。メディアで男性華道家の活躍が目立ち、対象者を男性に限定した教室や、男性のみの花展が開かれるなど環境も整ってきた。「女性の趣味」というかつての概念を取り払ってみると、生け花の新たな魅力が見えてくる。
リタイア後の居場所の一つ
東京都内の72歳の男性が生け花に出会ったのは61歳のとき。きっかけは知人に誘われた花展だった。リタイアを前に「なにか学びたい」と模索していた時期に「素朴な花に魅せられ、習いたいと思った」と振り返る。
知人に紹介された都内の教室に今も通う。生け花から植物や万葉集、植物画に興味が広がり、趣味も増えた。男性は「生け花は潤いや癒やしをもたらしてくれる。リタイア後の居場所の一つにもなった」と笑顔を見せる。奈良県での研修会や年に1度の花展に参加するが、周りで多いのは圧倒的に女性だ。
今も続く女性が多数派の状況に一石を投じたのは、革新性が特徴のいけばな草月流だ。東京・赤坂の草月会館で男性だけの教室「男子専科」を1982年から開いてきた。男性が集中して植物と向き合える環境を提供するのが目的だ。
教室は金曜夜の午後6時から8時半までで、時間内なら出入り自由。入り口で、花材と花器を選び、テキストなどを参考に、自分の腕のレベルに合わせて花を生ける。完成すると、ひとりずつ講師からの講評を受けられる。レッスンは月3回で、1回の受講料は4500円(花材費別)だ。
現在の在籍者は約50人で、年齢は20~70代と幅広い。草月会広報部の畑花菜さんは「男性は、自分の世界を作ろうと、一人で黙々と集中する人が多い」と話す。
受講生に聞くと、きっかけも楽しみ方もそれぞれだった。昨夏から通う40代の会社員は転職を機に思い切って始めたという。「生けているときは花だけに集中できる。どの葉や枝をそぐかという決断力が必要。これはビジネスにも通じる」と指摘する。
男子専科歴8年の60代男性は「単身赴任先で週末の趣味として始めた。花材は、自分が思う形とは限らず、見えないところに工夫を凝らして、完成させる面白さがある」と魅力を話す。
男子専科担当講師の西山光沙さんは「生け花は、ダンスや絵画と同じ自己表現で、作者の性別は問わない。真剣に向き合わないと表現はできないのでその分、他のことを忘れて集中できる。植物の手ごわさに翻弄される楽しさもある」と解説した。
男性華道家もPRに一役
性別にとらわれず、生け花に親しんでもらおうと、男性華道家もPRに一役買う。池坊(京都市)は、全国の20~40代の男性華道家7人によるグループIKENOBOYSを2016年に結成。生け花によるパフォーマンスやワークショップなどを通して魅力をアピールする。

メンバーの本職は、大工、花店経営、学芸員など様々。最年少で25歳の真壁弘典さんは病院勤務の薬剤師だ。祖母の手ほどきで3歳頃に華道を始めた。中高校生時代は遠のいていたが、大学進学が決まったのを機に本格的に再開した。「古典立花の本を見てかっこいいな、と思ったのがきっかけ」と話す。
少しでも親しみやすさを感じてもらいたいと、ワークショップには、ジーンズにスニーカーといったカジュアルな服装で出演する。「和服の女性が畳の上で」というステレオタイプなイメージを壊したいという狙いもある。
真壁さんは「生け花の伝統的な型は、先人たちが500年以上の歴史の中で失敗を繰り返しながら作り上げてきた黄金比。サッカーのフォーメーションにも通じる合理性を感じる」と考えている。「生け花は歴史的にみれば男性のたしなみでもあった。作品づくりにドリルやクギを使う場面や硬い枝を扱うこともあるので男性に有利な点も多い」と続けた。
池坊は14年に、男性のみの花展「男花展」を京都で初開催。16年からは毎年、京都と東京で開いている。昨夏にはラグビーワールドカップ日本大会にちなみ、ラグビーがテーマの作品も展示された。
伝統に裏打ちされた奥深さと、自己表現としての楽しさ。「取っつきにくい」という既存のイメージを取り払うと、性別を問わず味わえる魅力が見えてくる。
(ライター 李 香)
[日本経済新聞夕刊2020年2月22日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。