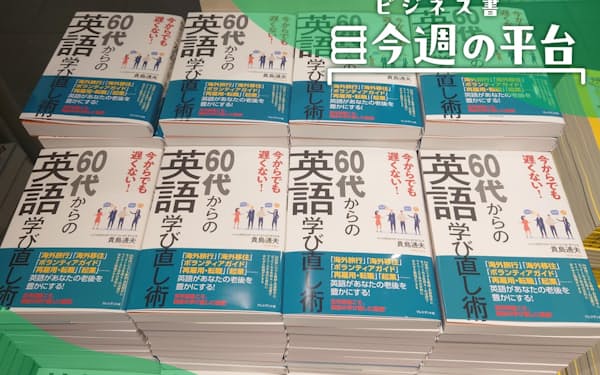増える早期・希望退職 ミドルは活路をどうつかむ
人生100年時代のキャリアとワークスタイル

東京商工リサーチは6日、2019年1~11月の上場企業の早期・希望退職者の募集が、6年ぶりに年間1万人を突破したという調査結果を発表しました。11月以降、味の素やLIXILグループ、ファミリーマートなど大手企業が相次いで退職の募集を発表していますが、20年以降も足元の業績が好調な企業を中心にすでに7社、計1500人の実施が判明しています。人手不足と言われる中で、こうした動きが再び広まっている背景には何があるのでしょうか。人事労務コンサルタントで社会保険労務士の佐佐木由美子氏が解説します。
ミドル・シニア社員へ重荷を感じる企業も
今では信じられない気もしますが、1980年代は定年が55歳。それが94年の法改正により60歳となり(施行は98年)、現在では希望者は65歳まで働き続けられることが可能になりました。さらに、政府は全世代型社会保障検討会議の中間報告案で70歳までの就業機会確保を打ち出しています。
従来、日本の大手企業では、終身雇用を前提に、職務や勤務地を限定しない新卒を大量に一括採用。社内で職場内訓練(OJT)・研修などの教育や人材育成を行い、企業の都合で自由に配置転換を行ってきました。社内で必要な人材を調達するシステムは、定年が今よりずっと早く退出もスムーズであったこともあり、かつてうまく回っていたといえます。
しかし、目まぐるしく社会構造が変化し、次々と新しい産業やビジネスが生まれる中で、従来のやり方では通用しないことは明らかになっています。これまでのように社内の人材を教育して、再配置を行うには到底追いつかないようなスピード感で、グローバルに経済活動が進んでいます。それがミドル・シニアとなると、デジタルネーティブとは異なり、なおさら新たな技術の習得に時間がかかり、適材適所がうまく機能しなくなったことは否定できません。
一方、今までは社内で通用するスキルを高め人材育成を行い、配置転換を企業側の意向で行ってきたところに、突然キャリア自律を求められても、従業員からすれば戸惑いを感じるかもしれません。
こうした中で、年功序列型の賃金体系が残る大手企業においては、即戦力として配置転換を行うことが難しいミドル、特にシニアは人件費からみても相当な重荷を感じていることは否めない事実といえるでしょう。しかも、事実上65歳までの継続雇用を踏まえると、その負担感はいっそう強まっています。
冒頭の調査では、19年で早期・希望退職者の募集人数は、業種別でみると業績不振が目立つ電気機器が12社とトップ。合計24社(構成比66.6%)が業績不振によるものでした。一方で、業績不振以外の理由による早期・希望退職も見られます。
多様なテーマの早期退職が広まる傾向に
20年以降、早期・希望退職の募集を予定している大手企業が明らかになっていますが、その理由は従来に見られる業績悪化によるものばかりではありません。むしろ、食料品や消費財、小売業など、比較的業績が堅調な大手企業が占めています。それは、国内市場の成熟化に伴う先行きを懸念し、経営体力のあるうちに既存の事業の見直しに加え、データ解析やマーケティングなど不足する人材を、外部の即戦力から獲得したい意向によるもので、いわゆる先行型の実施です。企業側もただ人員を削減したいのではなく、経営ニーズに合った即戦力は、喉から手が出るほど欲しいといえるでしょう。
また、「セカンドキャリアの形成」「社外組織での活躍」をテーマに掲げた募集も多くみられます。みずほ証券では、50歳以上63歳以下の社員について希望退職者を20年1月から3月にかけて募集するとの報道がありました。希望した人のみが対象で、応募後半年以内に次のキャリアが決まらなかった場合、応募の撤回も可能という今までには見られないような内容です。ベテランの社員に対して社内外を含めた柔軟かつ多様な選択肢を提供するもので、従来に見られる人員削減が目的ではなく、早期退職をキャリア形成のための手段と位置付けています。
人生100年時代、セカンドキャリアを考えるなら、ミドルのうちから副業・兼業も含めて選択肢を広げたいという考え方も広まる中、雇用の流動化も進み、多様なテーマを掲げて早期・希望退職者の募集が今後さらに広がっていくと考えられます。
定年を迎える女性たちが今後増加
第一生命研究所の定年に関するアンケート調査(16年)によると、男性は約半数が定年退職を経験しているのに対し、女性は定年退職を経験せず働き続けている人が多いといいます。これは、結婚・出産により就業を中断し、定年制度のない小規模企業に転職した女性が多いことのほか、同じ会社で働き続けている場合でも定年で退職せずにパートなどに雇用変更するなどして勤務延長する女性が多いことが要因にあると考えられます。
しかし、共働き世帯が増加し、法整備などよって、出産後も育児をしながら就労継続が可能な環境が広がりました。生産年齢人口が減少していく中、国も「働き方改革」によって、さらに女性の就労や活躍を後押ししています。
今後、地道にキャリアを継続してきた女性たちが多数、定年を迎えることになるでしょう。かつて、早期退職といえば、定年が前提であった男性正社員を想定したものでしたが、今や女性にとってもミドル以降の課題といえます。
まして、女性の方が男性よりも寿命が長いわけですから、60歳以降の働き方については、より切実になるのではないでしょうか。そう考えると、40代半ば~50代前半あたりの時期で、早期退職の話があれば一つのきっかけとなります。早期退職の話が特になくとも、これからのキャリア形成について、自分自身と向き合ってみるのは良い機会といえます。副業・兼業から何か始めてみるか、思いきって転職して別の活路を見いだすか、このまま企業で専門性を深めていくか、定年まで勤め上げる以外の選択肢も多様化しています。
自分の会社がどのようなタイミングで早期・希望退職制度を実施するか、あるいはいつ自分が早期退職の対象となるか、先は読めません。だからこそ、定期的に自分の職務経歴を振り返ってみたり、社外の人脈を構築して視野を広げてみたり、フレキシブルな対応能力に日ごろから磨きをかけておくことが大切になっていくといえるでしょう。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。