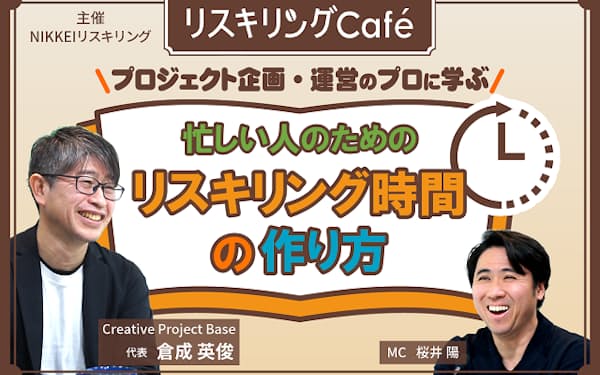鉄腕アトムできるかな ビリギャルが聞くAI未来予想
人工知能(AI) (後編)

AI(人工知能)は犯罪捜査や国民の監視、信用度のランク付けにまで使われていると聞き、正直少し怖いと思ってしまった。だけれど、公立はこだて未来大学の松原仁教授は「人間はAIとうまく付き合っていくと思う」と楽観的だった。松原先生は世間がAIに目もくれなかった時代からAIを信じて研究に打ち込んでいたんだって。そんな松原先生にAIの未来予想図を聞いてみた。
――AIの研究者の発言を聞いていると、未来をポジティブにとらえている人とネガティブな人に二極化していると思うんです。
「いわゆるシンギュラリティの議論がまさにそうですね。シンギュラリティというのは人間の脳の能力をコンピューターの能力が追い越して、人間に教わらなくてもコンピューターが勝手に自分で学習を始めて人間より賢くなってしまう時点のことです。レイ・カーツワイルっていう人がだいぶ前に言い出したことなんですが、当時はだれも見向きもしなかった」
――でも、現実味を帯びてきちゃった。
「今のAIブームで、もしかしたらシンギュラリティは本当にくるんじゃないかって大騒ぎしているわけですが、そういうときが来るという人と来ないという人がいます。そもそも、知識量ではAIのほうがずっと上なのだけれど、僕はシンギュラリティは来ないと考えているんです。そもそも機械と有機物である人間の脳を比較すること自体がナンセンスだともいえますよね」
――重要なのは、どっちが有能かではなくて、どっちが主導権をちゃんと握っているかということなのかなって思います。AIをどう使うかということが大事なのでは?
「そうなんです。僕がいつも考えているのは、AIと人って敵じゃないよねってこと。僕はそもそもAIは仲間だと思っているんですね」
――先生のなかでは、AIは鉄腕アトムなんですよね。みんななぜか少し人間の存在を脅かすものだと思っているところがあるけれど、鉄腕アトムだと思うとすごくわかりやすい。松原先生からみて、AIがいる未来はどんな生活になると思いますか。
「僕の理想の未来なんですけど、一人に一台、執事ロボットがいて全部やってくれるようになるんじゃないかと思っています」
――執事! それは超便利。
「赤ちゃんが生まれたときに、その赤ちゃん用にロボットを買うか、国が給付する。小さい頃は親に代わって子育てを手伝い、子どもが少し大きくなったらボディーガードや看護師、家庭教師になる。遊び相手もしてくれるし、仲の良い兄弟みたいな存在でもある。大人になってからもロボットが家事をしてくれるし、年を取ったら介護までしてくれる。ゆりかごから墓場までというロボットができるのが、僕の描くイメージです」
――それはすごくいい少子高齢化対策にもなりそう! 私、赤ちゃんが犬と大きくなって本当の兄弟みたいに仲良くしてる動画とか見るの好きなんですけど、それを今思い出しました。さらに、言語コミュニケーションやより正確な記録や様々な機能がついている感じですね。
「友達なんだけど助言もしてくれる。もちろん、一生のことをすべて、いつも横にいて音声も画像も全部記録しているから、『10歳のあのとき、どうしたんだっけ?』などと聞けば、すぐに上映してくれる。これこそ、僕が小さい頃に読んでいた鉄腕アトムです」
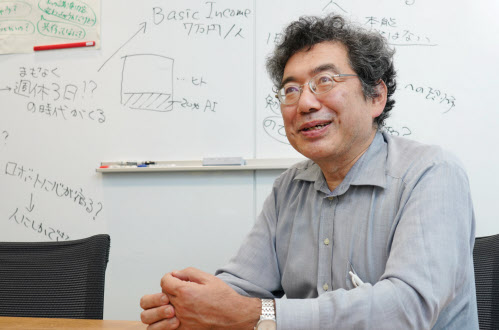
――それって……、いつごろ実現するんでしょうか。私それ、自分が生きている間に体験できるのだろうか。
「こういうロボットが急に登場するというより、ちょっとずつ段階的に生活に入ってくるだろうと思います。ただ、人間型にするのは難しいんです。戸を開けたり椅子に座ったりできるロボットを作るのは本当に難しい。だから、まずはAIスピーカーや掃除ロボットが人間のように動き始めるというイメージですかね」
――私がおばあちゃんになるころ、どうなっているんだろう。ちょっと怖い気持ちもまだあるけど、先生と話してたら楽しみになってきた!
「正直いってわからない。何が来るんだろう? もう地球に人類が住んでいるかどうかすら、わからないです。人間の代わりにロボットが宇宙を探索して、人間が住める場所を見つけて連れて行ってくれるかもしれない。50~60年でけっこう変わると思いますよ。僕は今、60歳なんだけど、2050年までなんとか生きて、どこまで進むか見届けたいなと思っています」
――そんな時代になったら、仕事は残ってるかな?
「仕事に対する考え方も変わるかもしれないですよ。そもそも仕事したいですか、という問いが出てくる。仕事は生きがいでもあるが、多くの人は食べるために働くわけです。でも、仕事しなくても食べていけるなら、働かなくてもいいかなという話になるかもしれない」
「たぶん遠くない将来、手始めとして週休3日の時代が来ると思います。僕は水曜日がいいなって思ってる。2日働くと水曜日がおやすみで、あと2日働くと週末です。金曜日案をとなえている人もいます。3連休だと旅行にいけるよねって」
――私は金曜日派だな! 連休大好き!
「何曜日に休むかはともかく、仕事の一部をAIがやってくれるようになったら、週休3日も現実的なんです。今やっている仕事のうち2割をAIに任せれば週に1日休める。その時間を副業とか、趣味、ボランティアに使えますよね」
「仕事を無理にしなくてもいいんじゃないかという時代は、大げさだけど人類にとって画期的なことだと思うんです。これまでの長い歴史で人類はずっと食べるのに困っていたから、ずっと働いていた。江戸時代の日本人は土曜も日曜も関係なく、ほとんどの人が農作業をしていたけど、それでも餓死者が出ていた。今は生産性が上がって週休2日になりました。このままAIがいろんな仕事をになう時代が来ると。もしかしたらほとんど仕事をしなくても食べていける時代が来る。そのとき、我々は何をするのか」
――確かに「昔は良かった」なんていう人がいるけど、明らかに私たちは文明の発展によって幸せになってきている。そしていよいよ働かなくて良くなる時代が来たら、私たちは何するんだろう。私ずっとNetflix見ていそう。

「ずっと絵を描くとか本を読むとか好きなことができる。人間が人間らしい生活をできるような世の中にするため、AIが貢献してくれるという考え方もできるんです。僕くらいの世代は子どもの頃から、男は仕事をするんだと言われて育ったんだけど、それも一種の偏見。仕事をしなくても食べていけるようになったら、違う価値観が育って、もしかしたら人類はさらに発展するかもしれないです」
――無理に働かなくてもよくなったら、なんのために勉強するのでしょう?
「今は大人になって食べていく力をつけるために教育があるといわれているけれど、働かなくても食べていける時代になったら、勉強して自分を高めるモチベーションを人類が持ち続けられるかわからないです。僕はそれでも人間は自分を高めると信じたいんだけど、絶対に怠惰な方向に流れると主張する人もいる」
――ドラえもんでいったら、暗記パンだっていらないもんね。そしたら、みんながのび太になっちゃう。
「怠惰なのび太になることを心配する人もいる」
――でも、とても平和そうですね。
「そう、怠惰かもしれないけど誰も争わない。戦争がなくなるかもしれない。AIが支配する未来は暗黒だという考え方がある一方で、AIに支えられて戦争しなくなるなら、それは天国だという考え方もあるわけです」
――私は講演などで「ロボットにはできなくて、人間にしかできない能力を今のうちに伸ばそう」って話すんです。具体的には思いやりとかおもてなし、ワクワクすることみたいなことなんだけど、もしもロボットにも心が宿ったら、人間にしかできないものって何が残りますか?
「それは正直言って僕もわかりません。鉄腕アトムは『美しい』がわからないとイジイジする場面があるんですよ。それでお茶の水博士にそういう感覚を入れてほしいと頼むんです。でもね、感情回路を入れるとアトムは弱くなっちゃう。こいつは悪いからパンチを打とうと思うんだけど、痛いかなとかこいつにも家族がいるんだよなとか考えるようになってしまう。それで、弱くなっちゃうから感情回路を外すというシーンがあるんです」
――なにそれ切ない。鉄腕アトムってそんなに深いお話だったんですね。
「AIには本能がないんですよ。生存本能もない。死の概念もない。死の概念がないと本当の喜びはないと主張する哲学者もいて、AIはこの点で人間と根本的な違いがあるわけです。それが、人間の行動とAIの行動にどんな違いをうむのか。正直、今のAI研究ではまだわかりません。AIって突き詰めると哲学になるんです。人とは何かという問いが常にある」
――深いなあ。これから学生たちへの講演で今日聞いたお話をすることにします。先生、これだけは伝えたいってこと、ありますか。
「AIは友達だって、伝えてください」
1959年東京生まれ。1981年東大理学部情報科学科卒業。1986年同大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了。工学博士。同年通産省工技院電子技術総合研究所(現産業 技術総合研究所)を経て2000年公立はこだて未来大学教授。2016年公立はこだて未来大学副理事長。人工知能、ゲーム情報学、観光情報学などに興味を持つ。 著書に「コンピュータ将棋の進歩」「鉄腕アトムは実現できるか」「先を読む頭脳」「観光情報学入門」「AIに心は宿るのか」など。 元人工知能学会会長、元情報処理学会理事、観光情報学会理事。未来の公共交通をITで創造することを目指す、未来シェア(函館市)の社長も務める。
1988年生まれ。「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話」(坪田信貴著、KADOKAWA)の主人公であるビリギャル本人。中学時代は素行不良で何度も停学になり学校の校長に「人間のクズ」と呼ばれ、高2の夏には小学4年レベルの学力だった。塾講師・坪田信貴氏と出会って1年半で偏差値を40上げ、慶応義塾大学に現役で合格。現在は講演、学生や親向けのイベントやセミナーの企画運営などで活動中。2019年3月に初の著書「キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語」(マガジンハウス)を出版。4月からは聖心女子大学大学院で教育学を研究している。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。