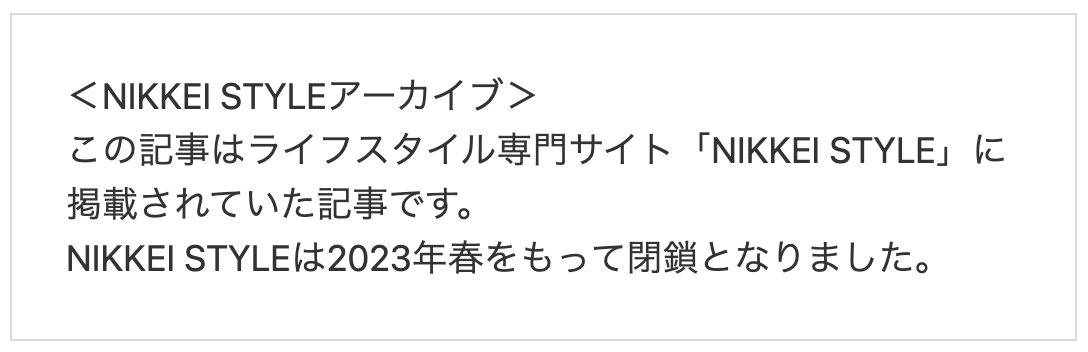実験漬けの研究員生活支えたNYサンド 福岡伸一さん
食の履歴書

福岡ハカセこと生物学者、福岡伸一さん(60)の原点は米ニューヨークにある。20代の後半、現地の大学で研究員として実験に没頭した。数少ない楽しみが、肉の薫製と発酵したキャベツを挟んだルーベンサンドイッチ。複雑な味は、そこで学んだ自然の深遠さと重なる。
ルーベンサンドは「複雑系」
それはアパートと研究室を往復する日々に、深夜営業している庶民のレストラン、ダイナーで見つけた。
ライ麦パンに、温かいパストラミとザワークラウト、スイスチーズがたっぷり挟んである。パストラミとは、塩漬けの牛肉の薫製で、コショウやニンニクなどの香辛料がきいている。ローストビーフより、もっと複雑でジューシー。そこに、キャベツを発酵させたザワークラウトがさわやかな酸味を加える。
食事といえば甘いドーナツに薄いコーヒー、油でべとべとのピザとコーラが定番。安いし腹持ちはいいが、さすがに飽き飽きしていた。
「いろいろ大ざっぱなことが多いアメリカのなかで、重厚な味でなかなかおいしい」。たちまち、とりこになった。「ビッグサイズなので、昼に半分食べて、持ち帰ってまた夕方に食べたり。ビールのあてにも最高なんです」
ぼろぞうきんのように働く
京都大の大学院を修了した後、スーツケース一つで意気揚々とニューヨークのロックフェラー大学に赴いた。電子メールもない時代、「数打ちゃ当たる」方式で多くの大学に手紙を書いたところ、採用の返事が来た。

ところが行ってみたそこは、「まさにブラック企業。朝から夜中まで研究室にこもる『実験の奴隷』でした」。ひとつの結果を得るために、とるべきステップは膨大で、やるべきことは無限にあった。ぼろぞうきんのようになって働いたという。
しかも、初めての異国。言葉の壁も立ちはだかり、ライバルにおくれをとる焦りも募る。なんとかして成果を出さなければならないというプレッシャーに押しつぶされそうだった。
息抜きしようにも当時の年収は2万ドルで、ぼろアパートの家賃を払えばすっからかん。時間にも気持ちにも余裕がなく、マンハッタンに住んでいるにもかかわらず、「自由の女神にもエンパイアステートビルにも行ったことがなかった」。そんななか、数少ない楽しみがルーベンサンドイッチだった。
だが今にして思えば、貴重な時間だったという。「実験し続けることで、自然がいかに一筋縄に本当の姿を見せてくれないかを学んだ。自然に対して謙虚でいなければ……」。研究者の原点は、ルーベンサンドの複雑な味わいとともに心に刻まれた。
ニューヨークには、安くておいしいとされる食べ物がほかにもあるはず。なぜルーベンサンドだったのか。
「そもそも味覚って記憶の積み重ねなんですよ。子どものころに食べておいしかったものが、一生おいしい。割と単純」
私たち人間は、子どものとき食べておいしかったものの記憶を常に追い求めているという。「(ルーベンサンドの)あったかいお肉と野菜、重厚な味わいに、なんらかの懐かしさを感じたのかもしれません」と振り返る。
おせち料理のようだったお弁当
衣食住にこだわった母親は栄養のバランスや品数を考え、1日に30種類ほどの食材を使った。小学生時代のお弁当にも、丹精込めたいろいろな料理が少しずつ入っていた。「今にして思えばすばらしいんですが、おせち料理みたいだなと学校で笑われたのはトラウマです」
周囲はハンバーグがばーんと載っていたり、コッペパンに缶詰だったりで、そんなワイルドなお弁当に憧れた。教室でお弁当の蓋を開けるのが苦痛だったという。
友達は少なかったが、昆虫がその代わりになった。虫取りが大好きで、両親が顕微鏡を買ってくれたことで、さらにのめり込んだ。「まだオタクなんて言葉なかったですけど、友達なんかいらなくて、虫オタク、顕微鏡オタクですね」。それは生物学者としての出発点でもある。
生命や人間を知りつくした今、食べるときに知識は邪魔しないのだろうか。
「全然大丈夫。なぜなら、一杯飲めばすべて忘れるから」。研究のかたわら、エッセーなどの文筆にも忙しい。「割と飲み助なんで、飲むなら書くな、書くなら飲むな。それで、書き上げたら飲む」。好きなのは、ビールとギョーザ、日本酒と板わさ、ワインとイタリアン。ハカセはけっこう飲む。

帰国後はうなぎ屋さん巡り
米国の大学で研究員をしていた時代、日本のものが恋しくなるなかで「夢にまで出てきた」のがうなぎだ。日本に帰国してから、「うなぎ屋さん巡礼」が始まった。
東京・渋谷にある「神泉いちのや」(電話03・5459・6862)は教授を務める青山学院大から近く、普段「食べたい」と思ったら訪れる店だ。
うな重(4800円)のうなぎは鹿児島産でふわふわ。串を打った後、一般的には素焼きしてから蒸すことが多いが、「素焼きせずそのまま蒸すことで柔らかさを出している」と同店の七代目付親方の天田貴規さん。代々受け継がれているたれで香ばしく焼き上げる。
福岡さんによれば、「『重箱の隅をつつく』という言い方があるけれど、うな重だけは真ん中から食べる」そう。
最後の晩餐
レオナルド・ダ・ヴィンチが好きで、彼の足跡をたどってイタリアを旅したときに、ベネチアで食べたイカスミのパスタをもう一度食べたいです。白ワインと一緒にね。それはそうと、あの有名な「最後の晩餐」のテーブルにもうなぎが載っているんですよ。
(井土聡子)
[NIKKEIプラス1 2019年9月28日付を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。