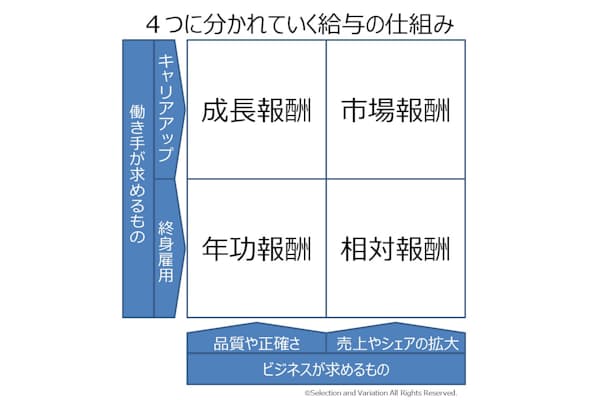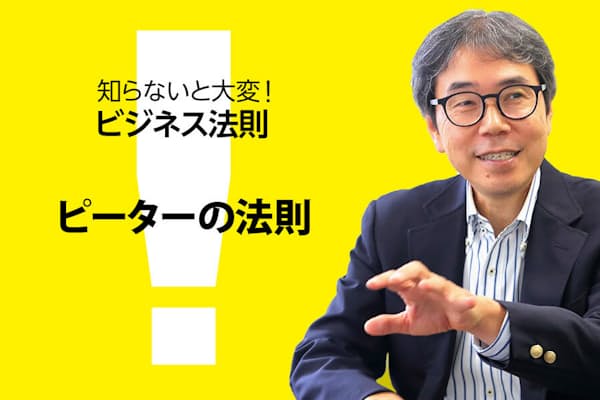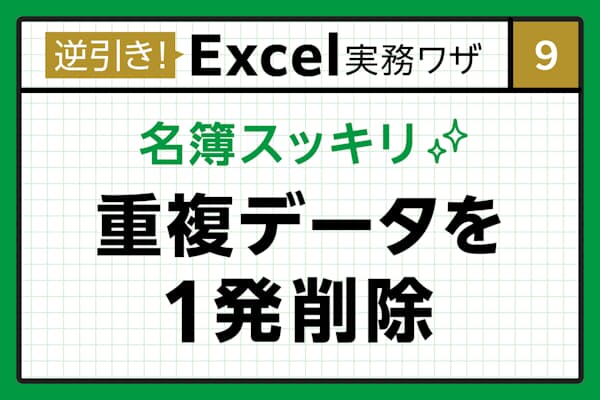転職の本質はマッチング 自分の経歴が生きる会社とは
20代から考える出世戦略(65)

写真はイメージ =PIXTA
前回ご紹介した「デキる就活生に『出世術』学べ 未熟でも成長求める力」について、多くの方は、採用「する」側の立場で読まれたことでしょう。けれども私がお伝えしたかったのは、採用「される」側に必要な本質的な考え方です。それらは新卒や中途転職の場面に限らず、自分の価値を他者に売り込む際に必ず必要になります。
採用の構造を理解しておこう
最初に理解しておくべき点ですが、わかっている会社ほど、自社の採用能力を過信していません。むしろ「確実に何割かは採用に失敗する」ということを理解しながら採用活動を行っています。
その前提で採用活動そのものの構造を考えてみましょう。
多くの場合、採用活動は大きく分けると2つのステップで構成されます。
A. 経歴書などの確認
B. 面接などでの確認
このうち、採用されるためにはどちらのステップを重視すべきでしょうか。
最終的な合格を得るにはどちらのステップで落ちてもいけません。その意味では両方のステップが重要ということになります。
しかしAの経歴については、さほど重要視しないとするという会社があります。これは日本企業の特徴でもある、採用してから育てる方針をとる会社が多いためです。一方でどの会社でも必ずBの面接は行っています。
だから面接対策を行うことが必須、ではあるのですが、合格するために一番重要なことも面接なのでしょうか。
最初に示したように、わかっている企業は、採用で失敗する可能性はゼロではない、と理解しています。それはつまり、面接で失敗する可能性がゼロではない、ということを意味しています。
私自身も著作やブログなどで、相手の本質を見抜くインタビュー手法としてBEI(Behavior Event Interview)手法を紹介していますが、これは少しでも面接で相手のウソを見抜く確率を高めるための手法です。しかしどこまで頑張っても、その確率は100%にはなりません。
仮に採用される側が面接対策をしっかりするということは、企業側にとっては、採用に失敗する確率が増えるということにもつながります。本来であれば採用されないような人が、面接スキルが高かったがために間違って採用されてしまった。その結果、社内で活躍できず、すぐに退職してしまった、という事例はいくらでも見つけることができます。
見えないものを見極めるのが採用活動
採用面接などの選考に限界があるのはなぜでしょう?
それは採用基準が不備であるとか、面接スキルが足りていないからではありません。
また、採用される側がしっかり対策して、面接スキルを高めているからでもありません。
本質的に、その人がどれくらい仕事ができるかを証明できないからです。やらせてみないとわからないし、やらせてみたところですぐにはわからないからです。
仮に就職が物の売買と同様であるとすれば、使ってみなければわからないものを買うなんてことはとてもリスクが高いということがわかります。