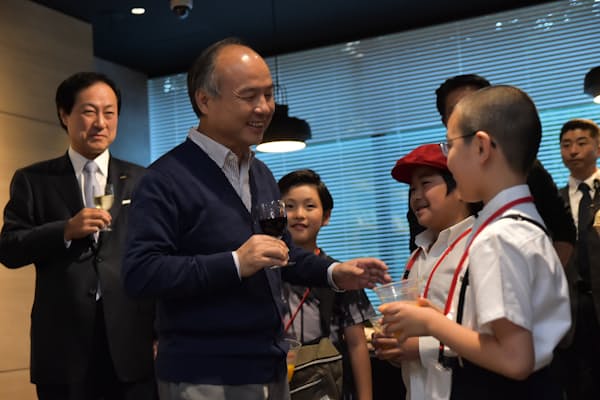LITALICO社長に学ぶ 「自分の問い」の見つけ方
UWC ISAKジャパン 小林りん代表理事(3)

ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパンの小林りん代表理事
社会に変革を起こすチェンジメーカーへの第一歩は、自分が取り組むべき課題を「問い」として設定し、解決に向けて行動すること。全寮制の国際高校、ユナイテッド・ワールド・カレッジ(UWC)ISAKジャパン(長野県軽井沢町)は、独自のカリキュラムでその力を育てています。同校の小林りん代表理事は、そんな「問いを立てる」生き方を体現する一人として、発達障害の子ども向け教育支援などのサービスを手がけるLITALICO(りたりこ)の長谷川敦弥社長(34)を挙げます。(前回の記事は「変革の道は『ワクワク発見』から 問いを立てる力とは」)
◇ ◇ ◇
障害者の課題解決、上場企業で
りたりこは、身体障害、知的障害、精神障害などのある人がそれぞれにあったやり方で働けるように、パソコンや軽作業などの基礎訓練やビジネスマナーの研修を行う就労支援施設を全国70以上の施設で運営する。教育の面でも、学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害、自閉症などの子供たちに個性に合わせた学び方を用意する学習教室を約100拠点で展開しており、従業員は今や2100人を超える。

LITALICOは学習に困難を抱える子どもなどのための教室を全国約100の拠点で開いている=同社提供
そのサービスで多くの障害者や子どもたちがビジネススキルや学力、人付き合いを円滑にするソーシャルスキルなどを身につけ、巣立っていく。ユニークなのは、同社が一定の利益と成長を期待される上場企業であることだ。「障害者の支援は福祉の領域」という常識にとらわれず、2016年に東証マザーズで株式を公開し、17年には東証1部に「昇格」した。社会貢献をしながらビジネスを成立させられることを証明する意味も込めて、上場への道を引っ張ってきたのが、09年に当時24歳の若さで社長になった長谷川氏だ。
長谷川氏は大学2年生のときに「世の中を変える仕事をしたい」と思い立ち、大手IT(情報技術)企業でインターンシップ生として働き始めた。顧客の開拓や新規事業の企画にやりがいを感じ、営業所の責任者を任されるほどの信頼も得たという。ところが、そこには「自分ごと」として考えられる「問い」はなかった。