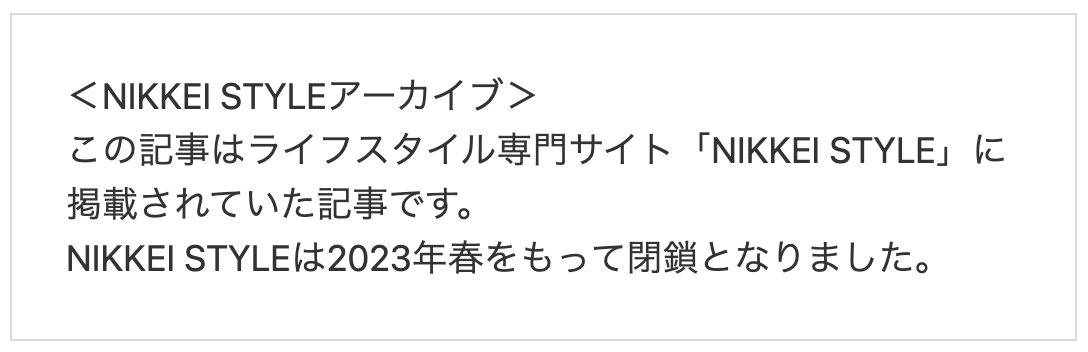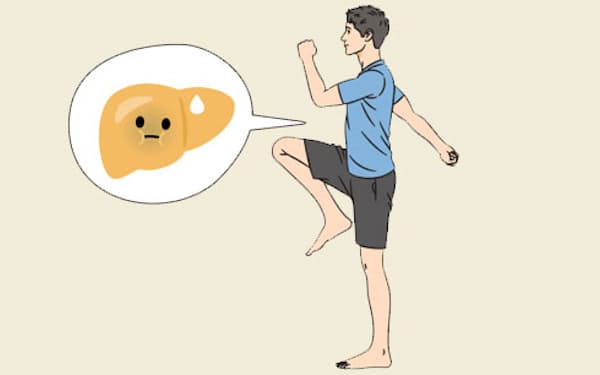エボラ大流行、治療に現地民の壁 医師団は襲撃被害も

アフリカ、コンゴ民主共和国(DRC)北キブ州の街ブテンボで育ったムリャンザ・ユゲットさんは、長距離を走るのが好きだったが、子どもたちと関わるのも好きだった。そのため、ブテンボのアサンプション大学に入学し、幼児教育を学んだ。
ユゲットさんが大学を卒業して1カ月たった2018年8月、世界保健機関(WHO)は北キブ州でエボラウイルス病(エボラ出血熱)が大流行していると、公式に宣言した。そして、ユゲットさんの夢は変わった。国連児童基金(ユニセフ)の仕事に就き、村々を回って、エボラについての知識を広めた。ウイルス性出血熱の広がり方、早期治療で進行を止められること、治療が遅れれば命取りになることを説いた。

人口約8100万人のこの国では、これまで何回も新たなエボラ対策が打ち出された。しかし、その度に、病気に対する恐怖と無知、外国の機関による医療支援への不信、武装した民兵たち、貧困、絶望など、大きな壁が立ちはだかるのだ。
2014年から2016年にかけ、アフリカ大陸で史上最大規模のエボラ流行が起こり、アフリカ西部で1万1000人以上が死亡した。ウイルスがコンゴに現れた2018年半ばまでに、医療専門家たちはエボラ研究をさらに進め、新たな治療法を手にしていた。ユゲットさんのように啓発を担う人たちが、希望を与えられる可能性が出てきた。早く治療を受ければ、回復の望みがあると。
数十年にわたって紛争が続く不安定な状態にあるこの国は、40年間で10回もエボラ流行に見舞われている。エボラによる死者の遺族は、遺体を持ち去って安全に処分しようとする保健スタッフに攻撃を加えてきた。その上、国内では50もの武装民兵グループが活動しており、悲惨な目に遭って家を追われた多くの人が絶えず移動しているため、感染症を封じ込めるのも困難だ。

武装グループは、支援スタッフの活動を妨害することに躍起になっている。よそ者である支援機関が、武器としてエボラを持ち込んだか、エボラから何らかの形で利益を上げていると疑っているのだ。こうした不信感から、多くの住民は病気になっても支援を求めない。2018年末までに、コンゴでのエボラ流行は記録上2番目の規模となった。
親戚中が集まった2018年の年末休暇の間、ユゲットさんはかなり疲れを感じていた。新年を祝う準備や料理の手伝いをしていたとき、彼女いわく「本当にひどい頭痛」が起こり、頭の中でハンマーが打ち付けられているような痛みがし始めた。それが4日続き、次いで39度の熱が出た。家族の中に医師や看護師をしているおじ、おばがいたため、急いでブテンボの病院に連れて行かれた。
ユゲットさんはマラリアだと言われ、通常のキニーネ治療を5日間受けた。WHOの医師がやってきて、彼女の血液サンプルを要請したことで、初めて正しい診断が下された。エボラだった。
どうやって感染したのか、ユゲットさんには分からない。エボラ患者の遺体を洗ったり、葬送の儀礼に加わったりしたことは一度もない。だが、葬儀に行ったことは何度もあった。愛する人のなきがらに触れた人たちの隣に座ったり、手を握ったり、抱き締めたりしていた。
ユゲットさんは短期間で治った。診断が早く、出血を伴う下痢、嘔吐、激しい腹痛が起こる前だったからだ。どうやってエボラに感染したかではなく、この事実が重要だと彼女は話す。ブテンボにあるITAVエボラ治療センターで1週間治療を受けると、帰宅できるほど回復した。この経験で、ユゲットさんは医学の進歩を実感した。
この記事のために筆者がユゲットさんに話を聞いた日、彼女が入院していたブテンボの治療センターを武装した男たちが襲撃した。施設を守ろうとした警察官が殺され、保健スタッフも数人負傷した。そこからほど近い町、カトワにある国境なき医師団の治療センターが2月26日に放火されてから、1カ月もたっていない。このときは保健スタッフ1人が死亡し、もう1人が負傷したため、国境なき医師団は活動を中断した。

このエボラ流行との闘いを一変させるかもしれない「武器」が、カナダの科学者が開発したワクチンだ。2015年の大流行で試験的に使われ、これまでエボラ患者と密に接触している親類や医療従事者など、10万人以上がワクチン接種を受けている。WHOは、エボラによる死を減らすのに、このワクチンが非常に有効なようだと報告している。
こうした有望なニュースがあっても、エボラに悩まされている北キブ州の住民たちは、国連の白いトラックや外国の医療機関の到着に疑いの目を向ける。
人口100万を超すブテンボでは、90%近くがナンデ族であり、伝統的に部外者を信用しない。この街には、集落を基盤とした武装集団もあり、混乱する貧困地域にプロパガンダと武力を利用して影響力を及ぼしている。こうした武装集団の中には、国境なき医師団や国際医療隊(International Medical Corps)といった支援団体に関して、誤った情報を広めるものもいる。結局「よそ者」の医療者たちは、必要があってしていることを非難される。エボラ患者を強制的に隔離する、現地の風習を無視した埋葬方法を押し付けるなどだ。

ブテンボの宿で、ジョファさんという若い男性と話した。エボラ治療センターが襲撃される理由について、彼は自分の考えを話してくれた。「おじが病気になると、エボラだと思ったらしく、武装した男たちが家にやってきました」。ジョファさんはたどたどしい英語で説明した。「男たちはあらゆるものを壊し、おじを連れて行きました。家財も奪われ、何を取られたのか把握しきれないほどです。彼らは、やりたい放題やるための理由にエボラを利用しているのです」
コンゴでは、「第一に、多くの人が広範囲に移動しているという状況があります。武装した民兵に襲われた恐ろしい体験から逃れようとしているのです」。世界保健機関(WHO)の緊急オペレーション・プログラム責任者であるミシェル・ヤオ医師は話す。「第二に、住民たちは外国人に全くなじみがないため歓迎せず、エボラのような事態も全く経験がありません」。医療支援機関は「西アフリカの大流行から多くの教訓を学んだ」ものの、「この国の流行には特殊な事情があり、対処が非常に難しくなっています」とヤオ医師。
一方、ブテンボから90分の都市、ベニでは様子が異なる。
コンゴとウガンダとの国境に近いベニでは、歴史的に複数の民族集団が混在し、平和に共存してきた。2018年秋、ベニを中心にエボラ流行の第2波が起こったとき、医療スタッフは住民から抵抗に遭ったとWHOのヤオ氏は話す。「安全な埋葬方法を拒む人たちでした。1つの家族内でたくさんの人がエボラで死に、その家族から感染が広がったのです」
住民の理解を得るため、WHOや提携団体は現地住民からボランティアを募り、地域への働きかけや、医療活動の補助ができるように研修をした。これが不信感を和らげるのに役立ち、医療スタッフはウイルスのまん延にわずかに先んじることができた。
ベニ・レフェランス総合病院の入口では、落ち着いて列を作り、消毒の手順に従う人々を見た。塩素処理水で手を洗い、靴の裏にも塩素処理水をスプレーする。長靴や手袋といった医療機器の洗浄や、食事の準備のために出勤してきた人たちだった。あるいは、いくつも並んだ「アウトブレイク用生物防護緊急ケアユニット」(略称:CUBE)の中にいる患者を訪ねてきた人もいる。国際医療活動同盟(ALIMA)が使っているCUBEは、大流行する可能性が高い、感染力の強い病気の患者を治療するために作られたプラスチック製の隔離ユニットだ。

CUBEに入っていたエボラ患者は、治療の主要な段階を終えて体力を取り戻すと、心理カウンセリングを受ける。その後、隔離ユニットを出て、回復中のほかの患者たちとガーデンエリアで交流できる。このエリアは、離れたところから家族が様子を見ることができる。「CUBE越しだけでなく、CUBEから出て動き回っている患者本人を家族が見ることができれば、エボラ治療センターでの処置をめぐる恐怖や陰口、噂をある程度なくせます」と保健当局者は話す。
テントを立て、治療のために自分たちの親類をそこに運び込んでいく外国人を、この国の多くの人々は良く思わず、信頼もしていないことをムリャンザ・ユゲットさんは分かっている。だが彼女はそれを変えようと活動しており、自らの体験を語ることもその1つだ。
彼女がエボラの診断を受けたとき、家族、友人、ボーイフレンドはパニックに陥らず、早く治療しさえすれば何も怖いことはないのだと気が付いた、とユゲットさんは言う。そして彼女のエピソードは間違いなくハッピーエンドだ。エボラにかかったのが数年前だったとしたら、ユゲットさんの家族は葬儀の計画を立てていたかもしれない。しかし今、彼女は自分の未来を計画している。そこには、NGOでキャリアを積むこと、伴侶を得ること、子どもを5人もうけることが含まれている。
次ページでも、未だ収束しないエボラと闘う人々の姿を紹介する。












(文 RACHEL JONES、写真 NICHOLE SOBECKI、訳 高野夏美、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック 2019年6月1日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。