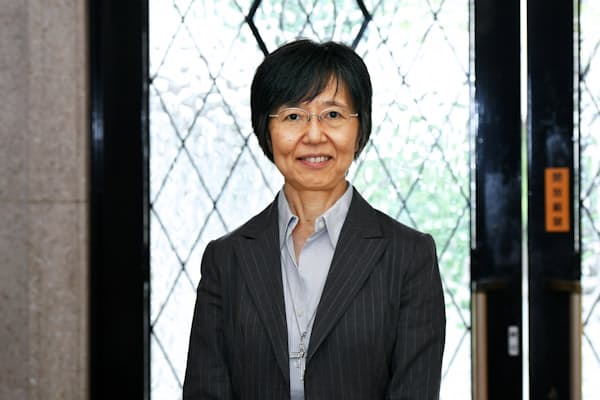ランチは生徒が作る 「起業家」の志を育む自由学園
自由学園の高橋和也学園長

自由学園の高橋和也学園長(バックの女子部食堂で毎日、職員と生徒が一緒に手作りランチを味わう)
東京都東久留米市にある私立の自由学園は、1921年に日本初の女性ジャーナリストといわれる羽仁もと子と、報知新聞編集長を務め、雑誌「婦人之友」をもと子と共に創刊した夫の吉一が創立した。「生活即教育」の理念に基づく、地に足のついた教育は、男子の新入生が自分の使う机とイスを自ら木工で作る慣例に象徴されている。2年後に創立100周年を迎える同学園の高橋和也学園長は「創立者2人が社会起業家の先駆けだったからこそ、次世代のチェンジメーカーが育つ苗床になり得る」と話す。
一貫教育、最長で19年間に
広大なキャンパスに抱かれて学び暮らす学園だ。創立者は一帯の土地約33万平方メートルを取得し、約10万平方メートルを学園の敷地に充てた。残りは分譲住宅地となり、学園町が生まれた。学園に足を踏み入れると、高原のキャンプ場にでも迷い込んだ気持ちになる。4000本もの木々が生い茂る広大な緑の中に低層の校舎が点在する。都内とはとても思えないほどの四季の息づかいにあふれ、生徒が花や作物を育てる畑もある。
幼稚園から最高学部(大学に相当)まで、最長で19年間にわたる一貫教育を行う。創立者の娘を学ばせる学校として、先に女子部が発足。後から男子部が加わった。全体としては共学だが、中等科、高等科は女子部と男子部に分かれる。小学校にあたる初等部を経て、女子部(中等科、高等科)、男子部(同)に進む。高等科からしか進めない最高学部を除けば、どの段階からも入学できる。最高学部は、文部科学省から大学としての認可をあえて受けておらず、卒業しても学士資格は得られないが、多くの企業では大学相当の扱いを受けている。ほかの大学の大学院へ進む人も珍しくない。
初等部に入る前の児童を対象にした幼児生活団幼稚園の存在も知られている。東久留米市のキャンパスにある幼稚園以外にも、羽仁夫妻が組織した婦人団体「友の会」が主催する「幼児生活団」があり、オノ・ヨーコ氏や坂本龍一氏、蜷川実花氏らも通ったという。作家のいしいしんじ氏は、子供も幼児生活団に通わせた。筆名がひらがななのは、生活団で過ごした4歳のとき、最初に書いた自作ストーリーでそう書いたからだという。