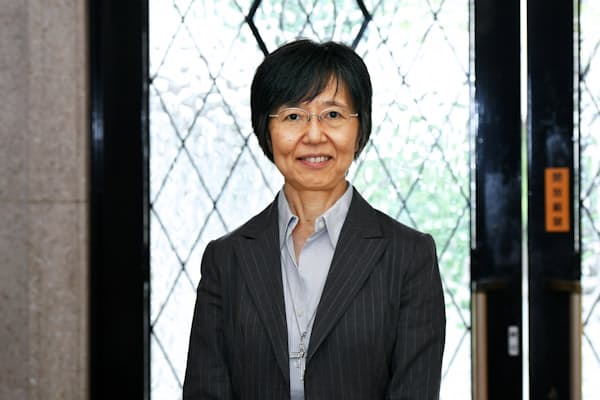「良妻賢母」の昭和女子大改革、小さな実績づくりから
昭和女子大学 坂東真理子理事長兼総長(上)

昭和女子大学の坂東真理子理事長兼総長
少子化、共学との競合など、女子大をめぐる環境は厳しさを増している。そんな中、志願者数を15年で約3倍に伸ばしているのが昭和女子大学(東京・世田谷)だ。就職率では、卒業生1000人以上の女子大で8年連続の首位を維持(大学通信調べ)。伝統的な「良妻賢母」育成校からの脱皮を果たした。仕掛け人となった坂東真理子理事長兼総長(72)の創造性の源泉とは。
――2003年に理事、04年に教授として昭和女子大に着任しました。そもそものきっかけは。
「2000年代初頭、昭和女子大は他の女子大と同様『氷河期』ともいえる状況にありました。志願者数が減少を続ける中、行く末に強い危機感を抱いた人見楷子理事長(当時)が、私に声をかけてくださったんです」
――国家公務員を34年間務め、57歳で退官されてからの転身でした。
「当初はカルチャーショックを受けました。『アリス・イン・ワンダーランド(不思議の国のアリス)』ならぬ、『マリコ・イン・ワンダーランド』です(笑)。特に印象的だったのは、学生も教職員も非常に控えめな人が多かったこと。伝統的に『良妻賢母』教育に力を入れてきた大学でしたから、服装などの規律も厳しく、とにかく謙虚であることが美徳とされていたのでしょう。あいさつを交わしても、声が小さい。自分の意見もはっきりと言わない。これは(一人ひとりに力や権限を持たせる)エンパワーメントが必要だと思いました」
女性たちが自立して経済を支えていくことが不可欠
「同時にそれが、大学としての苦境を脱するための条件だということも確信しました。自分は一歩引いて夫を支え、できのいい子どもを育てることで社会に貢献する――そんな『良妻賢母』像が、20世紀の日本の社会では求められていました。労働人口の不足が加速し、働き方も大きく変わりつつある今の日本では、女性たちが自立して経済を支えていくことが不可欠です。そうでなければ、自分や家族の生活も守れない。それなのに旧来型の教育を続けていれば、大学が社会に選ばれなくなるのは当然でしょう」
「私は国家公務員として、女性の地位向上のために尽くしてきたキャリアがありました。男女雇用機会均等法や育児休業法などの法律・制度は、あくまで女性たちが活躍するための舞台を整えるものでしかありません。舞台が立派でも、主役の俳優である女性たち自身が意識を変え、力を付けなければ、何も始まらないわけです。昭和女子大での私の使命はこれだ、と思いましたね」