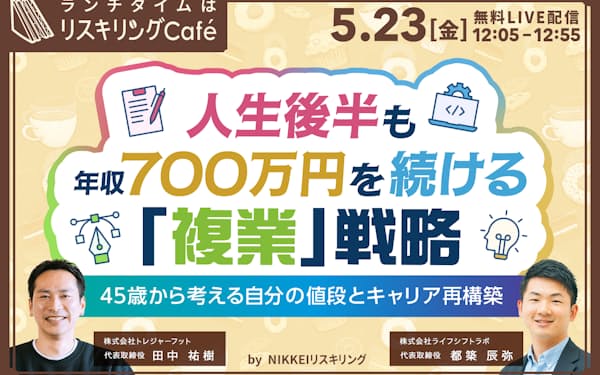もはや大学に遊ぶ暇はない 親の知らない学生事情

次の元号が「令和」と発表されました。大学新入生はこれから気持ちも新たに大学生活を迎えることでしょう。ところで、新入生とその親世代は意外と現在の大学講義事情を把握していないというのが私の実感です。「大学に行かず遊んでいた」「テストは名前を書くだけでどうにかなった」という親世代のこんな武勇伝めいた話もよく耳にしますが、新入生の皆さん、真に受けてはいけません。
■大学で単位を取るのは簡単ではない。履修計画をきちんと
現在の大学生の親世代と言えば40代から50代が中心。実は筆者も44歳で同じ世代です。文系学部の大学(東洋大学社会学部)を卒業したのが1999年。いわゆる楽勝科目も多かったですし、100人を超えるような、もはやゼミとは言えないようなゼミも珍しくありませんでした。
さて、私のような特に文系学部出身の親世代の人間の中は「大学=遊ぶところ」との思いが強く、我が子にもそのように伝えてしまいがちです。ところが、40代の親世代が大学を卒業した後の2007年、文部科学省は大学設置基準を改正します。この影響で大学の単位認定は一気に厳しくなりました。
今は出席も厳しく、基本的には3分の2以上の出席が求められます。テストも同様で、こちらも最低限の成績をクリアできなければ単位が認定されません。計画的な履修登録が必須です。
入学式が終わると、どの大学でも履修登録のガイダンスがあります。新入生は履修登録ガイダンスに必ず出席したうえで、必要な部分はちゃんとメモを取っておくようにしましょう。
注意が必要なのは、必ず希望の授業を履修できるものではない、ということです。人気科目はそれだけ多くの学生が受講を希望します。定員を大きく超えると抽選で漏れてしまう事態も起こりえるのです。希望通りの履修ができないと、ほかの科目を取らなければならないかもしれません。そうなると、履修計画の練り直しです。これらが落ち着くのが早くても4月中旬、遅い大学だと4月下旬か5月以降にずれ込むところもあります。
ですので、「学費や生活費のためすぐにでもアルバイトを始めたい」という新入生やそれを期待する親もいるかもしれませんが、履修科目が確定するまで、アルバイトは決めない方が無難です。
■親の想像以上に多彩な教養科目

また、親世代の想像以上に多彩とな授業が展開されているのが、教養科目です。
例えば、3月に古舘伊知郎さんが母校の立教大学で客員教授に就任しました。春学期の科目「現代社会における言葉の意味」を担当し、通期の講義(全14回)を担当します。立教大では秋学期科目で「立教OBOGの『社長の履歴書』」があります。同科目は峰岸真澄(リクルートホールディングス社長)、井田純一郎(サンヨー食品社長)など同大OBOGの社長がリレー式に講義をする、というものです。
明治大学では「地方自治体の仕事と労働組合」を開講。科目名にある通り、労働組合の自治労による寄付講座です。地方自治体や公立病院などの現役職員(かつ労働組合員)が講義をします。
山形大学は「Jリーグと地域社会(山形から考える)」を開きます。地元のJリーグチームであるモンテディオ山形が関わる講義です。講義だけでなく、職員とのグループワークもあります。
こうした教養科目は上に挙げた3大学だけではありません。中規模以上の大学であれば、教養科目を多彩にしているのが現状です。
さらに自校に希望する教養科目がなくても大丈夫。都市部を中心に、近隣大学と提携する大学コンソーシアムがあります。立教大学だと早稲田大学、学習院大学、学習院女子大学、日本女子大学とf‐Campusを形成。立教大生は他の4校の単位を履修することができます。
京都には大学コンソーシアム京都、大阪には大学コンソーシアム大阪があり、それぞれ加盟校の学生は他の加盟校の単位を履修することも可能。このように大学の講義は親世代が想定している以上に変化しています。新入生はどんな科目があるか、宝探しのような気分で履修登録を進めてみてください。
1975年札幌市生まれ。東洋大学社会学部卒。2003年から大学ジャーナリストとして活動開始。当初は大学・教育関連の書籍・記事だけだったが、出入りしていた週刊誌編集部から「就活もやれ」と言われて、それが10年以上続くのだから人生わからない。著書に『キレイゴトぬきの就活論』(新潮新書)、『女子学生はなぜ就活で騙されるのか』(朝日新書)など多数。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界