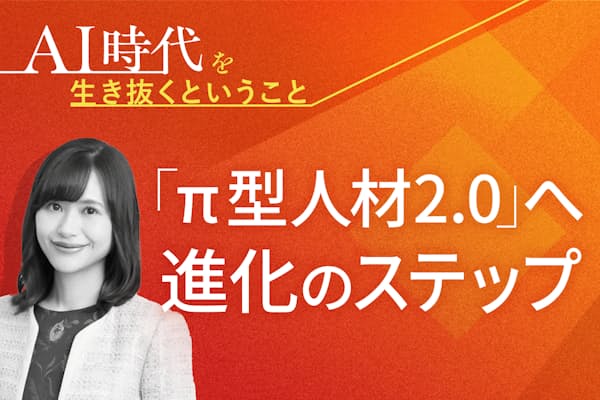世界25万人の経験・スキル網羅 日立動かすHRテック
日立製作所人財統括本部グローバルトータルリワード部長 古田大三氏

日立製作所人財統括本部グローバルトータルリワード部長の古田大三氏
人材を集めて育て、適切に配置して社員のやる気を引き出す企業の人事部門。働き方改革と成長の両立といった課題も多い。その解決に人工知能(AI)やクラウドサービスなど最新のテクノロジーを利用する「HRテック」が広がりつつある。2018年に世界規模での人材マネジメントを強化する統合プラットフォームを導入した日立製作所に、HRテックの勘所や課題を聞いた。
人材情報、「見える化」へ新システム
日立は18年1月、「人財マネジメント統合プラットフォーム」と名付けたシステムを導入した。世界各地の従業員の情報を登録するデータベースをつくり、マネジメントに生かすシステムだ。まず日立本体と海外現地法人の従業員約5万人を対象に稼働した。グループ企業にも順次導入し、約25万人まで広げる計画だ。米IT会社、ワークデイの人事管理クラウドサービスを基に構築した。
新システムの狙いは人材情報の「見える化」だ。海外のグループ企業も含めた従業員は約30万人に上り、その約45%は海外の人材だ。組織が巨大なので、どこに、どのような能力や経歴を持つ人材がいるかをすぐに把握できないのが課題だった。
世界規模の人材データベース構築に12年度から着手し、16年2月には新プラットフォームを海外のグループ会社で試験的に導入。18年に本格導入に踏み切った。古田大三・人財統括本部グローバルトータルリワード部長は「すべての情報を一つのシステムで管理できるオールインワンで、スマートフォンやタブレットなどモバイル機器を使える。いつでもどこでもデータを見られる」と利点を明かす。
人事関連のシステムは、会社や部署ごとにばらばらに構築してきており、グループ全体で「2000以上のシステムがあったとみられる」(同社)。従来のシステムをすべて新システムに統合するわけではないが、世界共通の人材情報のプラットフォームとして機能するという。情報を一元管理し、組織編成や人材の評価・育成などに役立てる狙いだ。