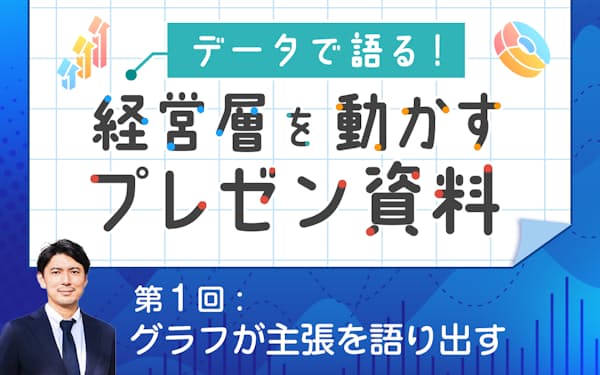AI時代を生きる君たちへ
池上彰の大岡山通信 若者たちへ

最近、高校生や大学生から「人工知能(AI)によって、将来、私たちの仕事はどうなるのでしょう」と質問されることが多くなりました。若者たちにとってAIは脅威に感じる対象でもあることがわかります。今回はAI時代の働き方、生き方について考えます。
■人間の能力を超える
日々、新聞や雑誌を読んでいると、AIというキーワードが必ず出てきます。2045年には、AIが人間の能力を超える「シンギュラリティー(技術的特異点)」と呼ばれる節目が来ると言う論者もいます。「AIで無くなる仕事」が強調されれば、不安になるのも無理のないことです。
私が講義を受け持つ東京工業大学の学生や卒業生にも意見を聞きました。「AIはこの先、自らアップデートし進化していくのでは」「ロボット開発はどこかで怖くなるのでは」という懸念がある一方で、「個性があり、予測不可能なのが人間の行動や感情だからAIでは代行できない」と指摘する声もありました。
理工系のスペシャリストである東工大生ですら、AIの可能性ばかりでなく、その能力に対する複雑な気持ちを抱いているのです。
AIはどんな分野に広がっているのでしょう。たとえば創作の分野でも進歩しています。18年秋、東工大のシンポジウムで人間とAIがつくった俳句を比べましたが、聴講者の方々は明確に見分けがつきませんでした。意外に進歩しているのですね。

ビジネス分野では、消費者の問い合わせに、ふさわしい回答を示す機能が紹介されています。AIは大量の情報から一番適した答えを、短時間で導き出す能力に優れることを示す事例です。企業の顧客対応の手法が大きく変わるでしょう。
技術革新の代表例が自動運転システムでしょう。自動車業界は、環境問題への対応も加わって電気自動車(EV)などへシフトしています。エネルギーやIT(情報技術)などの分野の「革命」ともいえる進化のスピードには驚かされます。
■人口減少社会を支える
AIと仕事が議論される背景の一つには、日本が直面する人口減少の問題があります。
国立社会保障・人口問題研究所のこれまでの推計によると、日本の人口は30年にはすべての都道府県で減り始める。53年には1億人を割り込むという分析もあります。時期の多少のズレはあるかもしれませんが、厳しい現実が待ち構えています。
労働力の不足は既に人件費の高騰を招いています。企業には深刻な経営課題です。人間がこなさなくてもすむ業務から、AIシフトが進むでしょう。外国人の人材活用へと動き出しているのも、根底には日本の人口減少という問題があるのです。
日本においても、石炭から石油へのエネルギー革命、ITの普及による技術革新などによって、人々の働き方が大きく変わりました。仕事が無くなるというマイナスの側面だけをみれば心配ですが、新しい仕事や役割が生まれるというプラスの側面もあるはずです。
大きな視点でみれば、日本の社会や産業にAIを根づかせていく新しい取り組みが始まっています。AIを使ったシステムの開発だけでなく、法律や制度の見直しも必要です。こうした分野を担当するのはやはり人間なのです。

若者たちにとって新しい社会をつくる仕事に参加できるチャンスなのです。しかも、日本は世界にも例のないスピードで超高齢社会がやってきます。人間の暮らしを根本的に支える最先端の技術が求められるはずです。
いま、高校生や大学生の君たちに大事なことは、「どの仕事を選ぶか」ということよりも「何を学び、どんな働き方をしたいのか」という視点だと思います。
そしてどんな社会を実現したいのか、その中でどんな役割を果たしていきたいのか考えてみることが大切です。これからの働き方、生き方を考えるよいきっかけになるはずです。仲間と大いに議論してください。
[日経電子版2019年1月28日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。