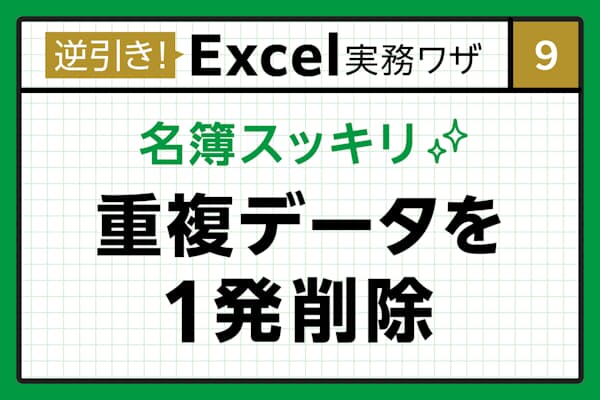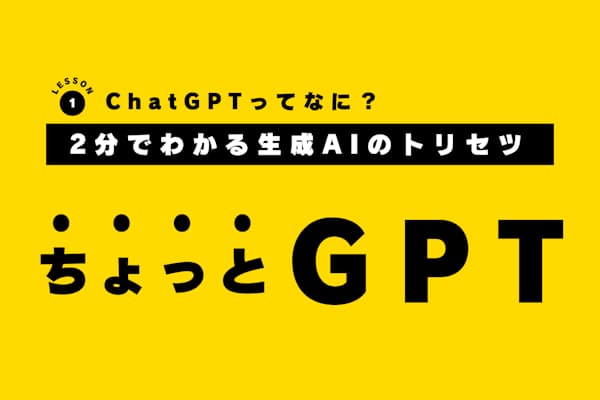物産トップはジャングルガイド 安永社長が説く突破力
三井物産の安永竜夫社長(上)

三井物産の安永竜夫社長
三井物産の安永竜夫社長は2015年、54歳のときに32人抜きで社長に抜てきされて話題となった。若い頃から剛腕商社マンとして海外を飛び回り、大型プロジェクトをいくつも手掛ける中で、リーダーシップを磨いてきた。トップとして巨大組織をどう導こうとしているのか。
32人抜きで社長、即答で受ける
――総合商社では異例の若さで社長に就任しました。まだ早いとは思いませんでしたか。
「15年1月に当時の飯島彰己社長(現会長)の秘書から携帯電話に着信があり、都心のホテルに来るように言われました。ご丁寧にもう一度電話があり、誰にも言わずに一人で来いと。時期的に人事に関する話かとは考えました。社長に指名されたときは、まさか本当に自分がと驚きましたが、選ばれた以上はやるしかないと思い、即答で受諾しました。期待に応えるのが組織人の務めです。自分でも若過ぎると感じましたが、三井物産の社長は体力が必要で、若くないと務まりません。馬車馬のごとく走ってきた3年間でしたね」
――なぜ自分が社長に指名されたと思いますか。
「私はプラント建設など設備系が長く、様々な産業界との接点がありました。成長分野であるモビリティー(移動)分野の本部長を務めたことや、経営企画部長として全社目線でいろんなことを考えてきたことも評価されたと想像します。いくつかの場面で相手が誰であろうと物おじせずに発言してきたことも評価につながったのだと思います」
――社長に就任しても年上の役員ばかりでやりにくくなかったですか。
「40歳前で課長になったときから年上の部下がいました。心掛けたのは、部下ではなく仲間として接することです。とはいえ評価者として、その人の良い所をきちんと見て、どういう役割を期待しているかをはっきり示し、結果を評価することは続けてきました。年上であれ年下であれ、誠意を持って対応することは大事です。社長になってからも基本は丁寧語で話しています」
――社長就任後に全社のリーダーとして、まず実行した改革は何でしょう。
「毎週火曜日に開いていた経営会議を月曜日の朝に変えました。火曜日に会議があると役員の行動の制約が大きくなります。特に海外出張に行きづらくなります。月曜朝に会議を済ませれば、その午後から海外に飛び立ち、欧米なら週初から仕事ができます」
「社員の働き方改革にもつながりました。従来は火曜日に設定した経営会議のための資料を、社員は週末に作成することも多かった。これはよくないので、前倒しした月曜の経営会議に合わせるように、資料は金曜日に作ってもらい、役員は週末に読み込むように改めました。これによって社員は週末にしっかり休みが取れるようになりました」