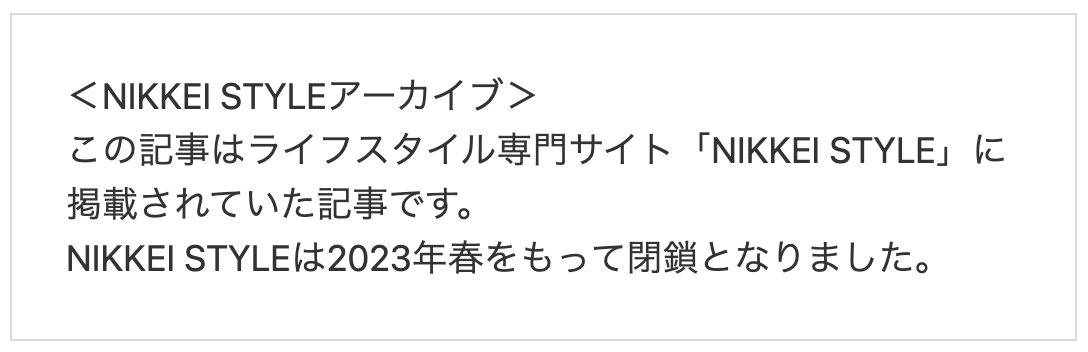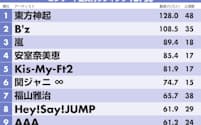大泉洋、難病患者の役に挑む 演じることに使命感
年1~2本のペースで映画主演を続ける40代俳優のトップランナー・大泉洋。2018年12月28日から公開されている映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』では、筋肉が衰えて動けなくなる難病と闘う主人公の役に挑んでいる。

『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』は、第35回大宅壮一ノンフィクション賞と第25回講談社ノンフィクション賞をW受賞した『こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち』(渡辺一史・著)を、『ブタがいた教室』(08年)の前田哲監督が映画化。大泉洋は、「筋ジストロフィー」を患い、02年に42歳で他界した鹿野靖明さんを演じている。
「まずは『こんな夜更けにバナナかよ』って、このタイトル一発に力がありましたよね。『何なんだろう、面白そう!』と思いました。そして話を聞くと、鹿野さんという人は、筋ジスで首と手しか動かないのに病院を飛び出して、たくさんのボランティアを集めて札幌で自立生活をしていた、と。しかもボランティアの方々に様々なワガママを言っていたという(笑)。『なぜそんなことができたんだろう。知りたい!』っていうのが、オファーを受けた時の感想でした。
撮影前に原作を読んで、筋ジスや治療法を学んだり、鹿野さんのお母さんや実際にボランティアをしていた人たちに話を聞いたりしました。鹿野さんと同じように人工呼吸器を付けた障害者の方たちにも会ったんですけど、彼らが望んでいたのは、『普通の人と同じように生活したい』ということ。
例えば、みんな彼らに話しかけていいか分からないから、最初に介護の人に話しかけるんですって。『こういうこと、言ってもいいですか?』って。だけどそうじゃなくて、『自分に言ってほしい』と。鹿野さんは、そういう思いに、正直に生きた人というか。障害のある人が普通に生きていくために、あえてワガママを言ったり、迷惑をかけたりしながら生きていたんじゃないかと思いました。
面白かったのは、人によって、鹿野さんの印象が違うことです。呼吸器を付けたある方が、『この人にはこれが頼める、この人には頼めないって、僕らは細かく人を見て頼むんです』と言ってたんですけど、鹿野さんも人によって態度を変えていたみたいなんですよ。だから『鹿野さんはこういう人だ』と言う人もいれば、『いや、そんなのは鹿野じゃない』って人もいる(笑)。なので、僕たちは僕たちで鹿野さん像を作っていくしかない。
その時に、実話を伝えながらも映画として面白いものにするっていう、折り合いが難しくて。前田監督と4時間くらい電話で話しながら、セリフやシーンを加えたり削ったりしたこともありました」
顔認証できないほど別人に
撮影は、北海道で約1カ月。大泉は外見も本人に近づけようと、約10キロの減量を行い、コンタクトの上にメガネを掛けるなど、細かい役作りをして挑んでいる。
「実際のところ鹿野さんは視力が弱かったから、メガネは度のきついものをしていて、僕も同じくらいの度のメガネにしたかったんだけども、そうすると相手が見えなくて、お芝居にならないわけですよ。僕は、目がいいから。だからまず視力を落とすためのコンタクトを付けて、その上でメガネを掛けて見えるようにしました。
困ったのは、メガネで視界が歪んで酔ってしまうこと。あと、ケータイが顔認証しなくなったんですよ(笑)。しかたなくパスコード入れたら、今度は学習するんですよ。『あ、これも大泉さんでいいんですね! 分かりました~』って(笑)」

「撮影期間はいろんな奇跡が起きて、鹿野さんに導かれているようでした。例えば、実際に鹿野さんが住んでいた部屋がたまたま空いて、ロケができたんですよ。美瑛のペンションも、鹿野さんが旅行で本当に泊まった宿。さらに鹿野さんの主治医だった方が今回、医療監修として参加されていたので、僕はいろんな現場で聞けるわけです。
『この時の鹿野さんは、どうだったんですか?』って。そこで『こうでしたよ』っていう生の声を聞いて、ホットな気持ちで演じられたので、鹿野さんと僕のシンクロ率が高かった。撮影が終わった時には役と離れるのが寂しくて、"鹿野ロス"になりました」
「個人的に"お涙ちょうだい"的な話は好きではないので、そういう作品なら僕は出られないなと思っていたんですが、この映画はどちらかというとコミカル…ある種のコメディに近い」と語る本作。大泉のコミカルな持ち味と人情味が生かされ、笑って泣けて、心温まる感動作に仕上がった。
物事を「不幸貯金」で判断
18年は映画『恋は雨上がりのように』や、山田洋次脚本のTBSスペシャルドラマ『あにいもうと』などに主演。演劇ユニット「TEAM NACS」では約2年半ぶりに本公演を行い、NHK『SONGS』の責任者にも就任するなど、八面六臂の活躍を見せた大泉。19年には46歳になるが、40代後半を、どのように歩んでいきたいのか。
「自分でこうなっていきたい、みたいなことはなくて、『面白い作品に出合いたい!』っていう、それに尽きますね。
今、世の中でこういうものが面白いんだ、みたいなアンテナを持ち合わせてるタレントさんもいると思うんですよ。でも、僕にはそれがない。たぶんプロデュース力ってものがないんですよね。だから他力本願だけど、マネジャーに頼るしかない(笑)。そして46歳なら46歳の『今、やるといい作品』に出合いたいなあ、と願うだけ。
ただ、その出合いの力みたいなものは、信じてるかもしれないです。僕には『不幸貯金』ってものがありまして。いいことも悪いことも同じだけあると思ってるから、よくないことが起きた時に、『これはいいことが近づいてるな』と思うんです。
『行きたかった店に来たのに、定休日~!』みたいなことが続くと、『これは相当、デカい仕事が近づいてるぞ』と思う(笑)。そうして本当に仕事が来た時の『キタキタキター!』っていう喜びが忘れられない。『こんな夜更けにバナナかよ』も、まさにそういう作品でしたね。
普段は『楽しんでもらえればいい』が基本なんですが、この映画に関しては、何か使命があるような気がします。『ノーマライゼーション』という言葉がありますけど、障害を持つ人が一般の人と同じように生きられるようにしようっていうのは、まだまだ僕たちの社会が抱えている課題。なかでも、日本はそこがすごく遅れてると思うんですよ。だから障害者の方が夜中に『バナナが食べたい』って言うと、ワガママだと思われるわけです。
でもそれは、『動けないんだったら、食べるんじゃない』という健常者の論理。鹿野さんを演じることで僕自身、考えさせられることも多かったですし、『こんな夜更けにバナナかよ』がワガママにならない時代になるといいよね、と思っています」
(ライター 泊貴洋)
[日経エンタテインメント! 2019年1月号の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。