グループディスカッション 下手でも通過の3条件 VS. 上手が落ちる3条件
ホンネの就活ツッコミ論(10)

グループディスカッション(以下、GDと略)は選考の初期から中盤にかけて利用される選考方法です。書類選考(エントリーシート・履歴書)は採用担当者が読み手となります。つまり、ある程度は対策が可能です。適性検査のうち、能力検査はひたすら勉強するしかありません。こちらも対策可能。
面接は採用担当者ないし部長・役員クラスが面接官となります。人対人なので対策できない部分もあります。が、一方で、学生よりは確実に年齢が上。ということは、年上が相手だから、と割り切ることが可能です。その点、GDはどうでしょうか。面接と同じ人対人なので、不確定要素が大きいです。
さらに言えば、相手は同じ選考に参加している学生です。学生よりもはるかに年上だからというわけでもなく、まして採用の権限があるわけでもありません。全員が次の選考に進むのか、それとも1人しか通過しないのか。あるいは2人か3人か、全く不明。盛り上がればいいというわけでもなく、盛り下がっても落ちそうです。
全く読めない、とこぼす学生が多いのがGDの特徴でしょう。それから、普段から話している大学の同期ならまだしも、見ず知らずの学生とGDを進めることになります。うまく話せない、と嘆く学生も多いのも特徴です。では、企業はどんな思惑でGDを見ているのでしょうか。
GDは全てが討論、ではない

GDはパターンとして主なものは3つあります。抽象型(テーマが抽象的)、ケーススタディ型(テーマがケーススタディそのもの)、ディベート型(ディスカッションというよりも討論)です。ディベート型はベンチャー企業の一部などでしか利用されません。そして、残りの抽象型とケーススタディ型は他の学生を言い負かせるかどうか......、ではなく、実のある議論をしたかどうかが大事です。
このディベート型の実施かどうか、というところが大きな分かれ道です。議論慣れしている一部の学生や留学生は、全てのGDについてディベート型と勘違いし、他の学生をいかに言い負かすか、その一点に注力します。
ところが、抽象型とケーススタディ型はともにディベート型と異なり、討論能力を中心に見ているわけではありません。むしろ、討論能力が強すぎると、「我が強すぎて、うちでは合わなさそう」「他の学生を巻き込めないのはどうか」などと考えて、評価が落ちてしまいます。
不確定要素が強いからこそGDは面白い
GDについては曽和利光さんのコラム(3月30日掲載)でも書かれているのでそちらも合わせてどうぞ。ここで書かれていることをざっくりまとめると、就活生個人の性格の他に「アサーティブネス」(相手が受け入れやすい言葉遣いに気をつけること)、「テーマに対する現状認識や問題の明確化、原因の分析」、「アイデアの実現可能性や効果の明示」などがGDの成否を分ける、とあります。
私もそこは同じ。付け加えると、不確定要素が大きい中で学生がどう動いたか、そこを採用担当者は見ています。たとえば、GDの特徴として、他の学生の暴走があります。話が長い、人の話を聞かないなど、いわゆる痛い学生ですね。さて、この痛い学生と一緒になった学生は、もうこのGDは終わった、と投げてしまうのか。それとも、どうにか議論を前に進めようと努力するのか。
前者の学生が入社した場合、うまく行っている時はいいですが、少しでもネガティブな状況になったとき投げてしまう可能性が高いはず。いわゆる、「攻めには強いが、守りに入ると弱い」タイプですね。一方、ネガティブな状況でもあきらめない、何とか状況を好転させようと頑張れる社員はどうでしょうか。ピンチをチャンスに変える、過去の「私の履歴書」に登場した社長のエピソードに近い活躍が期待できそう、そう思いませんか? 不確定要素が大きい中で学生が与えられた環境でどう頑張るか、そこを企業は見ています。学生の負荷は大きいのですが、逆に言えば、そこが面白い、とも言えます。
役割は着いた方が目立つ?それとも不利?
GDと言えば、役割。「司会をやれば目立つから有利」と言われるようになったのは1990年代ごろから。その後も「タイムキーパーは目立たないから不利」「書記は実はおいしい」など様々な俗説があります。学生を就活イベント・模擬GDなどで観察していると数年前から首都圏・関西圏の学生を中心に役割を特に決めないパターンが目立ってきました。
結論から言えば、ポジションの有利不利は全くありません。役割を決めないパターンももちろん有効。司会有利説は議論をリードできなければむしろ不利。タイムキーパー不利説も時間の話しかしていなければそりゃあ不利に決まっています。書記有利説は一理あると思います。メモを取りつつ、ときどきそのメモを元に議論をまとめ直すことができれば確かに有利。ただし、書記の学生で目立つのが、自分用にノートを取るだけ。GDで書記なのですから、ホワイトボードがあればそこに書く。特になければノートに書くにしても、他の学生にもわかるように大きく書く、くらいの工夫が必要です。
意外と知らない、GD開始前の必勝法3カ条
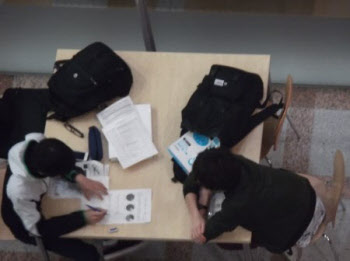
ここでGDの必勝法を読者に教えましょう。必勝法と言っても、コロンブスの卵みたいなもの。「なんだ、その程度か」と思うかもしれません。「その程度」が重要なのですよ、ええ。
さて、必勝法ですが、GD開始前に3点あります。
その1 受付時間ちょうどに会場に到着すること。受付時間ちょうどに行くと、GD開始まで余裕があります。他の学生が到着するたびに随時、自己紹介や雑談をしていくのです。そうすれば、どんな学生か、多少なりともお互いに理解することができます。その分、GDもスムーズに行きやすくなります。
その2 席は自由なら真ん中に座ること。企業側から指定されていれば別ですが、大体は自由なはず。その場合は端ではなく真ん中に座りましょう。特に議論慣れしていない人はここ、大事なポイントです。端の席だと声が届きにくく、しまいには議論参加をあきらめてしまうことがあります。その点、真ん中だと両サイドの話も聞きやすい、自分の話もしやすい、とメリットが大きい席なのです。
その3 用意したノートにテーブル地図を書きましょう。自己紹介のとき、どこに誰が座っているのか、聞きながらさっと書くと、名前で呼びかけられるので便利です。企業によっては、名札を用意するところもあります。が、名札があってもテーブル地図を書く習慣があればそれだけ話しやすくなるはず。
以上3点、誰でもできる話でしょう。が、この3点、やっていない学生がほとんどです。開始前から準備をしていれば、それだけGDは円滑に行きますので試してみてください。
うまく話せない学生の逆転3策とは?
ここからは個別の対応策です。まずは、うまく話せない学生から。GDは慣れの部分も大きいので、模擬GDなどに積極的に参加するのが一番です。とは言え、目の前にGDが迫っているのであれば、次の3点を意識してコメントするようにしてください。
その1 前提条件に立ち返るコメント
GD慣れしている学生が2人以上いると、前提条件から外れて枝葉の部分で盛り上がることがよくあります。私が昨年、鹿児島大・長崎大などの内定学生が主催した就活イベントで模擬GDのファシリテーターを担当した際、こんなお題を出しました。
「あなたは企業の広報担当者です。8.6秒バズーカ(「ラッスンゴレライ」)と日本エレキテル連合(「ダメよー、ダメダメ」)のどちらかを必ずCMに起用することになりました。どちらを選びますか? その理由をまとめなさい(両方起用しない、という回答はNG/どの企業かは自由/20分)」
どちらもやや旬の過ぎたコンビです。それからどんな企業かは自由。すると、案の定と言いますか、企業をどこにするのか、盛り上がるグループが続出しました。確かにちょっと想像しても、携帯電話会社がいいのか、食品メーカーがいいか、考えだしたら盛り上がります。
ところが、ここであるグループの口下手なタイプの男子学生が一言。「えっと、お題はどちらのグループを選ぶか、その理由をまとめる、とあるので、その話を中心にした方がいいのだけれど」。これが前提条件に立ち返るコメントです。
その2 時間を気にすること
タイムキーパーでなくても、時間をちょこちょこ気にして、「もう10分、過ぎました」「残り5分なのでそろそろ意見をまとめませんか」という程度のコメントでも印象はかなり変わります。もちろん、時間のコメントだけでは判断不能ですが、コメント数を増やす手法としては有効です。
その3 わからなければ質問していくこと
テーマがわからない、あるいは議論が高度になりすぎている場合、黙っているよりも、「ちょっとわからないので教えてほしい」と聞いてみてください。恥ずかしいと思うかもしれません。が、この一言で議論が締まり、前提条件に回帰できた、ということがよくあります。
GD慣れしている学生が落ちないための3カ条

次にGD慣れしている学生について。GD慣れしている学生が注意すべきはGDそのものではありません。そこは慣れているので、気にしなくてもいいはず。注意すべきは、まとめ、配慮、メモの3点。
その1 まとめ
まとめとは、結論を出そうか、というときに自身の教養や経験などから自分が正しい、と思うことにこだわりすぎるかどうかです。そうしたこだわりは確かに重要です。でも、GDはやはり結論を出すのが最優先。もし、正しい内容だったとしても、少数意見だったときは取り下げる、両論併記にするなどの工夫が必要です。意見が対立するのはGDでは構いません。ただ、最後はまとまれるかどうか。そこが重要です。
その2 配慮
GD慣れしている学生が2人以上いると、それだけで何となく盛り上がってしまいます。しかし、問題はGD慣れしていない他の学生。コメントしない学生が悪い、とも言えますが、慣れているのであれば彼らにも配慮しましょう。話を振る、意見を引き出すなどパスを出してあげるとそれだけ評価ポイントが上がります。
その3 メモ
書記であってもそうでなくてもメモは取りましょう。もし、書記が機能不全状態なら、途中からでも書記になったつもりでメモを他の学生にもわかりやすく書いてみてください。それと、他のグループの発表も合わせて聞く場合はその発表内容もメモしておきましょう。観察していると単に聞いているだけ、という学生がほとんど。最後に、「では、他のグループの発表を聞いてどう思ったか、感想を」など、フェイント質問が入ることがあります。かくのごとく、不確定要素の大きいGD、さて皆さんはどう乗り切るでしょうか。
1975年札幌市生まれ。東洋大学社会学部卒。2003年から大学ジャーナリストとして活動開始。当初は大学・教育関連の書籍・記事だけだったが、出入りしていた週刊誌編集部から「就活もやれ」と言われて、それが10年以上続くのだから人生わからない。著書に『キレイゴトぬきの就活論』(新潮新書)、『女子学生はなぜ就活で騙されるのか』(朝日新書)など多数。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。













