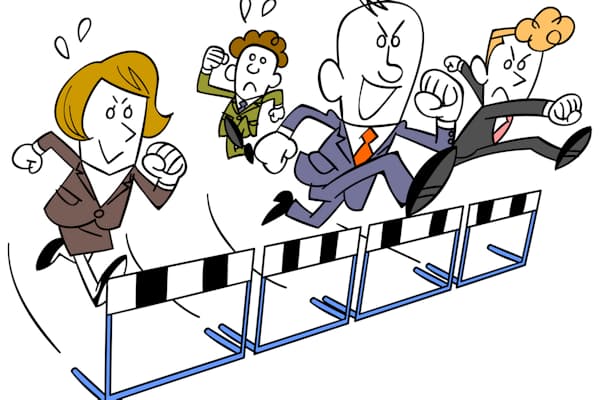マーケティング無用が新政流 反骨の志で変えた酒造り
佐藤祐輔 新政酒造社長(下)

新政酒造の佐藤祐輔社長はジャーナリストから転じた異色の経歴を持つ
人気の日本酒「新政」を造る新政酒造の8代目当主・社長である佐藤祐輔氏(43)は東京大学文学部を卒業後、反骨の社会派ジャーナリストとして活躍した。だが、偶然出合った日本酒の味わいに衝撃を受け、家業を継ぐことを決意。反骨精神は酒造りにもふんだんに生かされている。(前回の記事は「『ダメ人間』だからできた? 東大卒が醸す銘酒新政」)
小説家を目指し、東大卒業後も定職には就かず、家庭教師、郵便局員などと、職を転々とした。葬儀会社でも働いた。葬儀会社や郵便局の夜間の仕事はかなり実入りがよく、経済的には自立できていた。
全国紙の編集局長まで務めた元新聞記者と出会い、交流を続けるうち、ジャーナリズムの世界に興味を抱く。フリージャーナリストになり、先輩記者に手ほどきを受けながら、ブラック企業を告発したり、食品の安全性を検証したりする記事を、メジャーな雑誌に書き始めた。
「僕はもともと反体制派。だから、ビートルズをはじめとするロック音楽にはまったのも、大学時代に反体制的な文学作品に共感したのも、ジャーナリストとして社会問題に取り組んだのも、僕にとっては全て一緒。たとえば、今でも原発反対とはっきり言っている。商売に影響するから、そんなことは言うべきではないと言われることもあるが、商売より大切なものもあるので、僕は気にしない」
「ジャーナリスト時代は僕にとって青春だった」。ジャーナリスト仲間と議論を戦わせ、企業への潜入ルポを敢行するなど、危険な橋も何度となく渡った。「使命感もあったが、目的意識だけでは続かなかったと思う。仕事に夢中になれたのは、仕事が純粋に楽しかったから。それは現在の日本酒造りにも当てはまる」と佐藤氏は振り返る。
日本酒の味を知らなかった
ジャーナリスト仲間の飲み会があり、ある先輩が持参した日本酒を飲ませてくれた。それは静岡の銘酒「磯自慢」だったが、佐藤氏はそのおいしさに衝撃を受け、思わず「これは日本酒ですか」と聞き返したという。歴史ある酒蔵に生まれながら、それまでまともに日本酒を飲んだことがなかったのだ。
磯自慢を飲んだ瞬間、好きなことにはとことんはまる性格にスイッチが入った。たまたま農業関係の取材をしていて、農業分野に関心を持ち始めた時期だった。ジャーナリストとして日本酒を得意分野に加えるのも悪くない。そう考えた佐藤氏は、日本酒について猛烈に勉強し始めると同時に、地酒で有名な東京都内の酒店を回り、財布が許す限り日本酒を買いまくった。
さらに、いずれ日本酒について本を書くならもっと詳しくなる必要があると感じていた佐藤氏は、旧大蔵省醸造試験所の流れを組む酒類総合研究所(広島県東広島市)が開く業界関係者向けの連続セミナーにも通い始める。ジャーナリストとしての仕事が減るのも覚悟のうえで、東京から広島に移り住んだ。専門的な勉強を続けるにつれ、気持ちが徐々に「酒造り」へと傾いていった。