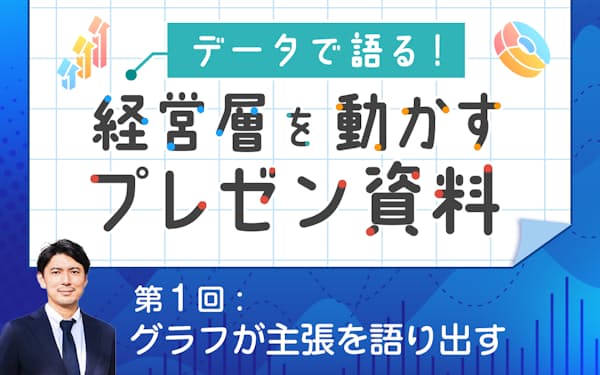「西海」でタイムトラベル 長崎・北西部の歴史遺産

長崎県の北西部の西海市とその周辺は、古くからヨーロッパとの懸け橋となった地域。キリシタンに由来する文化遺産と日本の近代化を支えた遺構が残る。対馬海流が育んだ豊かな海の幸も楽しみに、この春、出かけてみたい。
◇ ◇ ◇
遠藤周作「沈黙」の舞台
2017年公開のマーティン・スコセッシ監督の映画「沈黙」は、遠藤周作の同名小説の映画化だ。江戸初期の日本におけるキリシタン弾圧を描いた作品だ。
舞台は長崎市の北に位置する西彼杵(にしそのぎ)半島。同半島は、1500年代に南蛮船が来航して以来、ヨーロッパに開かれてきた。信者たちが建てた教会が今も残るほか、ローマ法王にも謁見した天正遣欧少年使節団の一人、中浦ジュリアン出生の地として、波乱の生涯を記念する中浦ジュリアン記念公園もある。
さらに、明治末期から昭和まで石炭採掘で栄えた崎戸、松島、大島もあり、日本近代化の過程で大きな役割を果たした。特に、キリシタン史跡が集中しているのが、外海(そとめ)と呼ばれる西岸の出津(しつ)地区。「出津文化村」と称される地区の歴史は、1879年に赴任し、この地に生涯をささげたフランス人、ド・ロ神父抜きには語れない。

出津文化村の中心にあるのは旧出津救助院。地元の自然石を積み重ねた丈夫な塀を持つ、木骨レンガ造りの力強い洋風建築だ。
神父が赴任した当時、海難事故や病気で一家の働き手を失い、貧困に苦しむ女性は少なくなかった。「そうした人々の自立支援のために建てたのが、この施設。授産場であると同時に製麺、製糸工場を兼ね、女性たちに仕事を教えた。近隣には神父自ら開墾した農園もある」と、建物を管理する修道会のシスター。
外海には、小説「沈黙」が縁となり、この地に建てられた遠藤周作文学館もあり、海岸線一帯は夕日の名所としても知られている。
車で東の大村湾側へと回ると、海景が一変する。東シナ海につながる茫洋たる五島灘がどこか異国を連想させるとすれば、対照的に大村湾はどこまでも穏やかだ。
この大村湾の景色にほれ込んで、終の住み家「邦久庵」を造ったのが94歳の建築家、池田武邦さん。小さな岬の海岸線にせり出すように立つのは、伝統的な茅ぶき屋根の家。自然との共生、技術の伝承を主眼に、地場材を使い、くぎを1本も使わずに建てたという。
海辺の木造建築は、湿気や塩分で傷みやすいが、湖のように穏やかな内海だからこそ実現した「日本でここしかできない木造建築」(池田さん)だという。
プリップリ、新鮮な魚介類
西海市は、海と里山に恵まれた土地柄だ。西岸の五島灘は、黒潮から分岐した対馬海流が流れ込み、潮目の変化に富む海域。速い流れで鍛えられた、身の締まった多種多彩な魚介類が水揚げされる。それを存分に味わえるのが、小さな島宿「オーベルジュあかだま」だ。
地元漁師から直接買いつけた地魚をぜいたくに使った料理の人気は高く、早めに予約をすれば昼食時のみの利用もできる。
前菜に続きカルパッチョが出された頃には、予約が取りづらい理由に納得していた。この1皿だけでもヒラス、アコウ、イサキ、イセエビ、サザエなど10種の魚介類が盛り込まれている。すべてに一手間かけられ、食材の上質さ、ソースとの相性が光る。ここでしか味わえない皿の数々に魅了された。
この日の宿、大島に立つ「オリーブベイホテル」へ。入り江に面したロケーション、外光降り注ぐ館内は開放感があり、隈研吾さん設計の建築と自然とが融合。客室には湾を望むガラス張りの浴槽がしつらえられ、入浴しながら眺望を楽しめる。
夕食は地物の水産品を中心にした構成。2月初旬~5月は地元で栽培される、フルーツトマトに似た「大島トマト」も旬を迎えるという。

翌日は、宿から車で40分ほど走った森の中に立つ「音浴博物館」に足を延ばした。レコードや音響機器を集めた個人コレクターの思いを受け継ぐ館内には、演歌からポップス、洋楽までのレコード、歴代の音響機器が並ぶ。運営責任者、高島正和さんの説明も楽しく、昭和にタイムトリップして過ごした。時を超えて遊ぶ。こんな旅もまたぜいたくではないだろうか。
(日経おとなのOFF3月号より再構成 文・飯田 敏子 写真・松隈 直樹)
[日本経済新聞夕刊2018年3月10日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。