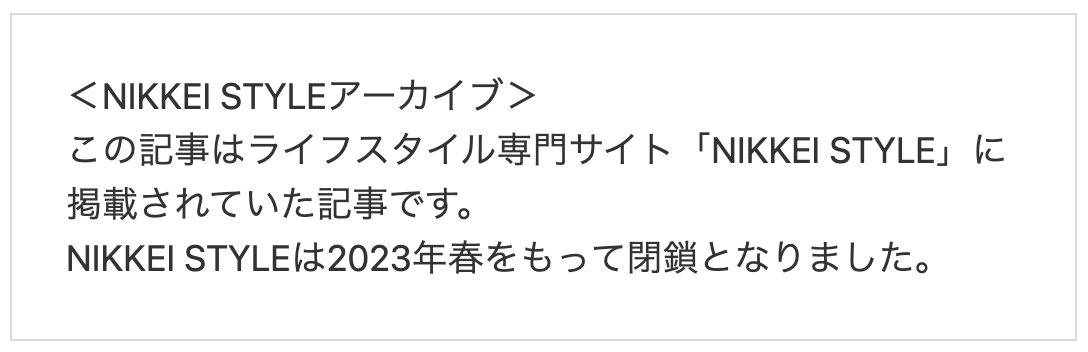採用にもAI活用 書類・面接で見えぬ人材を発掘

企業の採用に人工知能(AI)を使う動きが出てきました。採用した人材が期待した働きをしてくれない。せっかく採用した若者が「思っていたのと違った」と辞めてしまう。こんなミスマッチを解消する狙いです。
教育支援ベンチャーのIGS(東京)はAIを活用して性格や行動特性を診断するアプリを開発しました。採用に応募した学生にスマートフォン上で自分の考え方や行動パターンに近い選択肢を選んでいってもらうと、創造性や決断力、論理的思考、課題設定といった項目ごとに特性を数値化します。友人ら数名にも応募者を評価してもらい、スコアに反映します。
エントリーシートや面接では応募者のウソを見抜くことは容易ではありません。面接のテクニックを指南する本やサイトも氾濫しています。企業側も「創造力やコミュニケーション力のある人を」といいながら、実際には学歴に依存しがちです。
IGSのAIは過去のデータから学習し、自己評価や友人らからの評価の中から甘すぎるものや厳しすぎるものを見つけ、スコアを補正します。現在、働いている人のデータと合わせることで、採用担当者はどんな応募者が入社後に活躍できそうなのかを見ることもできます。
全日本空輸(ANA)では2017年のインターンの選考でアプリを利用したところ、書類では分からなかった創造性の高い人がみつかりました。そこで18年卒の事務職の採用でもこれを利用しています。「書類選考担当者が気づかない見方を取り入れたい」(広報担当者)
AI活用は他にも広がっています。ソフトバンクは米IBMの「ワトソン」を使ってエントリーシートを評価。インターネット広告のセプテーニ・ホールディングスは選考過程で得たデータをAIで評価し、入社後に活躍できるか予測しています。
近い将来、AIが採用を決める時代も来るのでしょうか。
今のところ、どの企業も最終的には人が判断すると強調しています。AIは過去のデータから学習するので、過去の誤った判断をそのまま評価に反映させてしまう恐れがあるためです。
米国では犯罪者の量刑や釈放の判断に過去のデータからはじく再犯危険度を活用していますが、米報道機関が追跡調査をしたところ、実際には再犯しなかったのに危険度が高いと評価されていた人の割合は黒人が白人よりも多かったそうです。採用にあてはめれば、例えば男女で偏見のある評価をしてしまうことも考えられます。
こうした公正性まで考慮したAIは「まだ研究段階」(産業技術総合研究所の神嶌敏弘主任研究員)というのが現状です。
神嶌敏弘・産業技術総合研究所主任研究員「属性無視でも不公平は起きる」
AIに公平な判断をさせるにはどんな課題があるのでしょうか。産業技術総合研究所の神嶌敏弘主任研究員に聞きました。
――コンピューターによる判断で公平性が問題となった事例はありますか。

「ラタニア・スウィーニー氏(米ハーバード大教授)の指摘を紹介します。情報検索サイトで人の名前を検索するときに、(検索連動広告に)『逮捕されました』といった文言がアフリカ系の名前には出やすかった。そこでヨーロッパ系の名前にしたところ、単に『我々は見つけました』といったあまり悪い印象の言葉ではなかった。アルゴリズムがなにか悪いことをしているのではなかろうかということで調べてみると、人種によって差別的な扱いをしていたということはなかった。検索する人が、アフリカ系の名前だと印象の悪い文章を表示したときにクリックしやすかったがために、そのデータにあわせて調整しているのでこのような差がついてしまった」
――アフリカ系やヨーロッパ系という属性を無視するアルゴリズムにすることで解決はしないのでしょうか。
「レッド・ライニングはご存じですか。昔、公民権運動があったときに、銀行は貸し出しをするかどうかを人種に依存して決めてはならないということを法令で定めました。ところが、銀行はどうしたかというと、住む地域によって貸し出すか貸し出さないかということを決めました。そして、貸し出さないと決めた地域にはアフリカ系の人がたくさん住んでいた。つまり、人種と関連のある情報を使ってしまうと、結果として差別的になってしまう。なぜレッド・ライニングというかというと、銀行がそういう地域を地図上で赤い線で囲んでいたからです」
――すべてのデータを入れた上で調整しなければならない。
「はい、情報を経由しても差別的にならないように、ということを考えなければいけません」
――公平なAIというのはうまくいきそうなのでしょうか。
「今まで不公平な状態かどうかということ自体が分からなかった。データ分析を適応することによって初めて明らかになったので、状況が悪くなったわけではないと考えています」
(久保田昌幸)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。