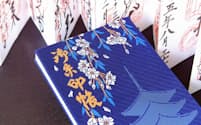リケジョが宮司 寂れた神社を復興させた現代の言霊力

過疎高齢化が進む地域で、2000年ともいわれる由緒がありながら寂れてしまっていた神社を復興させた女性宮司がいる。しかも大学では生物学を専攻したリケジョ(理系女子)……。こんな話を聞きつけ、奈良県御所市の「葛木御歳(かつらぎみとし)神社」の東川優子(うのかわゆうこ)宮司を訪ねました。
◇ ◇ ◇
葛木御歳神社は、平安時代に従一位を賜った由緒ある古社ですが、人の手が入らない状況が長く続いていました。十数年前までは、拝殿の床にコケが堆積し、摂社や社務所は壁が壊れ、屋根には穴が開いているという状況でした。
現在、神社の建物や瑞垣(みずがき)はきれいに修復され、途絶えていた祭事も復活し、多くの人が集まるようになりました。古くからの地元の氏子さんたちだけでなく、インターネットなどを介して縁ができた多くの人たちが共に神社を支える体制が実現したのです。

「葛木御歳神社の神域は、少なくとも1600年、おそらくは2000年の長きにわたって祈りの場であったと考えられています。この神社を、清浄な祈りと神祭りの場であると同時に、地域の方々が集って縁を結び合い、神様に奉納するエンターテインメントを皆で楽しむ場、いわば神社本来の形に戻したい。そして、神社を包む森の環境とともに1000年先まで伝えたいと考えています。賛同してくださる方を一人でも多く募り、このビジョンを実現させたいのです」
「次の1000年」を見据えた神社のビジョンを語る東川さん。ネットでの情報発信やクラウドファンディングを活用し、マーケッターとして抜群のセンスを発揮して復興を進めてきました。しかし彼女自身はもともと神社にゆかりはなく、神社の地元の出身でもありません。どのようにして現在に至ったのでしょうか。
経済苦の中で突然出会った「神様」
東川さんは大阪生まれ。父は会社経営者で、恵まれた環境に育ちました。「小さな頃からいつも学級委員に選ばれるタイプで、勉強も好きでした」という東川さん。行動力と好奇心にあふれた優等生でしたが、「自分はこんなに頭でっかちのままでいいのだろうか、という不安はどこかに抱えていました」と話します。そんな彼女に「豪快で明るい父は、いつも『思うように生きなさい』と言ってくれました」。
奈良女子大学では環境生物学を専攻。卒業後は、趣味だった陶芸に本格的に打ち込むため関東でしばらく暮らしましたが、力仕事がたたって体調を崩してしまいました。
2年ほどで大阪の実家に戻り、その後、紹介する人があって結婚。結婚によって移り住むことになったのが葛木御歳神社の近隣でした。
その後も何不自由ない暮らしを送っていましたが、40歳を超えた頃、大きな試練が訪れました。父が創業した企業が倒産し、その余波で自身も負債の返済に追われることになったのです。それまでの生活は一変。その後、夫とも離婚することになります。
「子どもを抱えて、家庭教師と塾の経営を掛け持ちして休みなく働きましたが、どうにもなりませんでした。子どもの足が大きくなっても、新しい学校用の上履きを買うことができない。ATMでお金を下ろそうとしたら残高は0円。スーパーで小銭しか入っていない財布を握りしめ、涙が止まらなかったこともあります」。そんな生活が1年以上も続いていて、普通の精神状態ではなかったかもしれない、といいます。
「気が付くと、神社の境内に立っていました。そして唐突に『この神社を継ごう。神社を再興しよう』と思ったのです。本殿の背後の森に入っていくと、例えようもない優しさで神さまが迎えてくださる気配をありありと感じました。たおやかな女神様と、りんとした男神様が『よう来たな。待ってたんよ』と降りていらしたようなイメージでした。その場にひれ伏したいような気持になり、涙がボロボロこぼれました。とにかく、この神社の再興を自分の生きがいにしたい、と思いました」
決意してからは、持ち前の行動力で突き進みました。当時の宮司は公務員と兼務しており、後継者はいませんでした。思いを打ち明けて宮司から許しを得ると、皇学館大学の神職講習会を受講し、宮司になるための資格を取得。相変わらず借金の返済に追われ、余裕はなかったものの、学費を払う段になると不思議と「お金が降ってくるように」援助があったりして、勉強を続けることができたといいます。

ネットは現代の「言霊(ことだま)」ツール
神職として活動を始めた東川さんは、「どうぞ気軽に神社に足を運んでください」と、懸命に地域の方々に呼び掛けました。しかし、一度は途切れかけていた関係を、地域の慣習も知らない新参者の女性神職が修復することは容易ではありません。春秋の祭りの参加者はわずか数人、参拝者も数えるほどという状況が1年ほど続き、東川さんは悩みました。
まずは多くの方々にこの神社の由緒を知ってもらおうと、2004年からインターネット上で発信を始めました。神社のホームページに加えてブログを立ち上げ、神道の話や神社の行事、神社の1000年先を見据えたビジョンのこと、保護したムササビの話などを日記のようにつづりました。
神社好きが集まるネットの掲示板に「手水が枯れているので水が流れるようにしたい」「山道の整備をしたい」「秋祭を開催します」などと書き込むと、各地から人が集まって作業をボランティアで手伝ってくれるようになり、地域外からのお祭りの参加者も徐々に増えてきました。
「神道には、言葉に宿る霊力によって現実がもたらされるという言霊信仰があります。祈りの言葉を口にすることで、困難なことを実現できる方向に持っていくのです。インターネットは、会ったこともない人に対しても言霊の力を発揮できるすばらしいツールです。過疎化が進み、交通の便も悪いこの地から世界中に情報を発信し、協力者を求めることができるのですから、使わない手はありません。改めて、すごい時代だと思います」
クラウドファンディングでカフェサロンを実現
ネットで神社の情報を広く発信する傍ら、東川さんが悩んでいたのは地元の支援者の獲得でした。地域に根差した存在とならなければ、神社を1000年先まで伝えることはできません。
「私はこの葛城の生まれではありません。また、ネットを通じて集まった人々の多くは、葛城以外の地から来た人たちです。この歴史ある地で生まれ育った氏子さんの中には、神社をよそ者に取られたように感じる方もいらっしゃったかもしれません。でも、絶望せずに根気よく道を探れば、状況はきっと変わる。間違ったら神様が止めてくださる。そう信じて進みました」
東川さんがそこで考えたのは、人を集めるためのさまざまな催しでした。
「楽しみや感動には人を呼び寄せる力があり、神様もにぎやかなことをお喜びになります。皆でわいわいと集まり、楽しみながら、少しずつ山を整備し、境内を整えるうちに、地域の方々もさまざまな形で協力してくださるようになりました」
09年には、神社を支える奉賛会として「崇敬会」を立ち上げ、月次祭(つきなみさい)を復活しました。境内に玉砂利を敷き、70年ぶりに御田祭(おんだまつり)を復活。境内を抱く森と山の整備に協力する「おとしだまの森倶楽部」も発足しました。同年12月には前宮司が引退、東川さんは宮司に就任しました。
稲の神である御歳神を祭る葛木御歳神社にとって、その年の五穀豊穣を祈る「祈年祭」は最も重要な行事であるはずですが、開催は途切れていました。これも復活させました。
「神社の古文書の多くは失われていたので、途切れていた祭事を復活するためには前宮司に伺うほか、村史を調べ、近隣の神社のケースを検証し、先生方や村のお年寄りにもお話を伺いました。大学で習ったこと以外ほとんど知識のない私に、どの方も丁寧にお話を聞かせてくださいました」
10年に開催された「平城京遷都1300年祭」では、県からイベント開催の依頼を受け、崇敬会、おとしだまの森倶楽部、氏子さん、市役所の担当者で構成する「実行委員会」を立ち上げました。会合を重ね、腹を割って話すうちに、氏子さんと地域の外から集う若者たちは打ち解け、両者の関係は劇的に変化しました。イベントは大成功し、ばらばらだった車の両輪が支え合い、そろって走るようになったのです。以降、拝殿の階段補修、摂社の改修と遷座祭、2度目の瑞垣(みずがき)の修復などが進み、一連の「平成の大修理」は14年に終わりました。神戸のボランティアが手水を流してから10年目のことでした。

続いて東川さんは、神社のあるべき姿として描いている「地域の方々が集って縁を結び合う交流の場、神様に奉納するエンターテインメントを皆で楽しむハレの場」として、カフェ兼サロンの開店を思いつきました。
建物の改装資金の捻出方法として選んだのはクラウドファンディング。目標の100万円を超える金額が集まり、15年6月に「サロン&カフェ みとしの森」を神社のすぐ隣に開店しました。予約制で、カフェレストランの運営から調理、サービスに至るまで、料理好きの東川さんが一人でこなしています。ここでミニコンサートやミニ上映会、古事記や古代史の勉強会、さまざまなワークショップなどを開催。宮司としての拠点と、地域の文化発信地としての役割も果たしています。
「人は受け継がれる歴史の一瞬」
40歳を過ぎてから、宗教者という予想もしない人生を歩むことになった東川さん。今後の目標をお聞きすると「これまで、しんどい思いをたくさんしてきましたので、今しんどさの最中にいる方に何かしらの助けになれれば、というのが今後の一番の目標であり、望みです」との答えが返ってきました。
「私は生物学を学んでいましたが、『生物はDNA(遺伝子)の乗り物』といった生物学の概念には、驚くほど神道と通じるものがあるんですよ」。東川さんはこう言います。
神道では、人間は神様の御霊(みたま)の一部である清らかな「分け御霊」を根本の魂として抱えて生まれてくると考えます。つまり、人は「分け御霊の器」なのです。そして人生を終えると、人は等しく祖霊となります。世代を超越して連綿と受け継がれていく点で、分け御霊と生物のDNAは似ているといいます。
さらに、神道で大切なのは「中今(なかいま)」と呼ばれる現世。「神道には、輪廻転生も原罪も最後の審判もありません。約束の地や天国、解脱のような最終的な目的地や目的もありません。現世を清く、正しく、明るく生きることが、何より神様のお心にかなうのです」。人生の目的に迷ったり、あるいは目標を達成できず挫折したりしてもそのために悩む必要はないといいます。「分け御霊を抱え、そこまで歩んできた道は確かに自分が生きた証。後は、同様に分け御霊を抱えた次の人に託せばよいのです。私たちも誰かの後を継いで、ここまで来たのですから」
限りなく続いていく歴史の一コマにすぎない自分の「中今」を楽しみながら精一杯明るく生きればいい。「絶望せずに根気よく方法を探せば、必ず助けは来ると経験から学びました。今しんどいと感じている人にそう伝えることができれば」と東川さんはほほ笑みます。
(ライター 木暮真理)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。