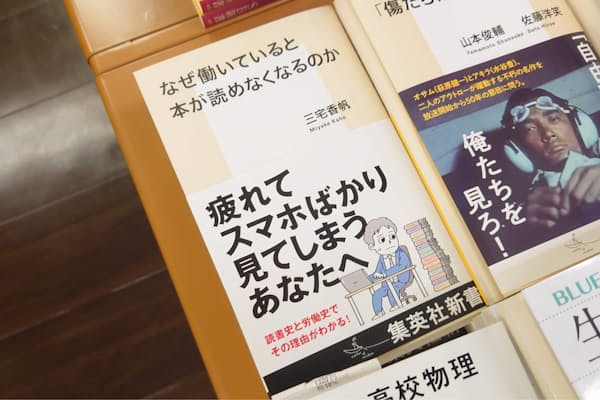医学部合格者数が日本一 東海中高、実は個性派ぞろい
東海中学・高校校長の林道隆氏に聞く

名古屋市の東海高校・中学
中京圏の名門私立男子校、東海中学校・高等学校(名古屋市)。国公立大学医学部合格者数は10年連続日本一という医師輩出校だ。東京大学や京都大学などにも多くの生徒が進学し、さまざまな分野で活躍する個性豊かなOBが少なくない。キラリと光るユニークな個性はどのように育まれるのか。名古屋の東海を訪ねた。
仏教系学校
あれ、お坊さん? 校長室に入ると、林道隆校長がニコニコと優しい笑顔で出迎えてくれた。スーツの上から輪袈裟を提げ、左手には数珠を巻いている。実は、東海はもともと、浄土宗寺院の子弟のために全国に建てられた学校の一つ。歴代の校長も、林校長を含めて全員がお坊さんだ。
その林校長の案内で校内を歩いた。訪れた日はちょうど試験期間中で通常の授業はなく、生徒の姿はまばら。ときどき、騒がしい中学生の集団とすれ違う。「高校生だともう少し落ち着いているんですけどね」と林校長も苦笑い。全国有数の進学校といっても、見た限りはごく普通の学校だ。
最初に向かったのは、東海の象徴である「明照殿」。重厚な扉を開けると、正面にまつられた阿弥陀仏が目に飛び込んできた。この場所で、中学生は毎週、「宗教」の授業を受ける。
宗教といっても範囲は広い。中1では仏教の基礎知識を教えるが、中2、中3になると、再生医療や臓器移植など生命倫理に絡む問題や、原爆やホロコーストといった戦争と平和の問題など、幅広いテーマを取り上げる。林校長は、「よりよく生きるためには、いろいろなことに関して自分で考える力を身に付けることが大切」と授業の目的を説明する。
この「宗教」を除けば、授業のカリキュラムに関して他の進学校と大きく違う点は特にない。林校長は、「医学部合格者数が多いので、医学部合格用の特別なカリキュラムがあるのかとよく聞かれるが、そんなものはありません」と笑う。
8割は理系
医学部合格者数が多い理由をあえて探すと、まず、もともと生徒数が1学年440人と多い上、年によっては全体の約8割ぐらいが理系を選択するという進路選択の傾向がある。加えて、最近は進学実績が広く知られるようになり、「医学部を受けるなら東海へ、という流れも出てきた」(林校長)。
もう一つあるとすれば、生徒の習熟度に合わせたクラス編成だろう。具体的には、高2の時に、それまでの成績を基に習熟度の高い生徒を集めたA群と残りのB群にグループ分け、それぞれのグループに合った授業を行う。医学部や難関大学を受けるのは、だいたいA群の生徒だ。
ただ、学校側は、習熟度別のクラス編成はあくまで生徒の授業内容への理解度を深めるための措置で、大学合格の実績づくりのためではないことを強調している。