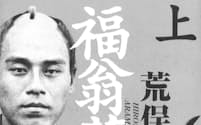「坂の上の松山」 司馬遼太郎ゆかりの地を行く(下)

「竜馬がゆく」「坂の上の雲」などのミリオンセラー作家、司馬遼太郎。亡くなって20年以上になるが、いまだに「司馬文学」の人気は衰えを知らない。司馬遼太郎のゆかりの姫路、松山を訪ねた。
友にもつなら黒田官兵衛
「司馬遼太郎」の名を最初に冠した本格的な施設は姫路文学館の「司馬遼太郎記念室」だ。96年5月にオープンした。本人は大阪の生まれだが戦国時代から祖父の代までそのルーツは「播州」にあった。姫路出身の人間国宝・桂米朝らとの長く深い親交も影響したかもしれない。姫路文学館も安藤忠雄氏の設計による。JR姫路駅からはバスなどで6分ほどの距離だ

司馬遼太郎記念室は戦国武将、黒田官兵衛(如水)を描いた「播磨灘物語」を中心にした文学施設。常設展では官兵衛と主君の豊臣(羽柴)秀吉が活躍した「播磨灘物語」の舞台や姫路との関わりなどを豊富な資料で紹介している。
官兵衛はあとがきに「友をもつなら、こういう男を持ちたい」とまで司馬遼太郎がほれ込んだ、爽やかで人にやさしい性格の主役でもある。「播磨灘物語」だけではなく長編「関ヶ原」でも最後のシーンで官兵衛は登場する。敗亡した石田三成を好意的に語り「如水、翌日、京を去った」のひと言でこちらの小説は終わる。
玉田克宏・姫路文学館学芸課長は、ある時官兵衛の小説をまとめて読んだことがあるという。「老練な軍師の『黒田如水』を無欲な青年の『黒田官兵衛』に変えたのが司馬遼太郎の『播磨灘物語』」と指摘する。生誕日の8月7日を「司馬遼太郎メモリアル・デー」とし毎年イベントを開催、県外からも多くのファンが集まる。
月1回の読書会には日ごろ時代小説に縁の無さそうな研究者やエンジニアなど理数系の読者が多いのも特徴だという。底流に一貫して流れる明るい合理主義になじみ易いのかもしれない。
秀吉 播州から天下とり
展示コーナーには最晩年、開設準備大詰めの最中に書いてもらった「思邪無(思いよこしま無し)」の書が公開してある。直筆の原稿用紙は色鉛筆を駆使して油絵のキャンパスのようになっており、いかにも才気煥発、知識とアイデアがあふれ出てくるようなイメージだ。ところが書の方はたっぷりと墨を含ませ、ゆっくり真っ直ぐに下ろしていった筆運び。やや無骨なまでに男っぽい書風だった。

姫路市ではやはり姫路城を見てみたい。法隆寺とともに真っ先に世界遺産に認定され、国宝の城でもある。「播磨灘物語」では城主の官兵衛が秀吉にさっと姫路城を譲るシーンが描かれる。官兵衛が活躍する舞台を播州から「天下」へ飛躍させるきっかけともなった。現在の姫路城は「平成の大改修」を終え、シンボルの天守閣にも落ち着いた風合いが出てきている。JR姫路駅から徒歩10分ほどだが、新幹線の窓から見てもそれとわかる巨大な平山城だ。天守閣までくまなくみて回るには2時間ほどみておきたい。
子規、秋山兄弟が生まれた松山

松山市の「坂の上の雲ミュージアム」は今年で10周年を迎えた。その名の通り司馬作品の代表作のひとつ、「坂の上の雲」の世界をテーマにしている。明治期の日本を舞台にし、「まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている」で始まる書き出しは最も知られた一節だろう。秋山好古・秋山真之・正岡子規の3人の主人公は松山の出身で同市の街づくりに生かそうというユニークな試みを続けている。
坂の上の雲ミュージアムはJR松山駅から市内電車で約10分。地上4階地下1階建てで、やはり安藤忠雄氏が設計した。2階から4階まで三角形を描くスロープ上に沿っていくつもの展示室を回遊していく構成で、好古・真之・子規の3人の主役をイメージしたのかもしれない。4年3カ月間連載した新聞の切り抜き、1296回分が壁一面に張り巡らされ、秋山兄弟の手紙など直筆資料の展示も多い。
三角形の順路を巡っているうちに、フィクションの小説世界とノンフィクションの近代日本史が頭の中で渾然(こんぜん)一体となってくる。現在は企画展「好古・真之・子規-明治20年代初頭」を来年2月まで開催中だ。資料や写真約130点を公開している。石丸耕一学芸員は「国家としては憲法制定、さらに好古のフランス留学、真之の海軍兵学校入学、正岡は『子規』の俳号を使い始めるなど節目の時代にあたる」と解説する。
松山市には見どころが多い。ミュージアムから徒歩5分の場所には「秋山兄弟生誕地」がある。残された写真や関係者の証言などから兄弟の生家を復元し秋山兄弟の関係資料などを展示している。兄弟の銅像もある。約10分のビデオテープで子孫の方の貴重な証言を聞くことができる。
司馬作品、ベスト5は

「子規堂」は伊予鉄道・松山市駅から徒歩5分。子規の生い立ちの家の勉強部屋を復元し、遺品などが展示されている。もともと司馬遼太郎は正岡子規への関心が深く、松山市を取材しているうちに「坂の上の雲」の構想を思い立ったという。
小谷野氏は「司馬遼太郎の文章はやはりうまい」と話す。学校の授業では苦手だった日本史の概略を簡明な司馬作品で知ったという読者も多いだろう。しかし自らも2度芥川賞候補にのぼった小谷野氏は「司馬作品の本当の面白さは、実は創作したフィクションの部分にある」という。資料の多さに束縛されたりすることがないからだ。
小谷野氏が選ぶベスト5は(1)菜の花の沖(2)花神(3)胡蝶の夢(4)国盗り物語(5)箱根の坂――としている。この8月には「関ヶ原」の映画化も上映される。皆さんのベスト5はどの作品だろうか。
(松本治人)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。