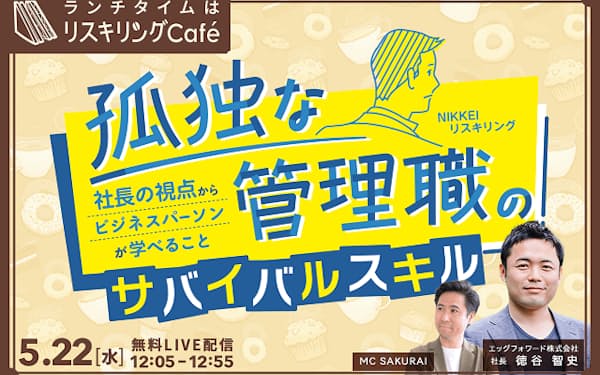ママがフリーに 子育てと仕事両立、もう一つの選択肢
スキルで連携 大きな仕事

2月上旬、東京都世田谷区が持つ施設の管理・運営をする世田谷サービス公社の会議室。従業員の多様な働き方に対応した人事制度づくりの議論が熱を帯びていた。議論をリードするのは、人材育成のコンサルティング会社、アビライト(東京・港)の安部博枝社長(49)と、同社と契約を結びフリーで働く黒田江身子さん(46)だ。

アビライトは3人のコア社員以外は専門性の高い社外スタッフと契約。大半がフリーで働く母親で、黒田さんもその一人。かつては大手自動車メーカーの開発部門に勤務していた。現在4歳になる長女が生まれた時は自動車メーカーの短時間勤務や在宅ワークを組み合わせて仕事をしてきた。仕事と育児を両立させるための制度は整っていたが使いづらい面もあった。
当時は在宅ワークは通常の勤務時間内に働くことが前提で、子どもを寝かしつけてからの仕事は深夜労働になるとして正式には認められなかった。「子育て時期は、もっと柔軟な働き方があるのではないか」。黒田さんはそう痛感し、フリーになる決断をした。
「出産などでいったん退職すると企業への再就職は難しい」。こう指摘するのは、アビライトの安部社長。自身も企業を退職後に、2人の子育てをしながら様々な雇用形態を体験してきた。退職した女性のなかで能力が高い人が数多くいることを実感。アビライトでは面談などを通じスキルの高い女性と契約し「プロジェクト管理から経営コンサルまで重要な仕事を任せている」という。
「企業時代と同様の賃金水準で仕事ができる」。こう語るのは、フリーでリサーチなどの仕事をこなす水間玲子さん(40)だ。IT(情報技術)企業を経て監査法人で企業の社会的責任(CSR)のコンサルティングをしていた5年前に出産。その後、短時間勤務になると重要な仕事に携われなくなることに焦燥感を覚えた。「このまま仕事を続けていては、どっちつかずではないか」と思い、ベンチャー支援の企業に転職。起業の過程や多様な働き方を知り、その上でフリーという働き方を選んだ。
現在は、総合職経験のあるフリーの女性を中心に3500人が登録している人材紹介企業、Waris(東京・港)などから仕事の紹介を受ける。Warisが仲介する仕事の時間単価は3000~6000円。大手企業と比べても遜色ない収入を実現できるのは、「総合職で10~15年働いた経験を持つ女性の高いスキルを結集することで、専門性を要する高単価の仕事が成立する」(田中美和共同代表)からだ。
「フリーでも創造的な仕事ができる」。手応えを語るのは、3人の子どもを育てる小松紫穂里さん(33)だ。ウェブ制作会社で顧客の要望を聞くディレクターをしていたが、長時間勤務が当たり前だった。長女が生後10カ月のときに個人事業主となって、フリーとして企業からウェブの運用・管理の仕事を受け在宅でこなしたものの、「個人で受けられる仕事の量と質に限界がある」と感じていた。
現在は、SBヒューマンキャピタル(東京・港)の人材サービス事業の一つ「マムズラボ」などに参加している。マムズラボをまとめる佐藤にのさん(38)によると「企業が個人のフリーに外注する仕事は切り出しやすく単純なものが多い」。マムズラボではスキルの高い人材を集めチームとして企業から仕事を受注するので「企画段階から関わるような創造的な仕事もできている」(佐藤さん)。
新しい働き方に詳しいニッセイ基礎研究所専務理事の櫨浩一氏は、「いまの企業は、午前9時から午後5時まで働ける人たちを標準として作られた組織。子育てをしながら働く母親たちを標準にすれば、フリーランスで在宅勤務なども取り入れ、チームで仕事をする、という働き方になるのではないか」とみる。
「ITの進歩で一カ所に集まらなくても仕事ができるようになった。一方で団塊世代のリタイアが始まり空前の労働力不足になっている」(櫨氏)。2つの環境変化が重なって、母親たちの新しい働き方を後押ししている。
◇ ◇
広がり見せる外注分野
経済産業省の「雇用関係によらない働き方」に関する研究会が約200社を対象に実施した調査によると、フリーランスなど外部人材を活用している企業は2割弱。活用が多いのが「IT・情報システム」「各種コンサルタント」でともに25.6%だ。「新規事業開発、企画・広報、人事制度改革などは外部に委託できないと思っている企業が依然多い。しかし、フリーでもしっかり成果を出せることを積極的に売り込むことで、こうした分野でも外注が増えている」(Waris共同代表の田中氏)という。
フリーで働く人が増えた背景には、ネットで仕事を受注、在宅で仕事ができるクラウドソーシングなどの仕組みが広まったことも関係する。ただ、スキルが伴わない働き手がいたり、一部の企業が人件費を節約するために低単価で発注したりする問題もある。Warisなどでは、企業で働いた経験を持つ母親たちが「協業」することで、大きな仕事を受注し成果をあげている。「フリーの中でも新しい働き方が登場していることを社会で広く知ってもらい、企業とフリーの連携関係をもっと広げたい」(田中氏)という。
(相川浩之)
[日本経済新聞夕刊2017年3月8日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。