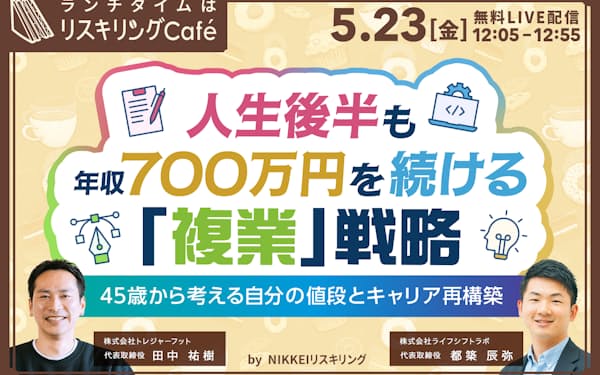世界の首脳をもてなすワイン 足利で醸す
主役は障害者、「ココ・ファーム・ワイナリー」

ワイン愛好家が一度は訪れたいワイナリーが、栃木県足利市の山の中にある。名前は「ココ・ファーム・ワイナリー」。2008年の北海道洞爺湖サミットや今年広島で行われた主要7カ国(G7)外相会合など、日本で開かれる重要な国際会議の舞台では、必ずと言っていいほどココ・ファームのワインが振る舞われる。そんな日本を代表するワインを造っているのは、個性あふれる元気な知的障害者たちだ。
■仕込みの秋 手作業が決め手
ココ・ファームを訪れたのは9月中旬。ブドウを収穫しワインの仕込みに入る秋は、ワイナリーにとって1年で最も忙しい季節だ。
倉庫のような大きな施設の中では、運び込まれたブドウの選果が行われていた。房の中から、熟し具合が足りなかったり潰れたりしている実を人の手で取り除く作業で、ワインの質を左右する重要な工程だ。ワイン造りは機械化が進むが、選果は依然、人手に頼るところがほとんどだ。選果を経た実は、機械で茎から切り離され、集められて発酵タンクに運ばれる。
この日、選果作業をしていたのは、ワイナリーの専従スタッフや海外からの研修生ら数人。両手を素早く動かし、実をより分けていた。そのかたわらで、空の箱を片づけたり、機械から吐き出された小枝の束を、大きなフォークですくって別のかごに移したりする作業をしていたのが、障害者たちだ。

「ブドウの入荷が多い時は、園生(えんせい)も選果作業をします。『自分の食べたい実だけ残してね』と指示すると、ものの見事によい実だけを残します」。こう話すのは、施設を案内してくれた池上峻さん(35)。池上さんは、ココ・ファームを開いた故・川田昇氏の孫にあたる。
池上さんが障害者たちを「園生」と呼ぶのは、ココ・ファームで働く知的障害者は全員、同じ敷地内にある知的障害者支援施設「こころみ学園」の入居者だからだ。同学園には現在、男女合わせて90人の知的障害者が暮らす。
ココ・ファームはもともと、こころみ学園の創設者である川田氏が、園生一人ひとりが生き生きと働ける場所をつくりたいと、1980年に設立。それ以前から、生食用のブドウを作っていたが、価格の変動が大きく収入が不安定だった。そこで、より安定収入が見込めるワイン造りに乗り出したというのが、ワイナリー開設の経緯だ。ココ・ファームの「ココ」は、こころみ学園の「ここ」から取った。
■ワインは畑で造られる
ココ・ファームが持つブドウ畑のうち、最も古い畑は、醸造施設やこころみ学園を見下ろす山の、平均斜度38度という急斜面に広がる。ここに、赤ワイン用品種のマスカット・ベリーAや白ワイン用品種のプティ・マンサンなどが、びっしりと植えられている。
「ワインは畑で造られる」という言葉がある。ワインはブドウのみを原料とするため、いかによいブドウを育てるかが、ワイン造りにおいて最も重要という意味だ。その重要な畑を管理するのも、園生の仕事だ。
60代のKさんは、毎日、徒歩で山の頂上まで行き、崖の上から缶をたたいて大きな音を立て、ブドウを狙うカラスを追い払うのが仕事。仕事熱心なあまり、注意していないと台風が来ていても山に上ってしまうのが玉に瑕(きず)だが、池上さんは「なぜか、他の人がやるとカラスが逃げない。気迫が違うのでしょうか」と笑う。Kさんに話しかけると、一瞬手を休めて、「カラスを追い払うのは面白い」と答えてくれた。

畑の中で、傷んだブドウの実を摘み取る仕事を黙々とこなすのは、40代のOさん。重度の自閉症で人との会話に難があるが、仕事は正確だ。「Oさんはすごい能力を持っているんです」と池上さん。聞けば、辞書を読むのが趣味で、難しい漢字もスラスラと書けるのだという。
夏場は、除草剤を散布する代わりに、畑作業が可能な園生総出で、畑の草刈りをする。雑草が伸びると湿気がたまり、ブドウにカビなどの病気が発生しやすくなるためだ。農薬をできる限り使わないブドウ栽培が世界のワイン造りの主流になりつつあるが、ココ・ファームで除草剤を使わないのは、使うと園生の仕事がなくなるから。しかし、それが結果的に、土壌の活力を維持し、高品質のワインを生む秘訣となっている。
■同情で買ってもらうワインはダメ
炎天下で急斜面を移動しながら手先を使う作業は、年齢的に若くはない知的障害者には、けっして楽ではない。だがそれも、川田氏の信念と障害者支援にかける情熱の反映だ。知的障害者はともすれば、かわいそうとの理由で過保護に扱われることもある。しかしそれは本人たちのためにならないと感じた川田氏は、あえて厳しい労働を課すことで、障害者に生きる喜びを与えようとしたのだ。

ワイン造りに関しても、池上さんは、「祖父は初めから、『同情から買ってもらえるようなワインは、しょせん、一度きりしか買ってもらえない。何度も買ってもらえるような本当においしいワインを目指す』と言っていました」と話す。
1989年には、カリフォルニアの有名ワイナリーで修行を重ねた米国人醸造家のブルース・ガットラヴ氏を招へいし、醸造責任者に据えた。世界最先端のワイン造りのノウハウを持ち込み、園生からは「ブルースさん」と慕われた同氏の20年以上にわたる貢献も、ココ・ファームにとっては大きな財産となっている。
こうして造られたココ・ファームのワインは、川田氏が望んだとおり多くのファンが付いた。田崎真也氏など著名ソムリエの目にとまり、サミットなどの大舞台でも、日本を代表するワインとしてお披露目されるようになった。日本航空の国際線ファーストクラスのワインリストには、現在、世界の偉大なワインと共にココ・ファームの白ワイン「月を待つ」が名を連ねている。
ココ・ファームのワインは、園生同様、個性にあふれている。たとえば、北海道洞爺湖サミットの夕食会で振る舞われた赤ワイン「風のルージュ」は、豊かな果実味と酸味のバランスがよく、肉料理にぴったり。人気のロゼワイン「こころぜ」は、フレッシュな果実の香りに加えてほのかな甘みも感じ、さまざまな料理と合わせやすい。
「素晴らしいワインには、必ず素晴らしい物語がある。それが他のお酒にはないワインの魅力です」。ワイン愛好家としても有名なある日本人の経営者は、私の取材にこう語ったことがある。
ココ・ファームのワインがこれだけ多くのワインファンを惹きつけるのは、こころみ学園の園生一人ひとりの物語がぎゅっとボトルに詰まっているからに違いない。取材の最後に、ワイナリーのテイスティングルームでグラスを傾けながら、ふとそんなことを考えた。
今この原稿を書きながら、池上さんのこんな一言を思い出している。「ときどき園生が、ワインをテイスティングしているお客さんを遠くから眺めていることがあるのですが、よく見ると、その表情が何となく誇らしげなんです」
◇ ◇ ◇
◆アクセス情報◆ 最寄駅はJR両毛線足利駅または東武伊勢崎線足利市駅。ワイナリーまでは、両駅からタクシーで約20分。ワイナリー内のワインショップは午前10時から午後6時まで営業。テイスティング(1人500円)は午後5時まで。現地で申し込めば、ワイナリー内の見学もできる(所要時間45分、1人500円)。詳しくはホームページ(http://cocowine.com/)を参照。
1964年栃木県生まれ。慶応義塾大学法学部卒。米コロンビア大学大学院(ジャーナリズム・スクール)修士課程修了。新聞記者を経てフリーに。日本ソムリエ協会認定シニアワインエキスパート。著書に『仕事ができる人はなぜワインにはまるのか』(幻冬舎新書)など。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。