携帯やロボット…もの供養で償い 消費社会に罪悪感
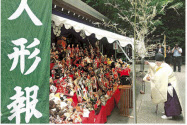
人や生き物ではなくモノを弔う「もの供養」。あらゆるものに魂が宿るという信仰心が背景にあるが、実は広まったのは戦後だ。人形からロボット、メガネ、携帯電話まで。日本特有の事情を探った。
4月26日、千葉県いすみ市の光福寺の祭壇にソニーの犬型ロボットAIBO(アイボ)約110台がずらりと並んだ。今年で6回目となるアイボの供養だ。これまで千台以上の修理を手掛けてきた元ソニーの技術者、乗松伸幸さんが社長を務めるA・FUN(習志野市)が主催している。
乗松さんは「修理」ではなく「治療」と言う。「部品としていわば『献体』してくれるオーナーも多い。アイボの魂をオーナーにお返しする儀式」と話す。
もの供養で圧倒的に多いのが人形だ。5月19日、東京都台東区の第六天榊神社で久月が開いた「人形報恩祭」。約300体の人形を前に横山久吉郎社長は「人形は家族の災いを背負ってくれる。感謝を込めたい」とあいさつした。
人形供養は平安の昔からある。しかし大きな行事となってきたのは戦後のこと。久月の供養も7回目だ。それでも毎年1割ずつ供養する人形は増えている。横山久俊専務は「人形を飾らない家庭が増え、役割を終えた人形が多くなっている」と分析する。
こうした供養は記念日に行うことが多い。ハサミの供養は8月3日の「ハサミの日」。メガネの供養は1001の形に似ていることから「メガネの日」である10月1日。目の神様として知られる葛城神社(徳島県鳴門市)には1998年に「めがね塚」が建立、毎年供養している。
供養の文化は日本特有だ。日本ケンタッキー・フライド・チキンは74年から毎年「チキン感謝祭」を開く。東は東伏見稲荷神社(東京都西東京市)、西は住吉大社(大阪市)だ。今年で45回目と古い。「世界中で展開しているが供養をするのは日本だけ」(広報部)という。
なぜこうした供養が広がっているのか。背景の1つが高齢化だ。新潟県最古といわれる古刹、国上寺(燕市)では、3年前から郵送で供養を受けている。山田光哲住職は「遺産整理で出てきたものの供養を依頼されることが増えた」と話す。手紙や手作り品、子供が大切にしていたヘルメットを託す母親もいる。

「みんなのお焚(た)き上げ」という供養代行サービスを昨年から始めたクラウドテン(東京・港)。同社の調査では98.6%の人が「供養したいものがある」と答えた。写真やレコードのほか、携帯電話も増えているという。山盛潤社長は背景に「丁寧に手放す精神だけでなく、ゴミとして捨てた時の罪悪感や『罰が当たりそう』という恐れの気持ちがある」と話す。
「メリーさんの電話」という都市伝説がある。少女が古くなった人形「メリー」を捨てる。その夜「あたしメリー。今ゴミ捨て場にいるの」と電話が。怖くなって切るが「今駅にいるの」「家の前にいるの」と電話の度に近づいてくる。そして最後。「今あなたの後ろにいるの」――。
国上寺の山田光哲住職は「本来仏教には罰当たりやたたりという考え方はない」と言う。宗教的な背景というよりはむしろ、戦後の大量消費社会の中で「ものを大切に」という現代的な教訓が、供養を広げた背景にあるようだ。
「お焚き上げ」という言葉の使い方も、時代とともに変わってきた。
「元カレをお焚き上げ」。ネットの恋愛相談サイトでは「失恋を克服して新しい恋に進むこと」をこう記す。文章を書く行為を自分を客観視するという意味で「お焚き上げの一歩」と表現する人もいる。供養やお焚き上げは「気持ちの整理をして前を向くための行為」(山田住職)だ。現代的ではあるが、案外適切な使い方なのかもしれない。
◇ ◇ ◇
共生の意味 問いかける

昆虫採集好きで知られる解剖学者の養老孟司さんが建てた「虫塚」が、神奈川県鎌倉市の建長寺にある。虫かごに見立てた外観は、建築家で新国立競技場の設計者、隈研吾さんのデザインだ。
「現代人はおびただしい数の虫を殺してきた。『命は大切だ』とよく言われるが、毎日何万匹の虫を車や電車で無意識にひき殺している。その加害者であることに自覚的であろうと思い、虫塚をつくった」と養老さんは言う。
日本人の「もの供養」好きは、「ものにも魂が宿る」という考え方に加え、「一緒に生きてきた仲間という意識がある。生き物は共生しないと絶えてしまう」と話す。もの供養は「共生の意味」を問いかけている。
(大久保潤)
[NIKKEIプラス1 2018年7月7日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界














