書簡の時代 アントワーヌ・コンパニョン著
手紙で繙く恩師バルトの記憶
ロラン・バルトの生誕100年にあたる2015年、フランスでは、哲学、文学、文化批評など、幅広い分野にわたる彼の思想と、その影響を顧みる催しや関連書籍の出版が数多く企画された。
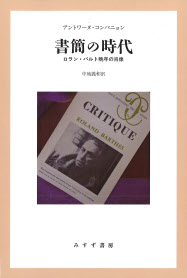
バルトの高弟として知られる著者も、バルト書簡集の編纂(へんさん)企画者から、師の手紙の譲渡を依頼される。40年ぶりにバルトの便りを繙(ひもと)きながら、20代だった自分と恩師との5年半の記憶を、彼の没した年齢に達した現在の視点で振り返り、初めて公的にまとめたのが本書である。
理系のエリートから文系に転向した著者をバルトは自分のセミナーに受け入れ、初期の原稿を真っ先に読んでは賞賛を贈り、私物のタイプライターまで譲って、常に励まし応援した。強い信頼関係にあった師の誠実な人柄や、評論家としての技巧と規律に対する深い敬愛の念を、著者は、納得できないバルトの著作や、後年、会えば泣き言ばかりの彼の姿に感じた苛立(いらだ)ちと同等に、淡々と述懐する。1歳違いの自身の父親の姿を時に重ねながら、情に溺れぬ抑制された著述に静かな感動を覚えるのは、通底する著者の学究的批評意識と人間的な情愛とが、誠実さとして伝わってくるからだろう。
著者の冷徹な意識は自身にも向けられる。若き日には十分に理解できなかった、高名な師の老年の倦怠(けんたい)や不安、孤独。今その年齢になって気づいた、当時の自分の思慮不足への苦い思い。手紙の再読に基づく師の回想録の体をとりながら、これは自叙伝の形で書かれた一青年の成長記でもあり、同時に、彼のバルトにまつわるさまざまな記憶をもとに自由に紡がれた小説のようでもある。筆致や趣向は異なるものの、既存の評論の形態の中で発揮した独自の創造性ゆえに、その作家性の如何(いかん)が現在も議論されるバルトを彷彿(ほうふつ)させる多面的書法は、かつて文学研究か創作かの選択に悩んだという著者が、モンテーニュを借用して述べるところの「(師から)集めた蜜をもとに独自の蜜を造る」「よき模倣」という一種のオマージュでもあるのかもしれない。
引用・借用を含め、随所で言及されることで垣間見えるフランス文学の伝統と系図、それを介してつながってゆく登場人物たちや偶然の符合など、本書の根底を成す知と教養の魅力には心底圧倒された。世界的文学研究者であり、20代半ばにして、バルトに助言を求められたほどに成熟していた著者の緻密で明晰(めいせき)な論理性と幅広い知識が、本書に幾重もの読み方を許す奥行きの深さを与えている。
(作曲家 望月 京)
[日本経済新聞朝刊2017年1月29日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














