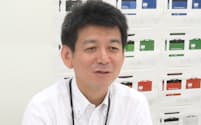音集め曲作り、見せる 「AIに作れない音楽」めざす
ミュージシャン・トクマルシューゴさん

100以上の楽器を1人で多重録音し、ワンマンオーケストラのような華やかなポップスを作ってきた気鋭が手法を一変した。多彩なミュージシャンとのセッションや自らの演奏をもとに、再構築と破壊を重ねたアルバム「TOSS」を発表。持ち味の色鮮やかで巧緻なポップスは変わらないが、楽曲の完成形だけでなく過程の面白さを訴える。
「AI(人工知能)が、あたかも人間が作ったような音楽を作れる時代。相対していくには機械には出せない答えを自分が示さないと」。新作に秘めた狙いを明かす。それは試行錯誤を繰り返し、出来上がった曲を聴かせるだけでなく過程を見せることだった。
2014年、新作に向けた録音を開始。従来の自宅録音からいったん離れ、気心の知れたドラマーやベーシストらと「何もイメージしないまま」自由なセッションを繰り返した。自らのギター演奏などとともに、それらの音を一小節よりも細かいフレーズに分解して、パソコンで曲として再構築する編集を繰り返した。「先にあるイメージを形にするのではなく、出た音をどう曲にするか。ゴールが見えないまま突っ走るから、時間はかかるが曲がどんどん変化していく面白みがある」
例えば、米国の1920~50年代のアニメ映画音楽を現代の日本によみがえらせようとした「チーズ・アイ」。新鋭作曲家の上水樽力(うえみずたるちから)率いる12人編成の室内楽オーケストラと共演した曲だ。上水樽は「トムとジェリー」などの音楽を手掛けたスコット・ブラッドリーらの研究家でもある。
「最初は音を何の意図もなく並べただけ。『タタタン、タタタン』とまさに機械が作ったような。それを『トムとジェリー』みたいな物語を想像し、何度も並び替える実験だった。何が正解なのかは分からない。でも手応えがあった」
音の素材は自身やバンドの演奏だけではない。制作の終盤には専用サイトを設け、世界中の人々に投稿を呼びかけた。「ちゃんとした楽曲から断片的なものまで、数週間で国内外から約2000件の投稿があった」。集まった素材を織物のようにまとめ上げ、壮大なスケールを感じさせる曲「ブリコラージュ・ミュージック」ができた。
このような過程を逐次、動画付きでネットで公開していった。例えば1曲目「リフト」ならば「その場で構成と内容を固め、ベーシック楽器、管楽器を録音→別曲に変更。全く別物に進化」などと完成までの進捗を文章でつづっていく。途中まで進んだのに「方向性の違いによりアルバムに収録しないことに決定」とボツにした曲もある。
「作曲家は普通、音楽ができる瞬間は見せない。過程を公開するのは怖いし、リスクもある。でも、出来上がった曲を聴くだけじゃなく、背景を知ればもっと音楽の価値や重みが増して面白くなってくるはず」
動画サイトには音楽があふれ、膨大な楽曲を聴き放題というストリーミングサービスも登場した。若い世代には「音楽は無料」という価値観が広がる。「この時代に、こんなことを考えていた人間がいたと後世に残したかった」と笑う。
◇ ◇
「変なこと」突き詰めたい
新作収録の「リタルータ」は14年、自ら運営するレーベル「トノフォン」から段ボール製プレーヤー付きレコードという異色の規格で発表した。ジャケットを組み立てるとプレーヤーになり、手で回して音を鳴らす仕組み。まさに「奇想」だが、それを実現できる体制を整え、大手レーベルに所属せずにインディーで活動する若手にとってはロールモデルになっている。
11年に始まった「トノフォンフェスティバル」は自らが主催する野外音楽イベント。新進気鋭、独創的なミュージシャンが出演する。「トノフォンはほかではできないことをやっていきたい」と語る。
新作では記号や矢印などで音を表現した図形楽譜の曲を書くなどアイデアは尽きない。「僕が影響を受けた(米国の作曲家)ヴァン・ダイク・パークスや鈴木慶一さんがそうだけれど、周りなんて意識せずにひたすら『変なこと』を突き詰めていったら、あそこまですごくなった。自分もそうなれたら」
(大阪・文化担当 多田明)
[日本経済新聞夕刊2016年10月26日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。