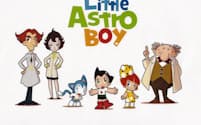「こち亀」が描いた40年 情報漫画化、ネタに先取性

東京・下町の破天荒なお巡りさん、両津勘吉が主人公の漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」(こち亀)が40年の連載を終えた。長期にわたる人気を支えた作品の魅力を振り返る。
「各巻を読み返すと『この時こうしてたな』と当時の記憶がよみがえって『こち亀』と人生を共に歩んできたと改めて思う。こんな漫画はなかなかない」。東京・芳林堂書店高田馬場店の関根俊英氏(43)は、この日を感慨深く迎えた。
ぶれない軸 強み
17日、最終回を載せた「週刊少年ジャンプ」と単行本第200巻が発売された。1976年から一度も休まずに続いた連載の終幕を祝おうと、関根氏は実家で過去のジャンプを探し出し「こち亀」が表紙となった号をスキャン。1巻~200巻をそろえた特設売り場でムードを盛り上げた。

舞台となった東京・亀有の書店などでは完売が相次ぐなど、こち亀の終了は社会現象に。作者の秋本治氏は連載終了によせたコメントで「ずっと描きたい気持ちはもちろんある」としつつも「200冊残して40周年で祝ってもらってスッと消えるのがやっぱり一番良い大団円の場」と述懐。「少年誌で漫画が40年続くってことはまずありえない」と率直な感想も明かした。
長寿漫画は「ゴルゴ13」など他にもあるが、こち亀のようにほとんどが1話読み切りのギャグ漫画では異例。しかも、人気がなければすぐに連載が打ち切られる「ジャンプ」で打ち立てたのだから「不倒不滅の大記録」(最終回が載った同誌の表紙より)だ。
長く続いた妙技はどこにあるのか。「鉄腕アトム」など数多くのテレビアニメ脚本や漫画原作を手がけてきた辻真先氏(84)は「いつでも振り出しに戻れる、恐ろしい強みを持った作品」と評す。題材は幅が広く、プラモデルやゲームのホビーの話、東京の下町の人情を描いた回、果ては主人公の両さんこと両津勘吉が神様と戦うといったSFもある。
基本は亀有の派出所(交番)を舞台にしたドタバタ喜劇だ。「ギャグ漫画はマンネリを防ぐため、話の種を絶えず変え、"ホラ"をエスカレートして吹き続けなければならない。軸がぶれて倒れる作品が多いが、両さんはいつでも亀有に帰れるから、どこまででも世界を広げられる。読者は安心して楽しめる」(辻氏)
情報漫画へ変化
漫画評論家で東京工芸大教授の伊藤剛氏(49)は「時代を捉えるアンテナの鋭さ」を挙げる。流行や最新技術、時事問題を題材に取り入れる情報漫画の傾向を強めるのは80年代前半以降。背景には「80年代の高度な消費社会の到来」(伊藤氏)がある。若者や子供が消費社会の主役となり情報を敏感に取得するようになった時代の変化を秋本氏が察知して作風を変えたのでは、と伊藤氏はみる。
ネタの先取性も特徴だ。携帯電話もインターネットも本格的な普及前にいち早く取り上げた。お金が大好きな両さんが副業で一山あてるものの欲を出して破滅するといった定番の型は大きく変わらない。古い「器」に常に新しい「水」を注ぐことで「読者が入れ替わっても全く古びない」(伊藤氏)作品として続いた。
メディア史専攻の関西学院大教授、難波功士氏(55)も「題材のたゆまぬアップデート」を強みとみる。「ネットがはやり始めた頃、パソコンで打つ顔文字を『スマイリーマーク』と呼んだ。そうした細部の事象まで折々のこち亀は忠実に描き込んだ」と指摘。「昭和から平成のメディアや世相の変遷を網羅した一大絵巻としても価値が高い」と難波氏は指摘する。
17日発売のジャンプによると、今冬にも秋本氏は新作4作を発表する。「新しい自分が見たいのだ 仕事する」。陶芸家、河井寛次郎のこの言葉が好きだと秋本氏はかつて語っていた。漫画を描き続けることで「自分の開けていないドアをたたける気がする」とも。国民的人気作を生み出した漫画家は歩みを止める気はさらさらないようだ。
(文化部 諸岡良宣)
[日本経済新聞夕刊2016年9月27日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。