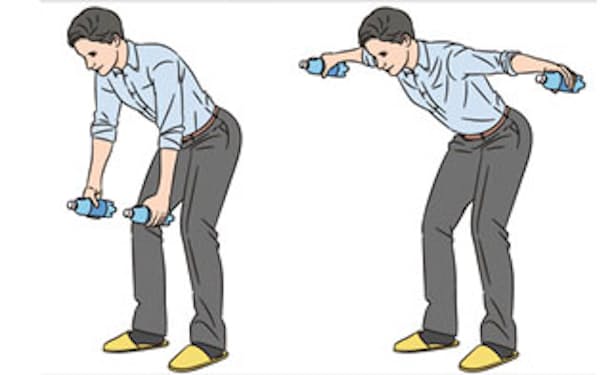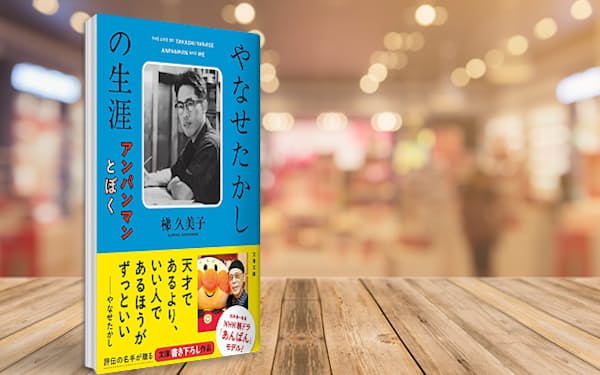その倦怠感、実は病気かも
慢性疲労症候群 日本に30万人以上の患者
普通に生活を送っていたのに、ある日突然、全身の倦怠(けんたい)感に襲われ、極度の疲労感や微熱などが何カ月も続く「慢性疲労症候群」。心の病気ではなく、脳機能の働き低下などで発症すると考えられているが詳しい原因は不明で、根本治療法もない。周囲に誤解され患者が苦しむ例もある。専門家はまだ少ないが、体に異変を感じたら詳しい医師の診断を受けることが大切だ。
関西地方に住む公務員の田中啓二さん(仮名、45)...
健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。