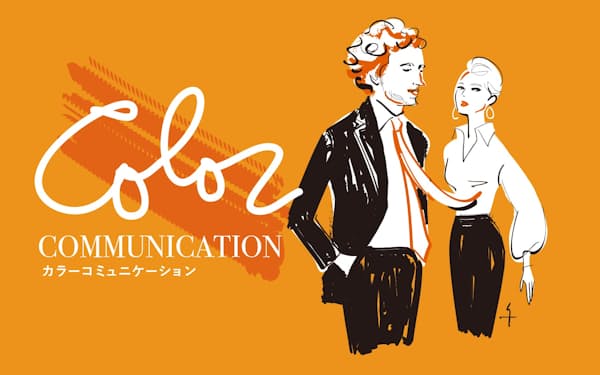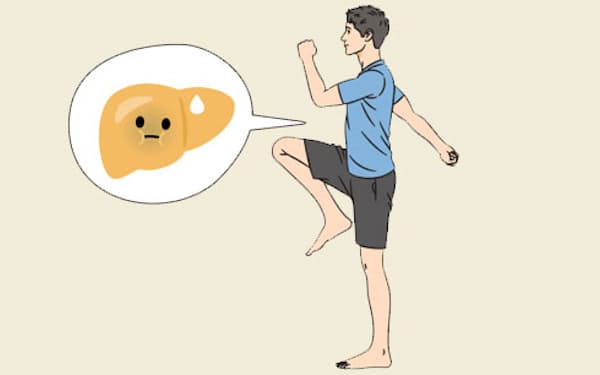伊藤、加藤、斉藤…「○藤」さん誕生の謎
編集委員 小林明
今回も「名字の不思議な勢力分布」について紹介する。
前回は「佐藤・鈴木」が東日本に多く、「田中・山本」が西日本に多く分布し、その東西の境界は太平洋側が関ケ原(岐阜県)、日本海側が飛騨山脈と親不知(新潟県)の断がいにあるということを調べた。今回はそれ以外の名字の秘密について取材してみた。
まずは「○藤」という名字。
全国名字ランキングをながめてみると、下に「藤」がつく名字が結構多いのが分かる。佐藤...
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。