不確かな世界を見える化 ビリギャルが学ぶデータの力

新型コロナウイルスに関して色々なデータが飛び交っているけど、どのぐらい信用できるのかな? データが大事だって最近よく言われるけど、どう向き合ったらいいんだろう? そういえば、私を塾で指導してくれた恩師、坪田信貴先生は統計学が大好きで、データから戦略を立てる人だったの。私が勉強楽しくなったのって、もしかしたら統計学のおかげなのかもしれない。数学は超苦手だけど、私も統計学を使えるようになったら、みんなに学びの楽しさを、もっと伝えられるかな。統計ブームの先駆けとなった「統計学が最強の学問である」の著者で、データ分析を支援するデータビークル(東京・港)も立ち上げた、統計家の西内啓さんを訪ねてきたよ。
――コロナでも色々なデータが出てくるじゃないですか。以前SNSで、「コロナに感染した人は自業自得だと思う」と回答した人の割合が日本は他国より高かったっていうアンケート調査が話題になっていたんですよ。そもそもこれ聞いて何がしたいんだろうって疑問だけど、こういうデータってどのぐらい信用していいと思いますか。
「まずアンケート調査を見るときに大事なポイントは、それをどうやって調査したのかなんです。同じ100人でも、渋谷で若い人に聞くのと、新橋でおじさんに聞くのとでは、違う結果が出てくるだろうっていうのは想像できますよね。そういうのを見たうえで、ちょっと引いた目で見るのがいいだろうという感じです」
「偏りをなるべくなくすために、統計学ではランダム(無作為抽出)というのが大事なポイントになります。本当に正確に調査するなら、ランダムに電話をかけるという方法をとります。調査対象がランダムに分けられたものなのか、そうでなければ何か偏っているかもしれないという視点を持っておくといいかなと思います」
――テレビとかで出てくるデータを真に受けちゃう人も多そうで怖いですよね。私でも、それ本当?って思うことがたくさんあるけど、統計学ってそういうことを見抜けるのかな。
「子育てに大きな影響を与えた有名な『マシュマロ実験』も、そうやって疑った学者によって、最近結果が覆りました。60~70年代に米国で実施された心理学実験で、子どもの前にマシュマロ1個を置き、大人が『いま食べずに我慢できたらあとでもう1個あげるよ』と言って部屋から出て行くとどうなるか、という実験です。実験結果では、我慢できた子どもはその後の成績が高くなったので、自制心が大事だねっていう話だったのですが…」
「マシュマロ実験」の結果は正しい?
――最初のはうそだったっていうこと?
「ウソというわけではないですが、マシュマロ実験はある集団をただ観察したものであって、ランダムに分けて、片方のグループではこういうことをやるけどもう一方ではやらない、という比較実験をしていないんです。それだと何が問題かというと、マシュマロが我慢できるから優秀なのではなくて、たまたまその集団が優秀だったんじゃないのかっていう反論から逃れられないんです」
「実際に疑問に思った人が、もう一度ランダムに分けて実験し直して、実験結果について親の所得や学歴なども考慮して分析すると、マシュマロを我慢できるかは関係ないということがわかった。つまり親が金持ちだとマシュマロぐらいまた買ってもらえるから我慢できる。結局、子どもが社会的に成功するかどうかは経済環境によるんじゃないか、ということだったんです」

――ちょっと世知辛い結果……。でも統計学がいろんな分野に入ってくると、不確かな情報に振り回される人を減らすことができそうですね。
「そうですね、昔に比べるといろいろなところでデータなどのエビデンスを重視するようになってきていて、医療業界が顕著です。それも1990年代から急速に進みました。80年代までの医療は、基本的に経験とロジックを元に治療を決めていました」
――え、意外と最近! ところでロジックとデータって、違うんですか。
「理屈上考えたことと、データから出てきた結果って逆なことがあるんです。それを示した大きな転換点が、1989年に報告された臨床試験結果(The Cardiac Arrhythmia Suppression Trialと呼ばれる、不整脈についての臨床試験)でした。それまでは、過去に心筋梗塞を起こしたことのある人が一命をとりとめた後も不整脈で亡くなってしまうというケースが多かったので、不整脈の薬を使って予防しようという治療が行われていました。その判断は理屈上、正しいじゃないですか」
「ところが、試しにどのぐらい効果があるかを検証するためにデータをとってみたら、不整脈の薬を使った方が死亡率を高めてしまうという驚きの結果が出てきたのです。医者が理屈上正しいと思っていても、人を死亡させてしまう可能性があるということがわかり、90年代初頭から『根拠に基づく医療』(EBM、エビデンス・ベースト・メディスン)という言葉が出てくるようになったのです」
――統計学で医療が進歩したんだ! 坪田先生も統計学が1番面白いって言ってたんです。西内さんは統計学のどういうところにワクワクしたんですか。
「人間とは何か、というような人文学的なことを科学的に実証できるところが一番面白いですね。例えば教育分野で、わずかな成功事例だけでは『たまたまその先生の教え方が上手だっただけ』といった特殊な状況を拾い上げているだけかもしれませんよね。それが何十人、何百人とデータを集めて適切に統計解析をすると、再現性のある科学的根拠として『確かにそう教えた方が良さそう』という成果が生まれるのがとても面白いと思います」
――統計って数学のイメージがあるけど、計算するだけじゃないんですね。
「数学ももちろん使うことはありますが、私が仕事で受ける依頼では、データ解析というより『仮説探し』が多いんです。どのあたりを深掘りしたらいいか、どの辺りに対して試しに実験してみた方がいいか、既存のデータから探していくという感じです。いっぱいデータはあるけど、どこが大事かわからないから、それを探すのが我々の仕事ですね」
教育の分野にデータを生かす
――西内さんから見て、この分野にはもっと統計の考え方を入れた方がいいのに、と思うところはいっぱいある?
「たくさんありますね」
――例えばどの分野?
「教育ですね」
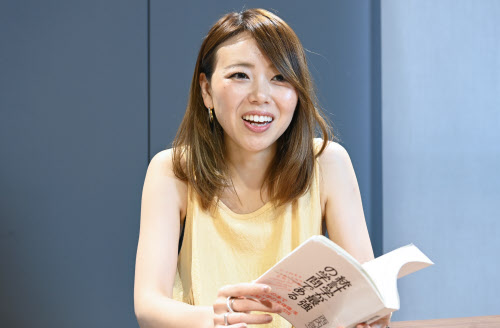
――ですよね! ビリギャルってよく奇跡だとか、もともと頭良かったんでしょって言われるんですけど、あれは奇跡じゃなくて、ちゃんと根拠があるものなんだということを言いたくて大学院で教育を学ぼうと思ったんです。教育について学べば学ぶほど、全然データとか根拠に基づいた教育がなされてなくて。そういうところを変えたくて、米国の大学院へ行こうと思っているんです。米国はデータを使った教育が進んでいるイメージですけど、プロの目から見るとどうですか。
「例えばノーベル賞を受賞したジェームズ・ヘックマン米シカゴ大教授による「ペリー就学前プロジェクト」によって、米国においては幼児教育プログラムを強化しようという政策につながっていきました。この研究は簡単にいうと、質の高い幼児教育を受けた子供と受けなかった子供を追跡調査し、前者の方が40歳時点の学歴や所得が高かったことを示したものです」
「この政策の是非は様々な議論があるようですが、それまで効果が不明確で、イデオロギー的な議論になっていたところにきちんとした根拠をつきつけたところが、前進だったかなと思います」
「ただ、米国の教育の予算は自治体で賄われるという構造的な問題もあります。つまりお金持ちエリアでは潤沢な予算があって、先進的なプログラムをやろうということになる一方、貧困層の多いエリアはそもそも予算がないからできない、となって教育格差が増強されてしまうんです。もともと格差が少ない日本は学力が高いと言われており、それはそれでいい面がある気がします」
――そっか、偏った見方にならないためにも統計学って必要なのかもしれない。私が大学院で専攻している学習科学はデータが大事だっていうのはわかっているつもりだったけど、まだ全然足りてない。勉強が楽しくないって思わせてしまう日本の教育を変えたい、そのためにはビリギャルのモデルとしての意見だけではなくて、根拠のある理論を持てるようにならないとって今日改めて思いました。
「私はデータというのは、人間の『観察』や『経験』を拡張するものだと考えています。例えば、年間約10万人が医療ミスによって亡くなっているデータを、米国医学研究所が報告書の中で示したんですね。これに基づき2004年、『100000 lives』と呼ばれる医療の質改善キャンペーンが始まりました。手洗いなどの院内感染対策や、投薬内容の確認など、ごく当たり前の目標を多くの病院で徹底した結果、入院死亡者数を大幅に減らすことができました」
「データの中には、一人の人間が認識できる範囲を超えて、『良い判断』に繋がるヒントが隠されています。教育界においても、いくら優秀な先生や官僚でも、国や地域の全学生がどのような状態にあるかを観察したり、経験したりすることはできませんよね。特に恵まれた立場の人間ほど、意識していないと格差の存在を見たり触れたりする機会は少ないですから、そういった意味でも、教育の世界においてデータをうまく使うことがとても重要だと、私は思います」
(文・構成 安田亜紀代)
1981年生まれ。東京大学医学部卒。東京大学助教、大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長などを経て、ビッグデータやデータサイエンスがビジネス界で注目を集めるようになった2010年に独立。14年にデータ分析用のソフトウェアを開発して売るデータビークルを立ち上げ、代表取締役CPO(最高製品責任者)に就任。著書に『統計学が最強の学問である』(ダイヤモンド社)など。
1988年生まれ。「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話」(坪田信貴著、KADOKAWA)の主人公であるビリギャル本人。中学時代は素行不良で何度も停学になり学校の校長に「人間のクズ」と呼ばれ、高2の夏には小学4年レベルの学力だった。塾講師・坪田信貴氏と出会って1年半で偏差値を40上げ、慶応義塾大学に現役で合格。現在は講演、学生や親向けのイベントやセミナーの企画運営などで活動中。2019年3月に初の著書「キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語」(マガジンハウス)を出版。19年4月からは聖心女子大学大学院で教育学を研究している。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














