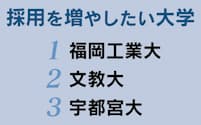「頑張れ」と言わない 校長が説く自己肯定感の高め方
「これからの学びのカタチ」 後編
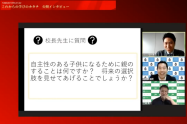
新型コロナウイルスの影響で全国の学校現場は大きな混乱に見舞われています。学びを止めないために、学校や保護者、そして児童・生徒は今どのように行動すればいいのか。今注目の2人の校長への公開インタビューで探るオンラインイベント「これからの学びのカタチ」を5月30日に実施しました。2回にわたってお届けする当日の模様、今回は後編です。(聞き手はU22 桜井陽)
工藤勇一氏(学校法人堀井学園 横浜創英中学・高校 理事・校長)
日野田直彦氏(武蔵野大学中学・高校校長兼武蔵野大学付属千代田高等学院校長)
桜井 ここからは視聴者から事前に寄せられた質問にお答えいただきます。まずこちらから。教育関係の方でしょうかね。「オンライン化が進み海外の高等教育においてもますます無料や低価格で受講、学位取得ができるようになると予測されます。教育の果たす役割はどのように変わっていくべきでしょうか?」。いかがでしょうか。
日野田 いわゆるインプット型の授業は、当然オンラインでやれます。となると、教育の役割は、例えば子供たちが行動を起こす際のマインドセットを支援するような、先ほどパシリテーターという言い方をしましたけれど、そういう方向に変わるのかなと思います。一方的な授業から脱却できる時代が来たので、先生も生徒もハッピーなのではないでしょうか。
工藤 もし単純に知識を吸収して受験に勝とうという今までの教育が変わらなかったら、オンラインでいいコンテンツを流しているところの勝ちになっちゃいますよね。世の中を自分の力で歩いていける子供を育てることと、社会の幸福のために対話して合意していくことを学べる場所であるという、本質の部分に向かって学校が進んでいくことが大事です。
桜井 今回は保護者の方からの質問もたくさん頂いております。「自主性のある子供になるために親のすることは何ですか? 将来の選択肢を見せてあげることでしょうか?」。コロナの有無にかかわらず重要なテーマかと思いますが、いかがでしょう。
工藤 一方的に与えられるだけで物事を自分で考える力を失ってしまった子供を復活させる手立てと言ってもいいと思うんですね。自分でやるということを見失ってしまった子供というのは、さっき言ったようにサービスを与えられ続けているので、うまくいかないことがあると人のせいにする。人のせいにする子供というのは、自分に対して劣等感を持っています。自己肯定感がとても低い。これを変えていくためには、「自己決定」を繰り返させていくしかないんです。
子供の自己決定を促す3つのセリフ
麹町だったら3つのセリフですね。最初に子供が自分で現状把握するような問いかけ方をするのが大事です。「何に困ってる?」「どんな感じ?」と聞きます。2つ目に「君はどうしたいの」と。悪さをしたり、友だちとけんかしたり、問題行動を起こした子供に対しても、必ずこの2つのセリフを最初に使うんです。今までは親とか先生が結論を出してくれる。「謝れ」とか、「悪いことしたんだからこうしろよ」と。そうではなくて、「君はどうしたいの」と聞くわけです。最初のうちは、どうしたいと聞かれても子供自身は戸惑うわけです。最後に僕ら教員が「何を手伝ったらいい?」と聞くと、子どもは驚きですよね。叱られると思ったら、何を手伝ったらいいかと聞かれるわけです。

「こんな支援だったらできるけどどうする」と聞くと、子供も「じゃあこうしたい」と自分で自己決定する。それを支援していく。こういう小さな自己決定を繰り返していくと、自分で物事を決定するということで自己受容が始まってきます。自分の決定を自分で許していくと、人の自己決定も許せるようになってきます。他との関係もだんだん良好になってくる。自分を嫌いな子どもは人も嫌いですから。人もだんだん許せて嫌いにならなくなってくる。そうすると主体性のある子供に変わってきます。小さな自己決定を繰り返すことですね。
日野田 例えばですけど、レストランで「好きなものをお食べ」としつつも「でもやっぱりラーメンを食べろ」と言ってしまったら、自分で意思決定できなくなってしまいますよね。よくない選択肢だと親が思っても、相当危険なものでない限りは本人にやらせてみる。それで一回痛い目をみたりしないと、わからないことのほうが多いですよ。僕ら大人だってそうですよね。親が選択肢を奪っていくと、我々の経験上、ろくなことになりません。なので、どんなに失敗したとしても、成績が下がったとしても、自らの選択肢は自分で選択させるというか、選択していくように待つことが大事です。まあ、僕も待てないことがあるんですけれどね(笑)。
工藤 勝手に子供たちに理想を植え付けて、その理想に届いていないことに対して劣等感を持てという指導をしていると思うんです、我々教育に携わる者や多くの大人たちは。「何でお前できないんだ、もっと頑張れよ」みたいな感じですね。今のままじゃダメだということを言っているわけです。自己肯定感にはつながらないわけです。勝手に理想を掲げて勝手に不幸になる教育はもうやめないといけないです。
桜井 3つ目の質問です。これもまた切実な質問ですね。コロナ禍の中で教員を志望する学生さんからです。「来年度採用に向けて教員採用試験活動中の学生です。『これからの学びのカタチ』を実践するためにこれからの教員に求められる資質は何ですか?」。いかがでしょう。
工藤 教育って何なんだろうって、何のために学校はあるんだろうっていう、本質的な問いかけをしてほしいと思います。実際に現場に立つと理想通りにはいかず、目の前の課題を解決していかなければならなくなるんですけど、一方で常にそれに疑問を持ちながらやるということが大切です。
弱みを見せることで対話が生まれる
それから、日本の教育がダメだなんて憂いたりしないでほしいです。勝手に理想を描いて勝手に不幸になるなということです。待ちの姿勢にならないで、校長が動いてくれないから、誰かが動いてくれないから、組織がダメだからと思わないでほしい。現実を憂いたりしないということを子供たちに教えたいのであれば、自分が組織の現実を憂いたりしないで、何が課題なのかを自分の目で何度も繰り返して見つめ直す訓練をしていく。そして行動に起こしてみる。それでうまくいかなければ違う行動を起こしてみる。これを繰り返していくということですね。そういう教員であってほしいと思います。

日野田 生徒が分からないと言っていることを理解してあげられる先生、また、苦手なことにでも果敢にチャレンジする先生の姿を生徒は見ています。本当の意味でのやさしさを持っていて、自分自身もつらい思いをしていたりする先生にこそ、生徒は共感できます。
偉そうな先生は鬱陶しいじゃないですか。先生が弱みを見せると、生徒も弱みを見せてくれます。先生がうそをついて強いふりをすると、生徒も強いふりをして、お互いにどんどん心の壁が深まっていって、対話ができなくなりますから。共感と共有ということをテーマに学び続けていただける先生だったらいいなというのを、うちの学校で教員採用するときには必ず言い続けているところですね。
桜井 ありがとうございます。ではまとめとして、コロナ時代の学びと教育について、全体を通じてのメッセージをお願いします。
工藤 僕は麹町中から横浜創英に来てまだ2カ月なんですけど、この2カ月間で本当に僕自身もいろいろな学びがありました。麹町でもいろいろなことを学んだんですけど、あらためてこの新しい環境に来て、ああやっぱりできるんだと。教育っていうのは、人ってすごいなということを感じたんですね。
コロナで大変な状況の中で、1人1台のパソコンもなく、教室のWi-Fi環境もない。それでも、1カ月もたたないうちにオンラインですべての子供たちと結ばれて、1600人以上の子供たちと二者面談が済んでいる。しかも、日に日にレベルアップしていく。これからのウィズコロナというのは、教職員一人ひとりの対応力を組織の対応力に変えていくことが求められていると思います。僕はこの2ヶ月で確信しました。これを多くの学校で、自分事にして展開していってくれたらうれしいと思います。
日野田 かつての日本には、米国のシリコンバレーのような雰囲気があって、30%程度の完成度で挑戦し、とりあえずフィードバックをもらおうと、そして、どんどん素早くつくっていこうという強さがありましたよね。今はどうでしょう。パッションと知識、マインドセットをなぜか社会が捨ててしまっているように見えるんです。
でも、例えば僕が以前校長を務めていた大阪府立箕面高校の卒業生の子が「あたらしい高校生」(山本つぼみ著 IBCパブリッシング)という本を書きました。それを読むとよく分かるのですが、本当に無限の可能性を持った中高生や大学生がたくさんいる国です。ウィズコロナの中であっても、皆でもっと応援して、そのチャレンジを支えていけるような国の政策や自分自身の行動ができたらいいなと思い続けています。
東京理科大学理学部 1 部応用数学科卒業。山形県公立中学校教員、東京都公立中学校教員、東京都教育委員会、目黒区教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課長を経て、2014年4月から2020年3月まで千代田区立麹町中学校 校長を務める。麹町中学校在職中、学校教育を本質から見直し、学校運営に全教職員、生徒・保護者を当事者として巻き込みながら、形骸化した教育活動をスクラップし、再構築した。定期考査や宿題の全廃、固定担任制の廃止、服装頭髪指導の廃止などを行う。
(主な著書)
学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる!公立名門中学校長の改革―(時事通信社)が10 万部超のベストセラー
帰国子女。同志社国際中高、同志社大学卒。塾ではトップ講師として、学校では私立学校の新規立上げなどに携る。2014年大阪府の公募等校長制度に応じ、大阪府立箕面高等学校の校長に着任(当時全国最年少36歳)。着任3年目には海外トップ大学への進学者を含め、顕著な結果を出す。2018年武蔵野大学中学校・高等学校の校長に着任。定員を大幅に下回る厳しい経営状況であったが、グローバル・イノベーション教育を展開し、2年で定員を充足し、さらなる発展を推し進める。2020年より武蔵野大学附属千代田高等学院の校長を兼任。
(主な著書)
なぜ「偏差値50の公立高校」が世界のトップ大学から注目されるようになったのか! ?(IBCパブリッシング)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。