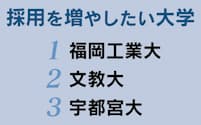校長に聞く、コロナで変わる教育 自律学習IT後押し
「これからの学びのカタチ」 前編

新型コロナウイルスの影響で全国の学校現場は大きな混乱に見舞われています。学びを止めないために、学校や保護者、そして児童・生徒は今どのように行動すればいいのか。今注目の2人の校長への公開インタビューで探るオンラインイベント「これからの学びのカタチ」を5月30日に実施しました。当日の模様を2回にわたってお届けします。(聞き手はU22 桜井陽)
工藤勇一氏(学校法人堀井学園 横浜創英中学・高校 理事・校長)
日野田直彦氏(武蔵野大学中学・高校校長兼武蔵野大学付属千代田高等学院校長)
桜井 全国の学校が迷いながら、新型コロナウイルスへの対策を進めています。緊急事態宣言が解除され、いわゆるコロナ前の「正常化」に向けて学校はどのように動き出したらよいのでしょうか。
日野田 「正常化」と言いますが、今まで通りに戻すということが前提の議論は、もはやナンセンスだと思っています。教育現場のIT化を契機に、次のステップに行かなければなりません。そうですよね?工藤先生。
桜井 工藤先生、そもそも、ITを使うとどのような教育ができるのですか。
工藤 私がこの春まで校長を務めていた千代田区立麹町中学のことをお話すれば、ITは技能や知識を習得するのにはとても便利でした。教室で一斉に情報を伝達して暗記させる従来のスタイルは、ものすごく非効率なんですよ。AIを使った学習ソフトによって、数学の習得時間を大幅に短縮できましたから。このとき大切なのは、黙々とAIで勉強するのではなく、生徒同士で教え合ったり、分からなかったら先生を呼んだり、雑然とした雰囲気の中で臨機応変に学んでいくことです。ITはあくまでツールにすぎません。
日野田 同感です。ITは手段であって、目的ではないですよね。これを使ってどのように自主性のある個人を育成するのかに焦点を当てるべきです。普通に教室で教師1対生徒40で授業している限りは、授業中に手を挙げたりとか、わからないことをわからないですとはなかなか言いにくいです。そういうのをオンラインを通じて素直に積極的に発言できるようになることが望ましいです。教育も目的は本来こちらですよね。もちろん、その前提としてインフラ整備も重要で、全国の小1から高3までの生徒にWi-Fiとパソコンを渡して通信費は国が持つというような、大胆な政策があってもいいと思います。
「教員も変わっていく時代が来た」
桜井 ITの力を使って生徒同士の学び合いを促進できるような環境が必要ということですよね。
工藤 横浜創英では5月から新しい授業カリキュラムをつくったのですが、基本的にオンラインでZOOMとグーグルのG Suiteを使っています。日常の授業ではなかなかグループ学習は活発ではなかったのですが、ITを使い始めたらグループ学習を盛んに使ってディスカッションをする授業が頻繁に行われるようになりました。チームティーチングも簡単にできるようになりましたしね。
桜井 そうなると、教員の役割も変わってくる気がします。例えば、メンターとかファシリテーターのような役割になっていくのでしょうか
日野田 教員が変わっていく時代が来たのかなと思っています。僕はよくファシリテーターではなく「パシリテーター」と言っているのですが(笑)、「僕らは君らのパシリ。だから何でも言ってほしい。チャレンジするのは君らのほうで、我々は最後のリスクヘッジだけするから、どんどん失敗して」とよく言っています。学びの主体は生徒です。学校経営にも生徒が参加すべきです。学校は自分の目的や使命に気づくところであって、受け身でひたすら知識をインプットされるところではないはずです。
工藤 これも麹町中の例になりますが、教育熱心な地域にあるので、小学校時代に塾などで詰め込み教育を受けてきた子供たちが多いんです。散々与えられ続けると、自分で学ぶことを忘れてしまう。何をしたらいいか分からなくなってしまう。その姿を見て、保護者もあたふたしてしまう。ですので、子供の自律性を復活させることが非常に重要で、僕ら教師側は「勉強しろ」とは絶対に言わない。そのかわり、「君はどんな状態?」「どうしたいの?」「僕らは何を支援したらいい?」という3つの問いを繰り返し投げかけていきます。

桜井 なるほど。ちょっとITにもう一度ひき付けてお聞きします。ITを使うと生徒が何をいつどう学んだのかの学習履歴が残りますよね。これを生徒が自分自身のために使えば、自律的に学ぶことの後押しになりませんか。
日野田 高3の生徒からのフィードバックで、「今までの学習では履歴が残らなかったのに、オンライン授業だと自分なりに履歴を見て勉強の方針を立て直すことができました」というコメントがありました。そして、こうした有益な情報も、生徒が勝手にどんどん共有してくれるんです。僕らみたいな教師や保護者が頑張りすぎないほうが、もはやいいんですよ。
「与えられるだけの消費者になってはいけない」
桜井 頑張っちゃダメなんですかね? とはいえ頑張っちゃいませんか?
日野田 僕らが気持ちよくなるために頑張ってしまうと話がおかしくなるので、そこですかね。生徒が自分たちで気づくように我々は頑張るべきだと思うんです。
桜井 自分の力で気づくのではなく、学校から与えられるだけの消費者のような感覚になっている生徒や保護者が多いかもしれません。自分のことを反省しながら言っています。
工藤 自分が優秀になるためにはどこか優秀な塾に入って、優秀な先生に習ったら勝手に成績が上がるって勘違いしている子供たちがいっぱいいるわけです。サービスって与えられ続けると、サービスに慣れてくるのでもっといいサービスをくれとなるんです。もっといいサービスがあるに違いないと思い込むんですよね。それでサービスの質に不満を言うようになるんです。あれがいいとか悪いとか。その時点でもう当事者意識を失っているので、能動的に動かなくなるんですよね。
日野田 工藤先生とまったく同じ考えです。常に何かしてもらえると勘違いしていると、大人になってからも会社が何とかしてくれると思ってしまう。だから、ある日突然会社が傾いてしまったら、もう大変。そうではなくて、自分がどうやって学校や社会に貢献するのか。自分にしかできないことは何かというのに気づくことこそが、「当事者意識」「オーナーシップ」ですよね。自分の人生のオーナーシップを持っている人は、自分で何とかしようと動くと思うのです。

工藤 今私が校長を務めている横浜創英は行事や部活が盛んで、教員と生徒がとても「密」につながっている、いわゆる日本的ないい学校なんです。でも、コロナでその長所が奪われてしまった。だからこそ、教員には子どもたちが当事者になるようなメッセージを発してもらいました。今できるベストを尽くしましょうと。選択肢としてはオンラインしかない。新たなカリキュラムを作る、つまりもう別の学校を作っちゃえということですね。
日野田 子供たちはオンラインで学ぶ環境に慣れてくると、どんどん新しくやりたいことが出てくるんです。ただ、もちろんリスクを伴う。だからそういうときはメリットとデメリットの両面を押さえた企画書を出してねと校長メッセージを飛ばしているところです。ただ「やりたい」とだけ言われても学校としては動けないですが、リスクを含めて全部説明してくれたら、きちんと対応すると伝えています。すべての学びは当事者としての生徒が主体ですから。
東京理科大学理学部 1 部応用数学科卒業。山形県公立中学校教員、東京都公立中学校教員、東京都教育委員会、目黒区教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課長を経て、2014年4月から2020年3月まで千代田区立麹町中学校 校長を務める。麹町中学校在職中、学校教育を本質から見直し、学校運営に全教職員、生徒・保護者を当事者として巻き込みながら、形骸化した教育活動をスクラップし、再構築した。定期考査や宿題の全廃、固定担任制の廃止、服装頭髪指導の廃止などを行う。
(主な著書)
学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる!公立名門中学校長の改革―(時事通信社)が10 万部超のベストセラー
帰国子女。同志社国際中高、同志社大学卒。塾ではトップ講師として、学校では私立学校の新規立上げなどに携る。2014年大阪府の公募等校長制度に応じ、大阪府立箕面高等学校の校長に着任(当時全国最年少36歳)。着任3年目には海外トップ大学への進学者を含め、顕著な結果を出す。2018年武蔵野大学中学校・高等学校の校長に着任。定員を大幅に下回る厳しい経営状況であったが、グローバル・イノベーション教育を展開し、2年で定員を充足し、さらなる発展を推し進める。2020年より武蔵野大学附属千代田高等学院の校長を兼任。
(主な著書)
なぜ「偏差値50の公立高校」が世界のトップ大学から注目されるようになったのか! ?(IBCパブリッシング)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。