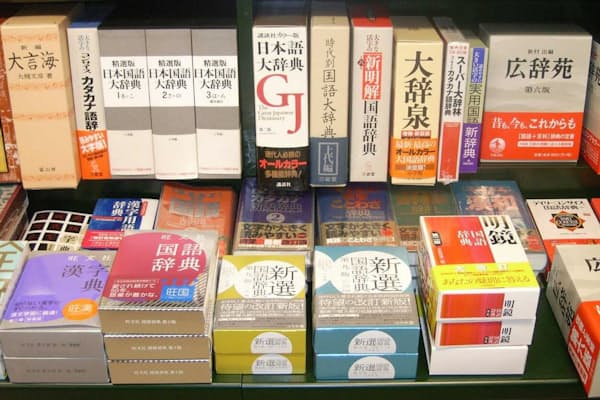芸能リポーターはどこへ行った? 変わるワイドショー

テレビのワイドショー番組も以前に比べ、芸能リポーターが主役ではなくなりつつある。 写真はイメージ=PIXTA
平成最後の師走がもうそこまでやって来た。平成のおよそ30年間を振り返るにあたって、「この時代の大きな変化のほとんどはデジタル化(主にインターネット関連のテクノロジー)がもたらした」と多くの人が言うことだろう。
例を挙げればきりがないが、カセットテープやそれを聞くラジカセを所有するのは一部のマニアだけとなり(近ごろは再評価も進んでいる)、ダイヤル式電話はもとより、街中で公衆電話を見かけることが減り、テレホンカードを使う機会も減った。
「ワイドショーの人気リポーター」が「絶滅危惧種」と言われ始めたのは、20年前にあたる1998年(平成10年)ごろからだという。これも「ネットの進化」に深く関わるらしい。たくさんの情報に個人がアクセスできる時代の到来は、芸能情報をテレビの芸能リポーター経由で入手する必然性が下がることにもつながったからだ。
芸能リポーターの出番が減った理由
今や「芸能情報にアクセス」どころか、SNS(交流サイト)を使えば、芸能人と直接やり取りすることさえ可能だ。リポーターの存在感が下がったかのようなことを言うと、井上公造さんのように現役でご活躍の芸能リポーターからお叱りを受けそうだが、では井上さん以外に「顔と名前が即座に一致する芸能リポーター」って、今、います?
1970年代初めから2000年ぐらいまでの約30年ほど、テレビ業界は芸能情報に重きを置いたワイドショー番組が茶の間の高い支持を受ける時代だった。そこで大活躍したのが芸能リポーターのみなさんだ。長老格とも言うべき、スポーツ新聞記者出身の鬼沢慶一さん、芸能リポーター界のスーパースターだった梨元勝さん、そのライバルと言われたフジテレビ専属の前田忠明さん、映画にも詳しい福岡翼さんなど、そうそうたる面々だ。
異彩を放った辛口リポーター
そしてもう一人。某スーパーアイドルに「須藤さんがこの会見場にいるなら、僕、お話できませんから」とまで言わしめた、べらんめえな調子でズケズケと「相手が嫌がる質問」をぶつけた須藤甚一郎さんがいる。先日その須藤さんを電車の中でお見かけし、思わず声をかけた。
梶原「須藤さん、ご無沙汰してます、梶原です!」
須藤「おー! 梶原さん、どこ行くの?」
ご無沙汰もご無沙汰。テレビでご一緒したのは2回ほど、しかも20年も昔の話だ。その程度の関係なら、普通は見て見ぬ振りをするのがマナーというものだろう。