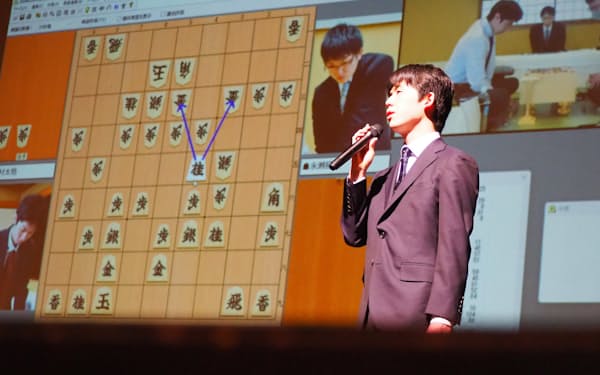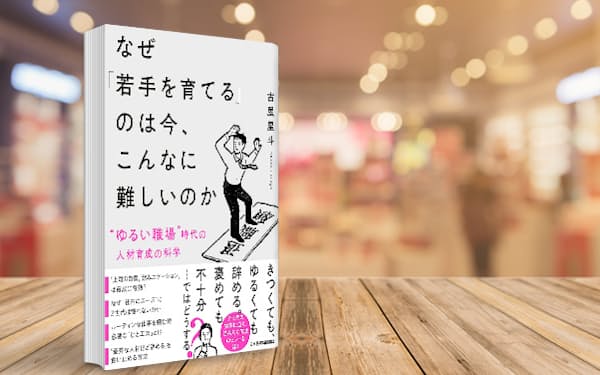クモの足の毛に鳥の羽 オーストラリアに残る化石

数年前のこと。オーストラリア南東部に住むナイジェル・マグラスさんが自身の土地を耕そうとしている最中、木の葉の化石を発見した。それはまるで本に挟んだ押し葉のように、細かい部分まできれいに保存されていた。
最近になって、サッカーグラウンドの半分もないその土地に、驚くほど状態の良い中新世(2303万年前~533万年前)の化石が大量に保存されていたことが明らかになった。
2022年1月7日付で学術誌「Science Advances」に発表された論文によると、ここマグラス・フラットは、中新世の熱帯雨林の生態系が化石として残る、世界でも珍しい場所だという。この時期、世界の生態系は大きく変化し、オーストラリアもアマゾンのような熱帯雨林から、現在のような乾燥地帯へと移行し始めていた。
オーストラリアではこれまでも中新世の哺乳類や爬虫(はちゅう)類の化石が見つかっているが、マグラス・フラットほど、生態系の基礎を成す小さな生物の化石が数多く発見されている場所は他にない。これらの化石は、1600万~1100万年前に、現在のニューサウスウェールズ州を覆っていた熱帯雨林がいかに多様性に富んでいたかを示している。
マグラス・フラットでは、クモの足の毛まできれいに保存され、魚は、虫を食べた後おなかを膨らませた状態で化石化していた。木の葉の化石は、二酸化炭素を吸い込んでいた気孔まで確認することができる。

生き生きとした生命の営みをそのまま切り取ったような化石もあった。頭を花粉だらけにしたハチは、きっと花の蜜を吸ったばかりだったのだろう。ある魚の尾びれには、二枚貝の幼生が寄生していた。この幼生は、川を俎上(そじょう)する魚に寄生し、その粘液を食べて生きていた。
化石の保存過程
オーストラリア博物館研究所の古生物学者で、今回の論文の執筆者の1人であるマシュー・マカリー氏がマグラスさんから連絡を受けたのは、17年のこと。マグラス・フラットの重要性に気付いたマカリー氏の研究チームは、その後繰り返し現地を訪れるようになる。
この場所の化石は、特殊な状況で保存されていた。化石は全て、針鉄鉱と呼ばれる極めて細かい酸化鉄の層の中に埋もれていた。同様の層から化石が発見されるのはこれが初めてではないが、マグラス・フラットの化石の質の高さは際立っている。
マカリー氏と共同で研究を率いたマイケル・フリース氏は、マグラス・フラットの化石は、その特殊な状況のおかげで、強力な走査型電子顕微鏡(SEM)の分析に適していると話す。一般に、SEMに使用する試料は、金やプラチナの薄い膜でコーティングする必要がある。だがそれをしてしまうと、その後この試料を使ってできる研究が制限されてしまう。その点、マグラス・フラットの化石は既に鉄が豊富に含まれていて導電性があるため、特別な準備をすることなくそのまま顕微鏡の下に置くことができる。
この方法によって既に、小さな化石のなかから驚きの発見がなされている。マグラス・フラットで唯一発見されている羽毛の化石からはメラニン色素が確認されており、その形状から羽毛が濃い色か玉虫色をしていた可能性があることがわかった。また、魚の目の化石にもメラニン色素が確認され、さらに1100万年以上前のチョウあるいはガの翅(はね)から剥がれ落ちた鱗粉(りんぷん)まで見つかった。

鉄の湖
マグラス・フラットは太古の三日月湖だったと、研究チームは考えている。蛇行する川の一部が途切れてできた湖だ。捕食動物はそれほど多くなかったが、これまでに十数種類以上の魚の化石が見つかっていることから、近くの川が氾濫した時に、魚など川の生物が定期的に流れ込んでいたと見られる。
マカリー氏とフリース氏は、近くにある玄武岩に含まれていた鉄が、岩の浸食とともにそこを流れる水に溶け出したのではないかと考えている。豪雨や洪水などで酸素濃度の高い新鮮な水が湖に流入すると、水中に溶けていた鉄イオンは湖底に沈殿して針鉄鉱を形成した。この時、たまたまそこにあった木の葉や生物の死骸も一緒に埋もれ、やがて化石となった。
この湖における針鉄鉱のサイクルが季節的なモンスーンによって引き起こされた可能性があると、研究チームは考えている。マグラス・フラットでこれまで発見された花の化石は、ほとんどが開花前のものであることから、毎年同じ時期にこの現象が起こっていただろうと見ている。また、現代の生態系では春と夏にしか見られない昆虫の化石も多く見つかっている。
マカリー氏とフリース氏は、マグラス・フラットの推定年代をさらに細分化しようとしている。そうすれば、熱帯雨林だったマグラス・フラットがどのようにして今のような乾燥した灌木(かんぼく)地に変化していったのかを理解し、さらに現代の世界にある熱帯雨林が、この先気候変動にどう反応するかについても手がかりが得られるかもしれない。
過去から未来へ
中新世の初期から中期にかけて、大気中の二酸化炭素の濃度はおよそ400~500PPM(PPMは100万分の1)だった。これは、近い将来、人間活動によってもたらされると推定される二酸化炭素濃度の値に近い。また、中新世は長い間温暖な気候が続いていた時期だった。特に1700万~1400万年前の中新世中期は最も暖かく、ちょうどマグラス・フラットの化石の時代がこの期間に含まれていた可能性がある。
中国科学院の古生物学者である王波氏は、今回の研究には参加していないが、次のように述べている。「今回の論文は、現代の地球温暖化に直面している熱帯雨林の生態系が、これからどのように変化していくのかを理解する助けになるかもしれません。論文によると、オーストラリアでは熱帯の生物相が少なくとも南緯37度まで達していたようですが、それがいつ現れ、いつ消えたのか、なぜそうなったのかまではわかっていません」
その変化についてさらに詳しく調べるために、マカリー氏とフリース氏は、マグラス・フラットでの発掘調査を続ける。「鳥の羽が非常に良い状態で化石化することはわかりましたが、鳥の体全体の化石も見つけたいです。きっと、それも保存状態がかなりいいはずです」
しかし、既に発見されている化石に関してだけでも、研究することは山ほどある。「この先10年は、研究対象に困ることはないでしょう」と、マカリー氏は言う。
(文 MICHAEL GRESHKO、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2022年1月15日付]
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。