注目の中東グルメ 味の決め手はゴマから作るタヒーニ
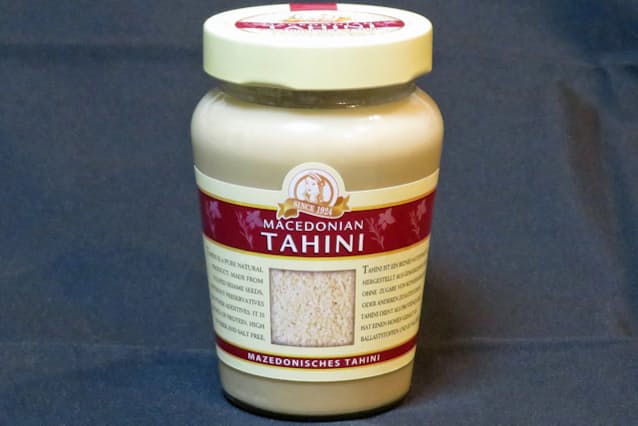
タヒーニ(tahini)という食品がある。中東地方で広く食べられているゴマペーストのことで、欧米のベジタリアン向けのレシピブックでは頻出語句の一つだ。以前、日本では輸入食材の店や高級スーパーなどでは見つかっても、身近なところではやや手に入りにくいものだった。それが、最近はネット通販で数種類が見つかるようになった。
実は新型コロナウイルス禍の前、東京オリンピック・パラリンピック(オリパラ)とそれによるインバウンド増加を控えていた時期、レストランや食品問屋はタヒーニを使った料理の研究や調達に力を入れていた。ところが、コロナ禍で渡航者の入国制限とレストランの休業要請によって、その成果はしばらくお蔵入りの状態となった。そんな中、行き場を失ったタヒーニがネット通販に流れているというのが、食品関連企業の人の見立てだ。
タヒーニを使う料理は多いが、代表的なものの1つはフムス(hummus)。ひよこ豆(ガルバンゾ)主体のペースト状の料理で、中東の広い地域で古くから食べられてきただけに多様なバリエーションがあるが、どのレシピでも共通してたっぷり加えられるものがタヒーニだ。

フムスは動物性食品を使用せずに無理なく作ることができるので、ヴィーガンやベジタリアンにも提供できる。しかも、植物性食品は基本的にハラール(ムスリムが選択してよいもの)とみなされ、調製されたタヒーニもハラール認証付きで売られているものは珍しくない。
つまり、フムスはヴィーガンやベジタリアン対応、ハラール対応という、従来の日本のレストランや食品関連企業が抱えていた弱点を同時にクリアし得る料理と言える。したがって民族・文化・宗教の多様性、環境、健康というキーワードとも親和性がある。しかも、日本人向けとしても新味を打ち出しやすい。
オリパラを控えて、各社がフムスをはじめとする中東料理や、中東料理でよく使われるタヒーニに注目したのにはそうした事情がある。

商品の例としては昨年12月、ファミリーマートがサラダ専門店「サラダカフェ」監修の「フムスと食べる タンドリー風チキンのサラダ」も発売している。そして2022年3月から、特に5月以降に国内の外食市場が回復してきており、また、インバウンドの回復につながるニュースも増えてくる中、動き出しているのが中東料理系メニューなのだ。フムスやフムスをアレンジした料理を提案するホテルやレストランが増えている。
また、「日本国内においてエスニック文化や食の普及活動を行う」日本エスニック協会(東京・千代田)も、同協会がこの夏に流行すると予測する「エスニック食」の1つとしてフムスを取り上げている。
このように話題になってくると、フムスをはじめタヒーニを使った料理を自作してみたくなるもの。というわけで、筆者もネット通販でギリシャ産のタヒーニを見つけて取り寄せてみたのだが、さっそく開封して味見して驚いたのは、しゃぶしゃぶ/冷しゃぶやそうめんのつけだれでよく知っている、何の変哲もない練りゴマの味と変わらないということだった。
日本の練りゴマそっくりだが作り方は多様

びんの表示を見てみると、確かに「名称:ねりごま」と書いている。しかも、「原材料名:ごま」で、エキゾチックな風味につながるようなハーブ、スパイス、ほかの材料由来の油脂などは使っていない、いわば全くの「ジェヌイン(正真正銘)練りゴマ」である。
実は、和訳された海外のベジタリアンが書いたレシピブックで、タヒーニという語には「ゴマペースト」「ゴマバター」あるいは「ねりゴマ」とカッコ書きで添えられていることが多い。また、タヒーニをネット検索で調べていたときに、あるサイトで芝麻醤(チィマァジャン)に誘導されて面食らったことがある。芝麻醤も練りゴマであり、そのウェブサイトの誘導は正しかったのだと理解した。
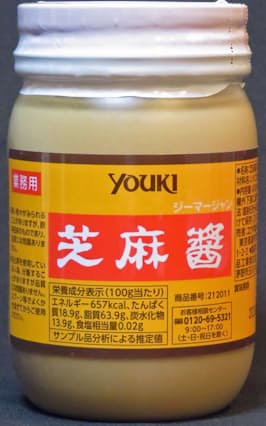
ただし、だからといってタヒーニがどれを選んでも誰が作っても同じということではない。というのは、欧米の料理好きには既製品のタヒーニを買って来るよりも、ゴマを買ってきて自分で作って楽しむ人も多いようで、ユーチューブでは各国のいろいろな人のタヒーニ作りを見つけることができる。そのそれぞれの流儀に違いがあるのだ。
それらからタヒーニ作りの一般的なプロセスをまとめると、まずゴマを軽く煎(い)る。英語圏の人はトースト(toast)すると表現しているので、さっとあぶってからりとさせるイメージだが、「よい香りがするまで」のように表現している人もいる。ゴマが含む油脂を軟らかくして、香りを引き出すための仕事だろう。
ゴマをほどよく煎ったら、それをフードプロセッサーにかけてそぼろ状にする。そこに食用油(多くの場合オリーブオイル)を加えて、さらにフードプロセッサーにかける(筆者が買ったギリシャ産のびん詰めの場合は、原材料がゴマだけなので、ゴマ油を加えて練ったものと考えられる)。これに適宜、塩を加えて味を調えるなどして完成だ。
こうしたプロセスのあらましはだいたい共通だが、トーストの度合い、加えるオリーブオイルの量、フードプロセッサーにかける時間の長さはさまざまだ。人によって違うだけでなく、同じ人でも料理や菓子の使い道によって変えることを説明していたりするので、なかなか奥深い。
多少本題からそれるが、こうしたタヒーニの作り方を見ていてふと不思議に思うのは、このゴマはなぜ白いのか、ということだ。
日本で育った人の場合(古い感覚なのかもしれないが)、ゴマと言って最初に思い浮かべるものは、赤飯にかけるゴマ塩のゴマではないだろうか。「ごま塩頭」という言葉があるように、そのゴマの色は黒だ。ひょっとして黒ゴマの表面を剥いたものが、あの白いゴマなんだろうかと思ってしまうかもしれないが、実はそうではなく、最初から白いゴマと黒いゴマとがある。
中東や欧米で使われているゴマは白ゴマという種類のもの。黒ゴマは日本など東アジアで栽培・流通しているもので、欧米では見たことがないという人が普通のようだ。黒ゴマは風味が特徴で、色から料理のビジュアルのアクセントにも使える。
ゴマは低糖質で抗酸化成分たっぷり

一方、白ゴマは黒ゴマよりも油の含有量が多いので、タヒーニのようにペースト状にして使うのに向いている。ほかに、トルコで特有に栽培されているものとして黄ゴマというものがある。これは風味に特徴があるということで、日本でも近年これの香りのよさを打ち出し、名称も「金ゴマ」と言い換えて売り出されている。
それでは日本はゴマをどれぐらい生産しているかというと、農林水産省のサイトでは「国内に流通しているごまのほとんどが輸入品です」という記述が見つかるぐらいで、数字は簡単に出てこない。「機械化できる部分が少なく、手間がかかるため、国内での生産増はなかなか難しいのが現状です」ともある。

世界のゴマの生産状況はJETROがまとめた20年のデータによると、生産量トップはスーダン、2位以下は1桁少なくミャンマー、タンザニア、インドなどが続き、このうちミャンマーは特に黒ゴマ生産が多い。ゴマをたくさん利用することは、文化交流だけでなく貿易による国際交流の振興にもなるということのようだ。
さて、前述のフムスは中東を中心とする地域の人たちの日常食であり、それにタヒーニがたっぷり使われているということは、彼らは毎日たくさんのゴマを食べていると言える。赤飯の上にちょっと散らすとか、おひたしなどの小鉢にちょっと振りかけるぐらいのお付き合いしかない日本の者からすると、これは大きな違いだ。特に栄養的にどんな御利益があるのかは気になるところだ。
何とゴマは、半分かそれを超える分が脂質である。「それは太りそう」と思うかもしれないが、2割がたんぱく質で、また2割近いがそれより低い分が炭水化物となっている。したがってゴマ食は糖質制限ダイエット向きと言えるかもしれない(ただし、例のフムスの主食材のひよこ豆は炭水化物の多い食品ではある)。
いずれにせよ、ゴマは油脂の多い植物である。しかも、比較的やせた土地でも手間なく育てやすい作物ということもあり、古来、油を取るための植物として栽培され、利用されてきたという。化粧品や薬としても利用されてきたというのは、主に油脂として保湿などに使われてきたようだ。
一方、中東は日差しが強い地域のイメージもあるので、ひょっとして美白効果とか抗酸化作用とかがあったりはしないか。実はゴマはリグナンというポリフェノールを含み、それは抗酸化作用を持つという。リグナンには、セサミン、セサモリン、セサモール、セサミノールといった種類がある。
そうは言っても、たとえフムス食ゾーンであっても、食事としてのゴマから摂ることができるリグナンはそれほど多くないので、リグナンを摂るにはサプリメントということになるだろう。上記のリグナンの種類の中に最近のサプリメント成分でもよく見かける名前があるわけだ。
このリグナンについては、健康食品メーカーだけでなく農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)も注目したようで、同機構は高リグナン含有のゴマ品種として「ごまぞう」「まるえもん」「まるひめ」という3品種を育種してリリースしている。
日本のゴマ生産量は決して多くないが、日本発のゴマ品種が世界のゴマ生産をさらに活性化するかもしれない。こんなロマンも抱きつつ、まずはこの夏、コロナ禍を超えて日の目を見るタヒーニ料理を楽しみたい。
(香雪社 斎藤訓之)
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














