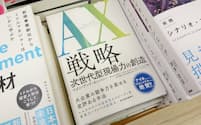人材が競争力を生み出す 人的資本経営へ戦略シフト
ヒト、モノ、カネは経営の三大資源といわれます。中でも今、ヒト(人材)への注目が急速に高まっています。人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、企業価値向上につなげる人的資本経営を表明する企業が国内外で増加しています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や、新型コロナウイルスの感染拡大などで経営環境は大きく変化しています。先が読めない時代だからこそ、競争力の源泉である人材に注目が集まっているようです。女性管理職比率や離職率など、人材の活躍・育成状況の情報開示を求める動きが広がっていることも理由のようです。
三井化学は今年4月、安藤嘉規専務執行役員をCHROに就けます。CHROは「Chief Human Resource Officer」の略で最高人事責任者のことです。同社は昨年、長期経営計画をまとめ、2030年度の連結純利益を2倍近い1400億円に伸ばすといった目標を定めました。目標達成を担う社員をどう育て活躍の舞台を整えるのか、人材戦略の立案・実行に責任を負います。
人材重視の動きは他社でも顕著です。資生堂は1月に人事部を解消し、人財本部を設けました。採用や育成、給与管理といった従前の雇用管理に加えて、社員データの分析やDX活用を通じて変革期を担う人材強化に努めます。中部電力も4月に社長直轄の人財戦略室を新設します。
働き方改革や女性活躍推進など、企業は人事施策の見直しを進めてきました。ただ人的資本経営へのシフトはそうした流れとは別です。デロイトトーマツグループ執行役員の田中公康氏は「経営戦略と強く結びついているのが特徴。企業価値を高めるためにはどんな人材が必要なのか。経営戦略から逆算して人材戦略を立てようとする動きです」と説明します。

背景にあるのは産業構造の変化です。2次産業が主流の時代は、いかに早く安く生産するかが企業の競争力の源泉でした。今は「何を」つくるか、創造性と革新力が問われます。これらは製造装置のような有形資産からは生じず、人材などの無形資産から生まれます。米国S&P500社の市場価値を分析すると、その約9割は無形資産が生み出しているといわれます。
政府も人材を中心に据えた経営を注視します。経済産業省は人的資本経営の実現に向けた企業向けガイドラインを年度内にまとめます。上場企業には人的資本に関する情報開示を求める意向で、開示項目や手法の議論も始まりました。
「欧米では情報開示を義務付けるルールが整備され、人的資本経営の中身は投資対象とするか否かの判断材料にもなります。日本企業も今後は、成長に結びつく人材戦略を立てて実行することが求められます」と田中氏は指摘します。
デロイトトーマツグループの田中公康氏「経営戦略に基づく人材戦略が重要」
人の知識や能力が経済成長の源泉であるとする人的資本の考え方は、米国の経済学者ゲーリー・ベッカー氏が20世紀に提唱した経済理論です。半世紀以上の歳月を経て、なぜ今、人的資本経営が改めて注目されているのか。国内外の人材戦略に詳しいデロイトトーマツグループ執行役員の田中公康氏に聞きます。
――ベッカー氏がノーベル経済学賞を受賞したのは1992年のこと。人的資本の重要性を提唱したのはさらに遡り、半世紀も前です。なぜいまさら人的資本経営に企業は着目するのですか。

「日本では昨年くらいから注目されはじめました。欧米ではもう少し早く、2010年代の半ばから人的資本経営が話題に上る機会が増えました。大きな背景は2つあります。一つはESG(環境・社会・企業統治)投資への関心の高まりです。このうちS(社会)に雇用問題が含まれます。経営者は企業利益さえ追い求めていれば良いのではなく、企業の社会的役割として10年代以降、社会の発展に貢献することが強く求められるようになりました。社員の働きがいや働きやすさをどう高めるのか。企業が持続的に成長し続けるためにも、そこに目を向ける必要が出てきました」
「もう一つは産業構造変化です。IT(情報技術)産業が典型例ですが、企業の競争力の源泉は革新的なアイデア・発想に移りつつあります。米国S&P500社の市場価値を分析してみると、かつては生産設備のような有形資産の比率が高かったのですが、今では人材や知財といった無形資産が市場価値全体の約9割を生み出しています。以前は無形資産が重視された製造業も同様です。今は製造ラインを自前で備える必要もなく、外部に製造を委託するなど外から調達可能です。突き詰めていくと、製造業であっても何を作るのか、その構想力が今まで以上に問われています。創造力や企画力の源は人間の発想です。そこで企業は、いかに優秀な人材を確保・育成するかにより強い関心を持つようになりました」
――人的資本経営への関心は欧米が先行しているということでしょうか。
「欧米と日本を比較すると、人材戦略に関する姿勢がそもそも異なる印象です。欧米企業には人的資本経営を重視する姿勢がずっと備わっています。ヒト、モノ、カネは経営の三大資源。人事施策と経営戦略を結びつける考え方を根強く持っています。一方、日本企業は人事と経営が懸け離れていて、企業価値を高めるために人事施策を練り上げていこうという意識が希薄です。例えば昨今の働き方改革や女性活躍推進にしても、働きやすさの向上や数値目標達成に向けて人事部門は手を尽くしてきましたが、それをどう企業の成長に結びつけるのかといった戦略思考に欠ける企業が少なくありません」
「欧米では昨今、企業に人的資本経営の状況について情報開示を求める動きが広がっています。これもその典型例です。どんな成長戦略を描いて、その実現のためにどんな戦略を立てて、どこまで達成できているのか。人的資本に関する各社の個別情報は、その企業が投資に値する企業であるか否かを投資家が推し量る重要な手掛かりだと見なされています。そのため2018年には国際標準化機構(ISO)が何をどう情報開示すべきか、企業にガイドラインも示しています。20年8月には米国証券取引委員会(SEC)が上場企業に人材の採用や育成といった人的資本関係の情報開示を義務付けました。情報開示義務付けはすでに欧州でも始まっています。人的資本経営への関心が欧米でこうして高まっているなか、日本企業もいつまでも無関心ではいられません」
――政府は情報開示ルールの策定を急いでいます。情報開示に向けて企業には何が求められますか。
「重要なのは経営戦略にひもづいた人材戦略です。どんな項目をどのように公表すれば良いか、政府が具体的に示してくれるでしょう。でもルールに基づき、社内の各種統計データを発表するだけでは投資家は納得してくれません。例えば離職率。離職率は低ければ低いほど高く評価されると思われがちですが、そうとも限りません。もちろん就労環境が劣悪で離職率が高いブラック企業は論外ですが、社内の人材育成力が高い企業だと社員が若くして独立起業するケースも増えて離職率は上がるはずです。ある程度の離職は社内の人材の流動性を高め、組織活性化につながることもあります。要は情報開示されたデータはそのまま他社と比較検討しても、意味が薄いということ。離職率が同業他社と比べて高くとも、その根底に企業成長につながる人材戦略があるならば投資家はきちんと評価してくれます」
「日本でも多くの企業は何らかの人事方針を立てています。ただ、残念ながら経営戦略とリンクした人材戦略を立てている企業はごく一部の先進企業だけです。役員クラスにCHRO(最高人事責任者)を置くなど、経営戦略に基づく人材戦略を立案・実行できる体制を日本企業は早く整えなくてはいけません」
――人的資本経営へのシフトは働く人にどんな影響を与えるのでしょうか。
「年功序列や新卒一括採用など従来の雇用スタイルを見直すきっかけになる可能性があります。変化への適応を求められるので短期的には対応に苦慮する人も出るでしょう。ただ、中長期的にみれば人材を重視した経営にシフトすることは働き手にとってプラス材料です。どうすれば社員の能力ややる気を高められるか、企業は今まで以上に真剣に考えるでしょう。キャリアアップに追い風です」
「今後人的資源に関する情報開示が進んだら、それを判断材料に勤務先を選ぶこともできます。そのとき大切なのは先述したとおり、情報開示データから企業の経営戦略と人材戦略を読み解くことです。どんな働き方がしたいのか。自分の希望に沿う会社を今まで以上に見つけやすくなるでしょう」
(編集委員 石塚由紀夫)
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。