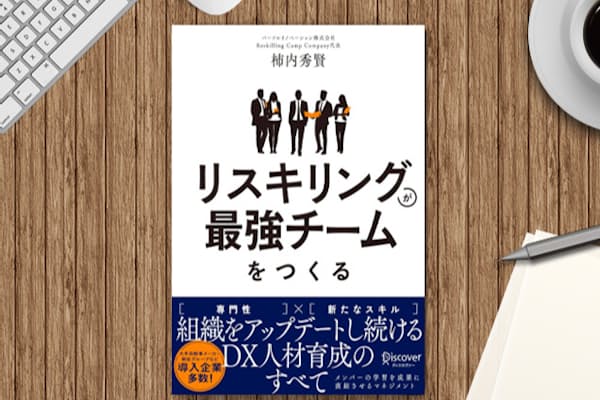出産すると不利?「チャイルドペナルティー」どう防ぐ
ダイバーシティ男女の賃金格差が問題になっているなか、その元凶として「チャイルドペナルティー」が世界的に注目されている。出産前後で収入が下落する先進国共通の現象だ。特に日本はその傾向が著しい。チャイルドペナルティーは、女性が潜在能力を十分に発揮できていない証しでもある。先進企業は解消策を練っている。
短時間勤務でも減収は小幅 「仕事の質」変えず
「この求人条件では応募者が集まらない。条件を見直しませんか?」。エン・ジャパンの勝又美奈さんは顧客に労働需給の現状を説く。2012年に入社し、ずっと営業職。21年に長女を出産し、今年5月に復職した。
初めての子育て。フルタイム勤務は難しいと考え、短時間勤務を選んだ。同社の育児短時間勤務は2種類あり、勝又さんは給与と職務が一律に軽減されない「スマートグロース制度」を選んだ。通常の短時間勤務は原則残業禁止。それに伴い担当も定型事務などに移る。給与も労働時間の減少率に比例して減る。
一方、スマートグロース制度は基本給は同じく減額されるものの、みなし残業代が支払われるので減収は小幅。仕事の量は調整するが、仕事の質は基本的に変えない。「出産前と同様に営業の前線で働けるのがうれしい」

スマートグロース制度を使うエン・ジャパンの勝又美奈さん。短時間勤務だが、減収は小幅、やりがいのある仕事も担う(東京都新宿区)
子育て期のキャリアロスをどう防ぐか――たどり着いた解決策がスマートグロース制度だ。通常の短時間勤務に比べると仕事の負荷は高い。その分、月40~45時間分の見なし残業代を支給する。ただ残業は必須ではなく、実際の残業は平均月20時間程度だ。フレックスタイム勤務を併用できるので、仕事の繁閑と育児状況に応じて1日の就業時間を柔軟に調整できる。
年収500万円の社員が1日6時間の通常の時短勤務にすると概算で同340万円に減る。スマートグロース制度なら同410万円だ。人財戦略室長の平原恒作さんは「減収を抑えられるうえ、成長につながる仕事もできる」と説明する。