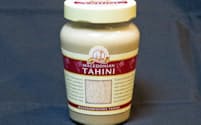世界農業遺産、琵琶湖の魚も 地方活性化イタリアン
イタリア美味の裏側(18)イタリア食文化文筆・翻訳家 中村浩子

「イタリア料理とは、イタリアの地方料理の集まりである」――。イタリア料理好きならこのフレーズを、耳にタコができるほど聞いてきたことだろう。イタリアでは、気候や風土の違う、その地方にしかない産品を使うことによって、地方独自の料理が生まれてきた。その料理が希少な産品を広く知ってもらうきっかけとなり、生産者の励みや支えとなって、観光にもつながっている。今、日本の地方のイタリア料理にも同じような流れが起きている。いわば「地方活性化イタリアン」が次々と生まれているのだ。
岡山県の倉敷美観地区は、白壁の蔵屋敷など古い町並みが続く観光地区。その一角にあるのが「くらしき 窯と南イタリア料理 はしまや」(以下「はしまや」)である。この店の楠戸伸太郎オーナーシェフは、この地で明治初期に創業した老舗呉服店に生まれ、楠戸シェフの時代になって店舗だった古民家をイタリア料理店に改装した。楠戸シェフは、岡山県北部と南部で大きく異なる気候・風土から生まれた幅広い産品を積極的に使っている。

初夏にこの店を訪問した。その日のスープは、モモのスープ。岡山県といえば誰もが思い浮かべる代表的な果物がモモだ。夏になるとモモのパスタは全国のイタリア料理店のメニューに登場する。楠戸シェフが6月下旬に使うモモは、県内で最も早く収穫される総社市の露地栽培の早生(わせ)品種のモモ「はなよめ」。甘さは控えめながらも豊かな香りのこのモモのよさが、スープに生かされている。上には、塩こうじに漬けたシソを乾燥させたユカリを振り、甘味と塩気のマッチングを楽しむ。
メイン料理の1つは、「揚げ穴子の麹(こうじ)トマトソース」。丸本酒造(岡山県浅口市)の日本酒「竹林」のこうじを使ったトマトソースに、自家製コチュジャンをしのばせて味に奥行きを出している。トマトはワッカファーム(岡山県瀬戸内市)が農薬や化学肥料を使わず露地栽培で育てたサンマルツァーノ・タイプ。アナゴも、ソースに隠れたハマグリも、岡山県の瀬戸内地方名産の海産物である。

手打ちパスタの1つは、「サフランを練りこんだタリオリーニ 山ウドとナスのソース」。パスタは、「しらさぎ」という岡山県ほか瀬戸内地方特産のコムギを石臼でひいた粉を使っている。かつて四国の讃岐うどん作りにもこの「しらさぎ」が使われていたほど人気だったが、2010年代になって岡山県の奨励品種でなくなり、生産農家が少なくなった希少品種だ。
器は骨董の陶器を好んで使う。「曽祖父が器や小物が好きで集めていたんですよ」と楠戸シェフはいう。倉敷に根づいて約250年になる楠戸家には貴重な骨董の陶器が多く残されていたせいか、父の時代に、陶芸家の浜田庄司や河井寛次郎、バーナード・リーチが訪れたこともあるという。
古民家を街並みごと生かし、骨董を大切に使うことは、環境を守ることにもつながる。その点も注目されたのか、同店は「ミシュランガイド岡山2021」において、環境やサステナビリティー(持続可能性)への配慮を評価するグリーンスターが与えられたのだった。新型コロナウイルス渦中では地元の常連客に支えられたものの、もともと観光地区にある同店が世界的なグルメガイドに評価されることで、さらなる観光客を呼び寄せることになった。
ビワマスや小アユ… 豊かな湖の魚を堪能

一方、滋賀県琵琶湖畔の近江八幡市には、「琵琶湖イタリアン」を謳(うた)うイタリア料理と手作り弁当の店「Vite(ヴィーテ)」がある。高岡洋文オーナーソムリエは大学時代にイタリア語を専攻し、ローマの日本国大使館で働き、イタリアソムリエ協会のソムリエ資格を取得。京都のリストランテ数店に勤めたあと、細君の母親が経営していた近江八幡市の弁当店を引き継ぐのと前後して、イタリア料理店を開いた。
「市の文化会館は公的な建物なので、最初はワインなどアルコール類が出せなくて悔しい思いをしました」と高岡ソムリエは苦笑する。店のコンセプトを考えるに当たって大切にしたのは、「滋賀県と近江八幡市、琵琶湖の素晴らしさを、イタリア料理を通じて表現すること」(高岡ソムリエ)だった。
料理を担当するのは、京都の老舗イタリア料理店からイタリアのミシュラン星付き店での修業を経て、京都のリストランテのオーナーシェフ時代に高岡ソムリエとタッグを組んでいた岩原信久総料理長。パナマ大使付き公邸料理人も務めたというユニークな経歴である。

6月末に特別にいただいたメニューは、「ビワマスの完熟トマトソース」「ブラックバスのフェンネル風味」「小鮎と新玉ネギのオレンジ入りマリネ」という前菜盛り合わせで始まった。サケ科のビワマスは薄いオレンジ色をした琵琶湖特産のマスで、琵琶湖にしかいない固有種16種のうちの1つ。とろりとした身がトマトソースの酸味と甘みに合う。
スズキ目サンフィッシュ科のブラックバスは琵琶湖だけでなく全国各地で繁殖している魚で、臭みがあるイメージだが、「湖水がきれいな湖北地域で獲れたものは特に癖がなく、食べやすい」(岩原シェフ)。高岡ソムリエによると、湖北の方が人口が少ないことと、河川一本だけから湖水が流出する湖南に比べて湖北には多くの川から水が流入することから、水質がよいという。小アユは、琵琶湖から川をさかのぼって大きくなったものと違い、10センチほどのアユで、初夏から夏が旬。丸ごと揚げてマリネした小アユの内臓のほろ苦さは、新タマネギの甘味とオレンジ果汁の爽やかさがアクセントになる。ヴェネツィアのイワシのサオールという南蛮漬けのような料理から、岩原シェフはイメージした。
自然と人間の優しい共存、琵琶湖システム

パスタの一皿は、「ウロリとネギのスパゲッティ」。ウロリはゴリとも呼ばれ、琵琶湖に生息するヨシノボリというハゼの仲間の小魚である。つくだ煮などで食べられるが、この日はニンニクの風味を移したオリーブ油でさっと炒めたウロリをパスタとあえ、上に白髪ネギ、炒めたパン粉をシチリア風に散らした。
琵琶湖の湖魚はこれにとどまらない。「Vite」の高岡ソムリエと岩原シェフは、今年2月末に東京の滋賀県アンテナショップ「ここ滋賀」(東京・中央)で滋賀県のワインと琵琶湖イタリアンの会を催し、冬の季節の湖魚も紹介した。
スジエビを裏ごししたスープはエビのビスクにも負けないほどの濃厚さがあり、殻は粉にしてグリッシーニという細いパンに散らし、スープにつけて楽しんだ。年に数日しか漁の許可が下りないアユの稚魚、氷魚(ひうお)は釜揚げにし、市内の水耕栽培者「湧水の恵みファーム」の規格外レタスを使ったサルサヴェルデ(グリーンソース)と合わせ、ほのかな苦味を楽しむことができた。

折しも今年7月、琵琶湖と共生する滋賀県の農林水産業は、「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」として、国連食糧農業機関(FAO)から世界農業遺産に認められたばかりだ。琵琶湖のまわりの水田は、フナズシで知られるニゴロブナなどが遡上する場所で、湖魚に安全・安心な生育環境を提供してきた。また、エリ漁と呼ばれる待ち受け型の漁法は、水産資源を取り過ぎず、持続可能性がある。
「琵琶湖システムについては、実は僕はまったく知らなかったのですが、自然と人間の優しい共存の姿でもあり、滋賀県を世界にアピールする好材料になると思っています」と高岡ソムリエ。かつてイタリア料理店のシェフを中心とした活動により熊本県阿蘇地域が世界農業遺産に認められたとき、まだ認知度が低かったあか牛をシェフと生産者と熊本県が力を合わせてブランド牛に押し上げた。シェフやソムリエが生産者と消費者の間に立って地方の活性化に大きく貢献する姿は、これからもどんどん現れるだろう。
イタリア食文化文筆・翻訳家。東京外国語大学イタリア語学科卒。イタリアの新聞社『ラ・レプブリカ』極東支局長助手をへて、文筆・翻訳へ。著書に『イタリア薬膳ごはん』(共著)『「イタリア郷土料理」美味紀行』、訳書に『イタリア料理大全 厨房の学とよい食の術』(共訳)『スローフード・バイブル』。
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。